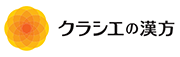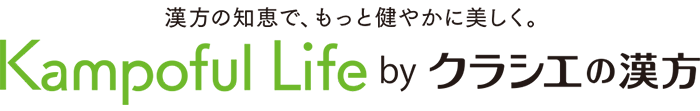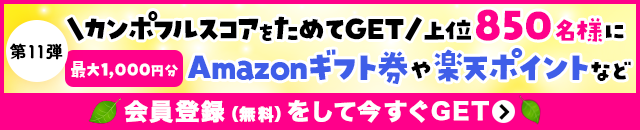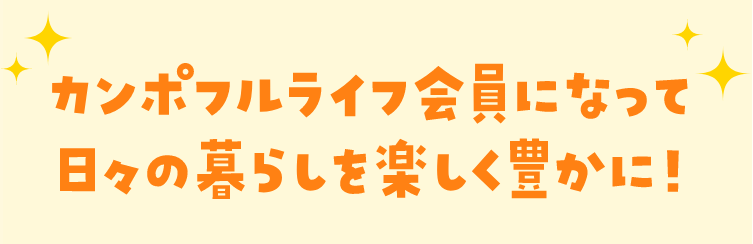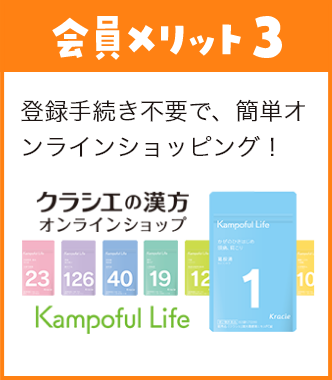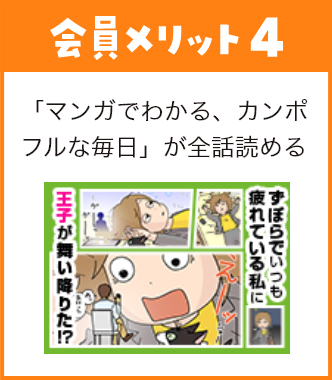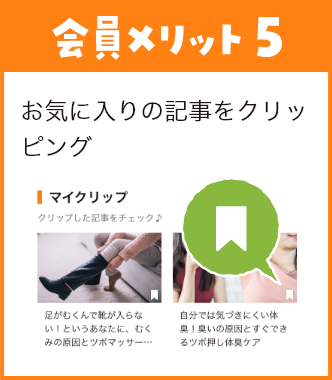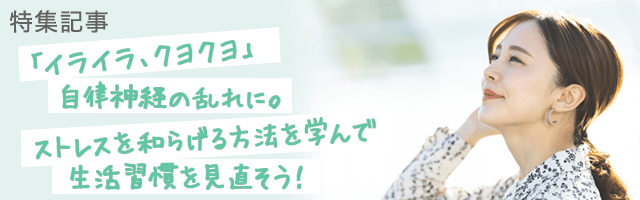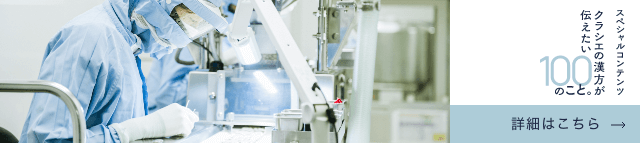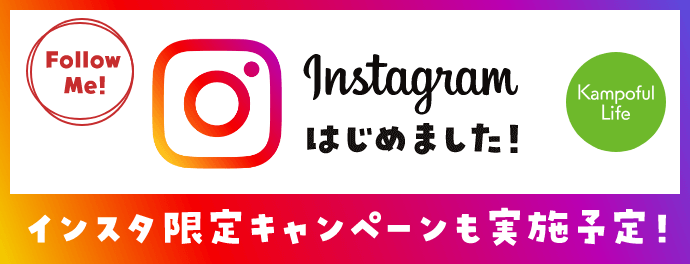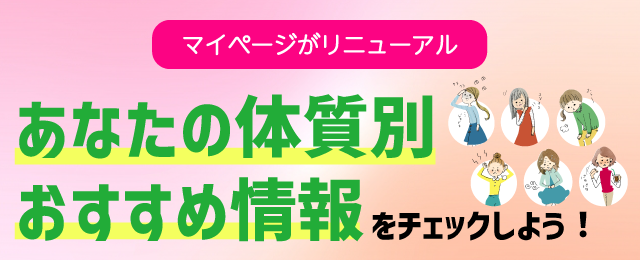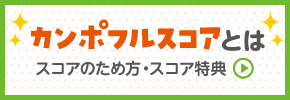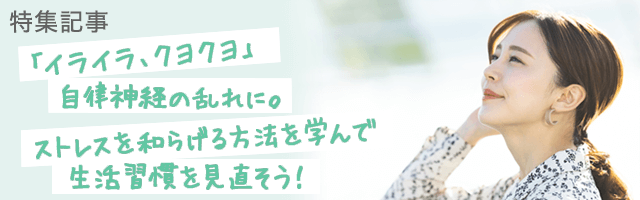目次
- ホルモンバランスと腸内環境の密接な関係
- 腸内環境のためにデブ菌と痩せ菌の存在を知る
- 腸内フローラのチェック方法
- デブ菌or痩せ菌のセルフチェック!
- ホルモンバランスを整えるには
- 漢方で腸内環境とホルモンバランスを整える
ダイエットは永遠のテーマであり多くの人が試行錯誤を重ねていますが、簡単に痩せられるダイエット法は「存在しない」とほとんどの方が分かっていることでしょう。それもそのはず、カラダによい食事と適度な運動をして、たっぷり寝てしっかり排泄していれば無駄に太ることはありません。思うように痩せられない大きな理由は「ストレス」によってカラダや思考のメカニズムが狂ってしまうこと。つい食べ過ぎてしまう、運動をだるく感じてしまう、という理由の多くはストレス。ほとんどの場合、ストレスによって脳がホルモン分泌を誤作動させ、お腹は減っていないのに暴飲暴食や甘いものの摂取を促したり、それによって睡眠の質が落ちたり、排泄を滞らせたり…といった悪循環に陥ることで肥満やむくみへと導かれてしまいます。この記事ではホルモンバランスと腸内環境(デブ菌、痩せ菌)の関係の紐解きから、カラダをトータルに調整する方法までをご紹介していきます。
ホルモンバランスと腸内環境の密接な関係
「ホルモン」とは、カラダの器官である内分泌腺から作られる化学物質のことです。ホルモンは様々な細胞に作用して、カラダの機能を調節したり成長を促したりする役割を果たしています。例えば、脳下垂体から分泌される成長ホルモンは、子供の成長を促すだけでなくカラダの修復をしたり、免疫力を高めたりする働きもあります。甲状腺から分泌される甲状腺ホルモンは、カラダの代謝を調節します。副腎から分泌されるアドレナリンは、カラダの危機反応を促します。
一方で「腸」は食べ物を消化して栄養を吸収し、便を作って排泄する臓器として知られていますが、腸の働きはそれだけではありません。腸の中ではホルモンやビタミンなどが合成されているほか、免疫細胞の約7割が腸に集中しているのです。腸内で産生されるホルモンは、体内の様々な機能を調節しています。そのため、腸内環境が乱れることで肥満、糖尿病、高血圧、動脈硬化、がん、うつ病など多様な疾患につながる可能性があることがわかっています。健康的な腸内環境は、ホルモンの生成や代謝に寄与し、結果的にホルモンバランスを保つ助けとなるのです。脳と腸は自律神経やホルモンを介して、相互に情報を送り合っています。このような脳と腸がお互いに影響を与え合うことを脳腸相関といい、ストレスによって腹痛が起こったり、逆に甘いものに手が伸びたりということが実感として理解できるかもしれませんね。
腸内環境のためにデブ菌と痩せ菌の存在を知る
腸内には様々な菌がいるためその様子がお花畑のようであることから腸内フローラと呼ばれています。腸内細菌の中でも「ファーミキューテス門」と呼ばれている腸内細菌類は通称”デブ菌”と呼ばれ、その反対に「バクテロイデス門」と呼ばれている腸内細菌は通称”痩せ菌”と呼ばれています(「門」というのは、生物を大まかに分類するグループのひとつ)。なぜこのような名前がついたのでしょうか?
この研究を始めたのは、微生物学者のアメリカのジェフリー・ゴードン博士で、痩せている人と太っている人の腸内環境に違いがあるのかどうかを研究していく過程で、痩せている人の腸内にはデブ菌「ファーミキューテス門」よりも、痩せ菌「バクテロイデス門」が存在していることを証明しました。デブ菌は、栄養を吸収するために必要な腸内細菌で、この菌が減少してしまうと栄養を腸内で吸収することができなくなってしまいますが、このデブ菌が多くなりすぎてしまうと、脂肪を必要以上に溜めこんでしまい、結果的に太りやすくなってしまいます。デブ菌に分類されているどの固有の菌が主な働きをしているのかは現在も研究している段階ですが、腸内環境が肥満とどのような関係があるのかを示すことができた貴重な研究であったとされています。
その反対に痩せ菌が多くなると脂肪の吸収を抑制してくれるだけでなく脂肪燃焼を促してくれますが、この菌が多くなりすぎると必要な脂肪まで燃焼されてしまいます。そのため、どちらの菌も腸内で効果的に働いてもらうためには、バランスが重要になってくるのです。理想的なバランスは、「デブ菌4・痩せ菌6」と言われています※1。デブ菌は多くなりすぎると、おならを増やすとも言われています。おならを増やすことは、腸内の”悪玉菌”が関係していますが、実はデブ菌は悪玉菌に属してはいません。腸内には悪玉菌と善玉菌の2種類に加えて、そのどちらにもなれる“日和見菌(ひよりみきん)”と呼ばれるカメレオンのようなカテゴリーが存在します。デブ菌も痩せ菌も共に日和見菌に分類されているため、腸内で優勢な方に味方をする性質があります。善玉菌が優勢であれば腸内環境も悪化しませんが、デブ菌は栄養分を体内に吸収しようとするため、動物性タンパク質や脂肪の多い食事などを多く摂取すると、これらが悪玉菌の好物となり、おなら増加につながってしまうのです。※1日本人を対象にした最近の研究では肥満との関係については、ファーミキューテス門やバクテロイデス門の菌の割合だけで判断するのは不十分であると指摘され、菌の多様性が重要だとされています。
腸内フローラのチェック方法
腸内フローラが整っているかどうかを調べるためには、病院できちんとした大腸検査を受けるしか方法はありませんが、費用がかかってしまうだけでなく気軽にチェックするというわけにもいきません。腸内フローラがどんな状態なのか知りたい場合には、自宅でできるかんたんセルフチェックから始めてみましょう。
<チェック1> 便の状態を見る
便で毎日健康チェックをすることができます。どのような状態で出てきているのかを水に流す前に確認してみましょう。
☑形がバナナ状、適度な水分がある便
理想的な便の状態です。
さらに臭いがきつくなく、黄土色で軽く水に浮いていれば全く問題ないでしょう。このような便であれば、腸内で善玉菌と悪玉菌がバランスの良い状態でいることがわかります。
☑毎日排便がない、便秘気味
毎日排便がなく便がかための場合、腸内のバランスが崩れている可能性があります。通常は、腸内で便が時速10cm程度の速さで進んでいきますが、これよりも遅くなってしまうと水分が腸内でどんどん吸収されてしまい、便がかたくなってしまいます。水分の吸収された便は水に沈み、色も黒くなっていきます。
☑下痢気味、軟便気味
水分量が多くて便の形が崩れたり、下痢気味になったりしている場合は一緒に善玉菌が排出されてしまうため、腸内フローラも乱れてしまいます。善玉菌が減ってしまうと悪玉菌が優位になり、様々な体の不調が引き起こされる可能性があります。
<チェック2> おなら、便のニオイを確認する
腸内フローラが整っていると善玉菌が優勢となり、腸内は弱酸性になっているので、おならも便の匂いも発生しないことが多いです。でも悪玉菌が優勢になってしまうと、便が腸内で腐敗して臭いが強くなったり、鼻をつくような臭いが発生したりしやすくなります。また野菜や果物を食事に多く取り入れている場合と、肉料理を取り入れている場合にも臭いに違いがあります。
<オプション編> 腸内フローラのバランスを専門機関に調べてもらう
腸内フローラが整っているかどうか知るために、便を専門の機関に郵送してバランスを調べてもらうことができます。申し込みをすると専用のキットが送られてくるので、その手順に従って便を送ると数週間程度で結果が手元に届きます。これらの検査によって、今まで悩んでいた便に対してのアドバイスや肥満との関係性、細菌の割合や腸内の菌の構成など、様々な項目から自分の腸内がどのような環境なのか、腸のタイプがどんなタイプなのか、見えないけど気になる部分が分かるようになっています。自分の腸内フローラの状態が数値で確認できるので、気になる方はチェックしてみましょう。
デブ菌or痩せ菌のセルフチェック!
自分の腸内フローラがどうなっているのか、20項目の中から当てはまるものをチェックしてみましょう。あなたの腸内フローラは、デブ菌と痩せ菌どちらが多いでしょうか?
- 1. 食事は野菜よりも肉中心だ
- 2. 暴飲暴食、不規則な食生活になりがち
- 3. 間食が多い
- 4. 少食でも太め
- 5. 幼少期からどちらかというと太め
- 6. きつい食事制限を定期的にしている
- 7. 運動をする機会がない
- 8. ダイエットに成果を感じない
- 9. ダイエットをやめるとリバウンドしてしまう
- 10. イライラすることが多い
- 11. よく風邪を引く
- 12. 寝つきが悪い
- 13. 思い詰めて悩むことが多い
- 14. 肌の調子が悪い
- 15. 花粉症を患っている
- 16. 怪我や傷がなかなか治らない
- 17. 排便の時間が不規則
- 18. 排便後すっきりしないことがある
- 19. 便秘や下痢をすることがよくある
- 20. 便やおならの臭いがきつい
上記の項目がいくつ当てはまるかで腸内フローラの状態をある程度確認できます。
・該当項目0~1個
痩せ菌が優位で、デブ菌は少ない状態
・該当項目2~4個
痩せ菌とデブ菌が半々の状態
・該当項目5~8個
痩せ菌が若干少なく、デブ菌が増えている状態
・該当項目9個以上
痩せ菌が極めて少なく、デブ菌が圧倒的に優位な状態
あなたの腸内フローラはどんな状態でしたか?
ホルモンバランスを整えるには
腸内環境を適切に保つことがホルモンバランスを整えるためには重要であることをお伝えしてきました。そのためには、①規則正しい食生活、②充分な睡眠、③適度な運動、が大切です。
1つ目の規則正しい食生活は、腸にダイレクトに関わるため非常に重要です。2つ目の充分な睡眠は、ホルモンバランスを整える鍵を握ります。3つ目の適度な運動は、腸の蠕動運動を活発にして排便を促し、カラダを巡らせるために必要です。最後に、『ストレス』はホルモンバランスを乱す、想像以上にカラダに悪いものであるためストレスを溜めないようにすることもホルモンバランスを良い状態に保つためにとても大切なことです。
★知っておこう!「幸せホルモン」の種類と増やし方
日常でストレスを感じることが多い場合、そのモヤモヤは自ら意識的に「幸せホルモン」を出すことでも対処ができるはず。4種類の幸せホルモンと呼ばれるものとその増やし方を知っておきましょう。
| ホルモン | 主な効果 | 増やし方の例 |
| オキシトシン (愛情とおもいやり) |
ストレス緩和、癒し、信頼感、学習意欲向上、心肺機能向上 | ふれあい(人・ペットとの直接又は心のつながり)、感動する行動、ビタミンCの摂取 |
| セロトニン (安心とリラックス) |
安心感、リラックス、幸福感、自律神経の安定、体温調節、睡眠の質向上 | 日光浴、有酸素運動、タンパク質(トリプトファン)の摂取、咀嚼、睡眠 |
| ドーパミン (ポジティブとやる気) |
快感、ポジティブ感、達成感、運動調節、行動力 | 目標達成、運動の習慣化、褒められる、笑う、チロシンを含む食品の摂取 |
| エンドルフィン (高揚感と満足) |
高揚感、集中力、記憶力向上、免疫力、回復力、鎮痛 | ランナーズハイ、好物の摂取、強い信念を持つ、運動、ときめく |
①食事で実践!腸内環境を整える
腸内環境の改善には、プロバイオティクスを摂取することが効果的です。プロバイオティクスとは、善玉菌のことです。善玉菌は、腸内で有害な菌の増殖を抑え、腸内環境のバランスを整えてくれます。プロバイオティクスは、ヨーグルトや納豆などの発酵食品に多く含まれています。サプリメントとして摂取することも可能です。
また、プレバイオティクスを摂取することも腸内環境の改善に効果的です。プレバイオティクスとは、善玉菌の餌となる食物繊維のことです。プレバイオティクスは、バナナや豆類、ゴボウなどの野菜に多く含まれています。
腸内環境の改善には、規則正しい食生活と適度な運動も効果的です。規則正しい食生活は、腸内環境のバランスを整えてくれます。適度な運動は、腸の蠕動運動を促進し、便通を改善してくれます。水分不足は便が硬くなり、便が腸内をスムーズに移動できず便秘の原因になるため水分を十分に摂ることも大事です。
◆プロバイオティクスとプレバイオティクスとは
| プロバイオティクス | プレバイオティクス | |
| 定義 | 乳酸菌、ビフィズス菌、麹菌、納豆菌などの善玉菌を食事から摂取すること | 善玉菌のエサとなる食物繊維やオリゴ糖を摂取すること |
| 代表的な菌 | 乳酸菌、ビフィズス菌、納豆菌など | オリゴ糖、食物繊維 |
| 代表的な食材 | ヨーグルト、納豆、みそ、ぬか漬け、キムチ、甘酒など | ゴボウ、オクラ、アボカド、キウイ、りんご、バナナ、海藻類、きのこ類、芋類、豆類 |
②光浴で睡眠の質を高めて腸内環境を改善
睡眠不足は、食欲増進ホルモンの分泌を増加させ、代謝を低下させるため、ダイエットの大敵です。質の高い睡眠を十分に取ることで、腸内環境を安定させダイエットを効果的に進めることができます。ストレスを感じると、自律神経のバランスが乱れ、腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)が弱まります。また、ストレスは悪玉菌を増やし、腸内環境を悪化させる原因にもなります。
光の効果は体内時計を24時間に調節することにあります。ヒトの体内時計の周期は24時間より長めにできているため、体内時計を毎日早める調節をしないと、ずるずると生活が後ろにずれてしまいます。朝の光には後ろにずれる時計をリセットさせる作用があります。起床直後の光が最も効果的なので、起きたらまずカーテンを開けて自然の光を部屋の中に取り込むことが必要でしょう。禁物なのは夜の光です。朝の光と反対で夜の光は体内時計を遅らせる力があり、夜が更けるほどその力は強くなります。家庭の照明(照度100~200ルクス)でも、長時間浴びると体内時計が遅れます。また日本でよく用いられている白っぽい色味の蛍光灯の明かりは体内時計を遅らせる作用があるため、電球色のような暖色系の明かりが理想的と言えます。
③ホルモンバランスを整えるエクササイズ
筋力トレーニングは、成長ホルモンや筋肉・骨格の発達を促すテストステロン等のホルモン分泌を促します。これらのホルモンは、筋肉量の増加や脂肪の減少を助けるだけでなく、代謝を活性化させます。特に年齢を重ねると、ホルモンバランスが崩れがちになりますが、定期的な筋トレでそのバランスを保つことが可能です。さらに、筋肉量が増えると基礎代謝が上がり、体重管理にも役立ちます。筋トレだけでなくストレッチは柔軟性を保ちながら、血流を改善し、リラクゼーション効果をもたらします。これはストレスの軽減につながり、ホルモンの安定に寄与します。さらに、ストレッチによって身体がリラックスすることで、睡眠の質が向上することもダイエットやアンチエイジングには重要です。まずは無理なく毎日できるヨガのポーズやストレッチをご紹介。できるものから試してみましょう。
★ヨガのポーズ「バッダ・コーナ・アーサナ」(合蹠(がっせき)のポーズ)
<効果>
股関節(鼠径部)周りの筋肉を緩めながら前屈など動きをつけることで、骨盤内への血流を促進します。ホルモンバランスを整え更年期や妊娠期の不調や月経痛緩和に効果があります。男女問わず、股関節周辺の血流が良くなることは、尿疾患の予防や生殖機能の向上、下半身の臓器の働きを調整するといった、さまざまな効果が期待できます。
◆注意する点やポイント
「あぐら」の姿勢に似ていることから簡単そうに見えますが、骨盤が後ろに倒れて背中が丸まってしまう、ひざの高さに左右差ができてしまうことがあります。無理のない範囲で行いましょう。前屈の動作が難しい場合は、ブランケットやタオルをお尻の下に敷いて骨盤が前に倒れやすいよう工夫をしてみて下さい。
(やり方)
1:床に座り足の裏を合わせましょう。両手はつま先又は足首を掴みます。
2:そのままカラダを左右にゆっくり揺らします。座骨(骨盤の下部)が交互に床から離れるように大きく動き、股関節からお尻までゆっくりほぐします。
3:膝をゆっくりと床から離し、ゆっくりと床に戻す動作を繰り返します。慣れてきたら、蝶蝶が羽を動かすイメージでパタパタと軽やかに動かしてみましょう。この動きを10回ほど続けることで鼠径部から太もも内側の内転筋、太もも裏のハムストリングスがほぐれます。
4:息を吸いながら背骨を伸ばし、息を吐きながら、ゆっくり上体をできるだけまっすぐにしたまま前に倒していきます。この時、顎は軽く引き首の後ろを伸ばすように意識し骨盤から倒している意識を持ちましょう。そのまま呼吸を数回続け、息を吸いながら上体を戻しましょう。


★ヨガのポーズ「キャット&カウ」(猫と牛のポーズ)
<効果>
背中を丸めた猫が由来のキャットポーズと背中を反らせる牛を彷彿とさせるカウポーズがセットになっており、シンプルで取り組みやすい動きです。神経の集まる脊柱を動かすことで自律神経の働きを整え、姿勢改善が期待できます。呼吸とともに腹部と背部を動かすため便秘改善やインナーマッスル強化にもつながります。
◆注意するポイント
四つん這いの姿勢で膝の真上に腰骨、手首の真上に肩がくるようにセットします。背骨を動かしても両腕と両太ももが床と垂直な状態を保ちましょう。膝や手首が痛い場合はその下にタオルなどでクッションをつくると痛みをカバーできます。
(やり方)目安5~10回程度
1.四つん這いになり、手と膝を肩幅に開きます。お腹のお肉が床方向に落ちないようにお腹を引き上げておきます。
2.息を吸って準備を整え、吐く息と共に骨盤を後傾させながら背中を丸め、顎を引くように目線をお腹方向へ向けていきます(猫のポーズ)。
3.息を吸いながら骨盤を前傾させ背中を反らせて首を長く伸ばし、目線は遠く上方に向けます(牛のポーズ)。
4.呼吸と共に繰り返します。

★もっと頑張れそうな方は以下のページからワイドスクワットにチャレンジ
漢方で腸内環境とホルモンバランスを整える
中医学では「脾(ひ)」は消化器系の主要な臓器とされ、全身のエネルギー供給や免疫機能に深く関わっているとされます。脾の機能が低下すると、消化不良、倦怠感、下痢や便秘などの体調不良が現れやすくなります。ストレスでイライラする場合にはカラダを流れる「気(エネルギー)」が滞り、カラダの症状として腸内は環境が悪化しお腹がぽっこりと出たり、便秘気味になったりすることがあります。脾の働きにフォーカスすることで腸内環境を改善し、気の巡りにアプローチすることでホルモンバランスを整えストレス太りを解消していきましょう。
■ 防已黄耆湯(ぼういおうぎとう)
疲れやすくて、ぽっちゃりとした方に
「水」の巡りを整え、カラダの余分な水分の排出を促すため、むくみや水太りの改善に効果があります。さらに胃腸機能を高めて「気」を補うことで代謝を活性化させるため、体力があまりなくぽっちゃりとした肥満に悩む方に効果的です。
■ 防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)
お腹周りの余分な脂肪や便秘が気になる方に
体力があり、暑がりで、お腹に脂肪がたまりやすく、便秘がちな方におすすめです。カロリーオーバーで排出がうまくいかない方に効果があります。生活習慣病やメタボリックシンドロームの内臓脂肪型肥満の方にも適しています。
■ 大柴胡湯(だいさいことう)
イライラとストレスを溜め込みやすい方に
「気」の巡りを良くし、自律神経の緊張を和らげる効果が期待できます。また、炎症を抑えたり、カラダの熱を冷ましたりする作用もあり、特に消化器系の不調を抱える方に適しています。ストレスが原因で太りやすいタイプの方に効果的です。
<PR>
-

- 肥満や便秘の気になる方に
肥満に効果的な漢方の選び方
- 詳しく見る

那須久美子
広告会社、大手化粧品会社宣伝部にてCM、雑誌等の広告制作に携わる。
その後フリーランスとしてバレエ講師、ピラティスマスターストレーナー、ヨガセラピスト、介護予防運動指導員として老若男女への伝える仕事に従事。
企業や官公庁での健康アドバイザーや研修講師も務める。
国家資格キャリアコンサルタントとしては企業内障害者ジョブコーチを経て自治体事業の就労支援プログラム講師とカウンセラーを兼任。
現在は就労支援事業の現場統括責任者を務める傍らキャリアコンサルタントのスクールにおいてオウンドメディアの監修も担当。
・ヘルスケアデザイナー
・バレエティーチャー
・ピラティストレーナー、ヨガセラピスト
・アスリートキャリアコーディネーター
・国家資格キャリアコンサルタント
・漢方アドバイザー
・介護予防運動指導員
HP:https://www.kandworks.com/about