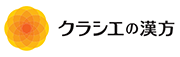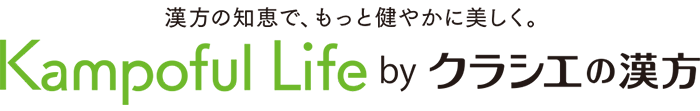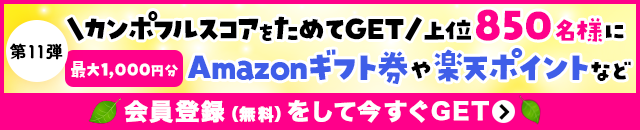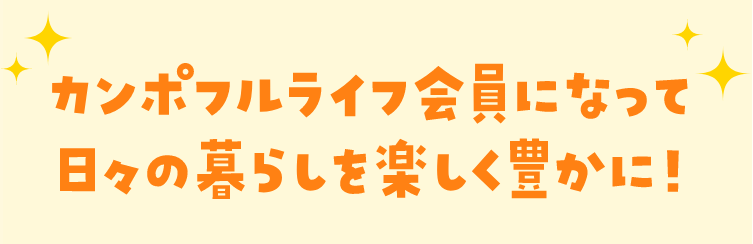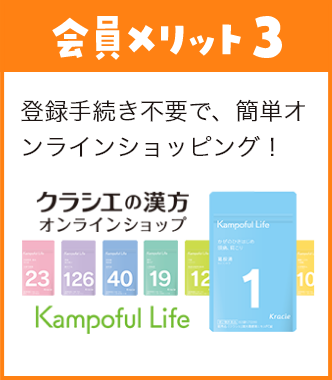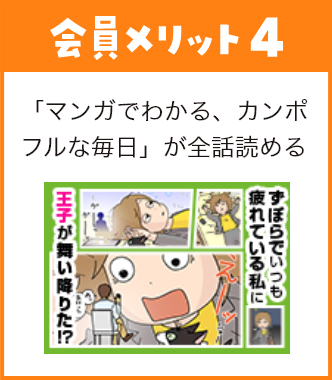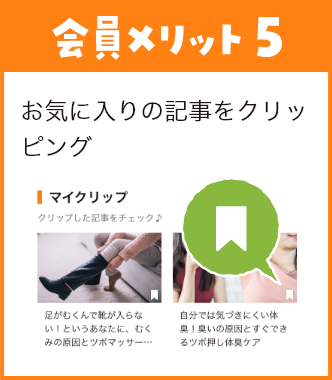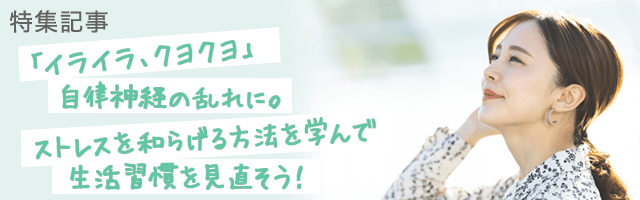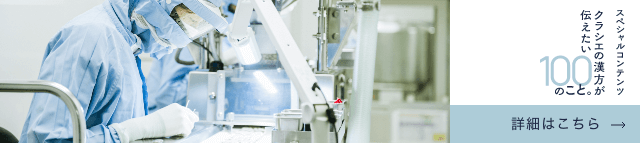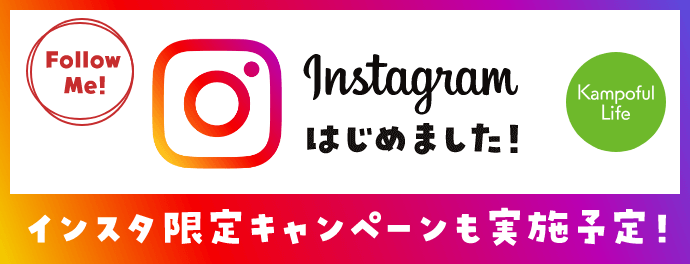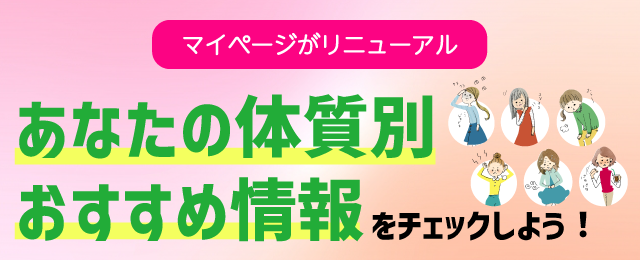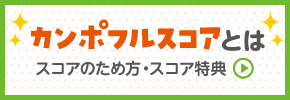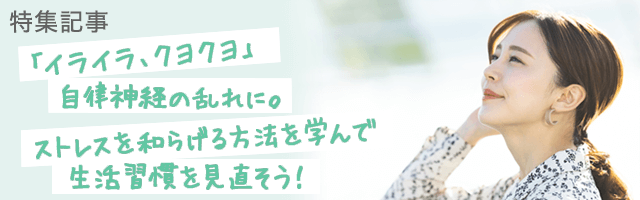目次
- 血行不良とは?しびれの原因
- なぜ血行不良が起こるのか?
- 血行不良に、今すぐ試せる改善方法
- 手軽にできる血行促進方法
- 血行を促進するお風呂の入り方
- 血行を促進する食べ物
- しびれを感じる方におすすめの漢方薬
健康的なカラダを維持するには、血行を良い状態に保つことがとても大切な要素です。
特に、手足のしびれは血行不良が原因で起こることが多いため、早めの対策が必要です。血液の流れが悪くなると、手足の末端まで酸素や栄養が行き渡らなくなり、神経が圧迫され痛みやしびれを起こす場合があります。血行促進をすることで手足のしびれを改善できる可能性があります。今回は、手足のしびれが起こる原因や改善方法を紹介します。
血行不良とは?しびれの原因
冬に起こりやすい痛みやしびれが起きる原因のひとつに、冷えによる血行不良があります。血行不良は、カラダを温めることで一時的に良くなることはありますが、長時間のデスクワークや運動不足がつづくと元の状態にもどってしまうことがあります。
漢方では、血行不良の状態を瘀血(おけつ)と言い、カラダの血液の流れが滞り、巡りが悪くなっている状態を指します。瘀血体質の方には、シミやアザができやすい・冷えのぼせが起こりやすい・目の下にクマができやすいといった特徴があります。
血行不良を改善するには、毎日の生活の中で無理のない工夫が必要です。血行不良をそのまま放置すると、慢性的な痛みやしびれといった症状が起こる可能性があります。
なぜ血行不良が起こるのか?
漢方で考える血行不良が起こる原因には、気(エネルギー)が不足した気虚(ききょ)、カラダの中に余分な水分が滞る水滞(すいたい)、気血の流れが悪くなる気滞(きたい)などがあります。
気虚(ききょ)とは
気(エネルギー)が不足している状態です。
気虚の原因は十分な栄養が取れていないことや睡眠不足などがあります。
水滞(すいたい)とは
カラダの中に余分な水分が滞っている状態です。
水滞の原因はカラダの冷えや水分のとりすぎなどがあります。
気滞(きたい)とは
カラダの中に気が滞っている状態です。
気滞の原因はストレスや不規則な生活などがあります。
また、加齢による血行不良は、運動不足・喫煙・飲酒など生活習慣の乱れが関係している場合があります。特に、ストレスによる自律神経の乱れも、血行不良の原因になると考えられています。
血行不良に、今すぐ試せる改善方法
血行不良の改善には、カラダを温めることを意識することがとても大切です。ただし、単にカラダを温めるだけでは血行不良の改善とはなりません。日常生活にとり入れやすい改善方法を紹介します。普段の生活にとり入れていきましょう。
しびれを和らげるツボを押す
①血海:血の巡りを良くするツボ
「血海(けっかい)」のツボは膝の皿の内側の角から指3本分上にあります。血の巡りが悪くなったときに押すツボで、血行促進に効果があります。太ももに対して、上から垂直に押します。

②三陰交:冷え性を改善させるツボ
三陰交(さんいんこう)のツボは、足の内くるぶしから指の幅4本分上にあります。冷え性を改善させるツボで、カラダ全体の血行の巡りを良くしてくれます。ゆっくり圧痛を感じるくらい押すのがコツです。

朝食には、温かいものを摂る
朝は空腹で体温が低い状態です。温かい食事を摂ることは、血行を促進し体温を上げる効果があります。白湯やお粥はカラダの内側から温めてくれます。カラダを温めることにより、内臓の働きを高めます。
ストレスをためない
ストレスは自律神経のバランスを乱すため、冷えを起こす原因と考えられています。日頃からストレスをためないような生活を送ることも、予防のひとつです。ストレスを感じたら、一度その場所から離れて深呼吸をしてみることをおすすめします。
腹巻きでお腹を温める
冷えの自覚がなくても、お腹を触ってみて「冷たい」と感じたら、内臓が冷えている可能性があります。腹巻きでお腹を温めることにより内臓が温まり、カラダ中の血液循環が促進されます。できれば一年中腹巻きをつけることをおすすめします。
下半身に筋肉をつける
筋肉が衰えると血行が悪くなります。大きな筋肉群が集中している下半身を鍛えて、全身の血行を促進しましょう。下半身に筋肉をつけることで、基礎代謝を上げることができます。特に普段あまり運動しない方におすすめです。
お風呂に毎日入る
血行不良を改善するには、シャワーではなくお風呂に入るのがおすすめです。湯船に浸ると、温熱効果により血行が良くなります。じんわり汗がかけるくらいがおすすめです。長風呂は、気を消耗するため控えたほうがいいでしょう。
次に手軽にできる血行を促進するスクワットやお風呂の入り方について紹介をします。
手軽にできる血行促進方法
血行を促進するには、毎日の生活の中で簡単に続けられる方法がおすすめです。家事の合間や仕事の休憩時間に、ストレスに感じない範囲で試してみましょう。
<スクワット>
血行不良を改善させるには、生活の中で運動を習慣化することが大切です。どれだけカラダを温めても、栄養不足や運動不足が続くと血液の流れが悪くなるからです。下半身に筋肉を付けるには、スクワットがおすすすめです。
・スクワットのやり方
- 1.足を肩幅に開き、つま先は膝と同じ向きにしましょう。手は腰より上で、「両手を真っすぐ肩の位置に伸ばすスタイル」や「胸の前で腕を交差して組むスタイル」など、ご自身の負担にならない姿勢を選びましょう。
- 2.椅子に腰をかけるような感じでゆっくりと後ろに腰を落としていきます。
膝はつま先よりも前に出ないよう注意しましょう。 - 3.太ももと床が平行になるまで腰をおろしたら、ゆっくりと腰を上げます。
※スクワットの回数は、10回3セットが目安ですが、初心者は10回1セットから始めて、慣れてきたら回数を増やすとよいでしょう。
※下のイラストのように、最初は45度ほど腰を落とすクウォータースクワットからスタートし、慣れてきたら徐々に深めていきましょう。

深呼吸は副交感神経を活性化させる働きがあります。副交感神経が優位になるとリラックス状態になり、血流の流れが良くなります。
・深呼吸のやり方
1.楽な姿勢で椅子に座ります。
2.口からゆっくり息を吐き切ります。
3.口を閉じたあと、鼻からゆっくりと息を吸います。
4.ゆっくりと息を吐き出します。
5.この動作を5回ほど続けます。
<日常生活の注意点>
血行不良を改善させるためには、生活環境を改善させることが大切です。生活習慣を見直してみましょう。
カフェインを避ける
カフェインには利尿作用があるため、摂取しすぎるとカラダの水分が排出され、同時にカラダの温度を下げてしまいます。カフェインの入っているコーヒーや緑茶などは控えましょう。
カラダを締め付ける服装は控える
カラダにあっていないサイズや締めつけ感のある服は、カラダの血行不良の原因になる場合があります。ストレスの原因にもなるので、できるだけ自分のサイズにあった服を身につけるようにしましょう。
血行を促進するお風呂の入り方
お風呂は、ぬるめの38~40℃くらいが適温です。たっぷりのお湯にゆっくり浸かりカラダを温めることで血行を促進しましょう。お風呂に入れないときは、足湯や手浴(しゅよく)などの部分浴もおすすめです。
温浴効果をさらに高めるためには、漢方薬の材料として使われる生薬(しょうやく)を使用した薬用入浴剤を利用するのも良いでしょう。薬用入浴剤に使われる生薬には、よもぎ・ドクダミ・みかんの皮などがあります。
血行を促進する食べ物
薬膳では、食材にはカラダを温めるもの・冷やすものがあると考えられています。
血行不良を改善するためには、カラダを温める「温性(おんせい)」の食材を摂ることが効果的です。
温性の食材には、しょうが・ねぎ・にんにくなどがあります。温性の食材は、カラダの中の気(エネルギー)や血(栄養)などの巡りを良くする働きもあります。
しびれを感じる方におすすめの漢方薬
しびれを感じる方は、毎日の生活習慣を整えることが大切です。それでも良くならない方は、漢方薬を利用するのもひとつの方法です。自分の症状に合わせて選びましょう。
■牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)
体力は中等度以下で、足腰が重だるく、しびれや痛みなどでお悩みの方におすすめの漢方薬です。腰痛や排尿困難・頻尿・むくみなどの症状がある方にも適しています。
■独活葛根湯(どっかつかっこんとう)
体力は中等度またはやや虚弱で、肩こり・四十肩・五十肩などが原因のしびれにお悩みの方におすすめの漢方薬です。カラダの中に滞った余分な水分を外に出す働きがあります。
<PR>
多田有紀(https://x.com/sora_writer)
漢方薬膳コンサルタント