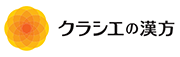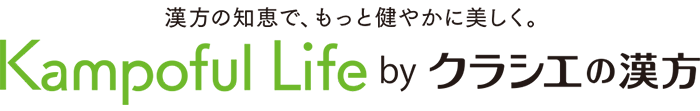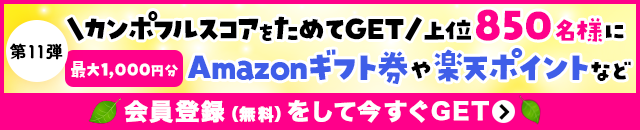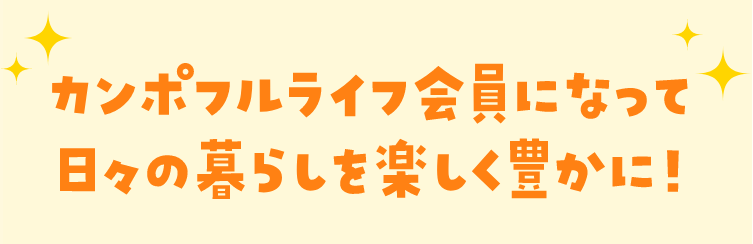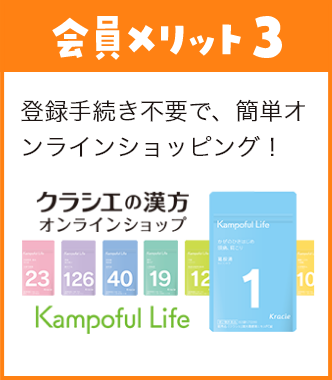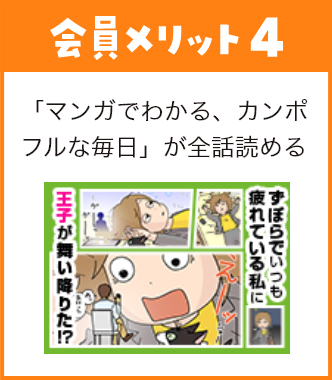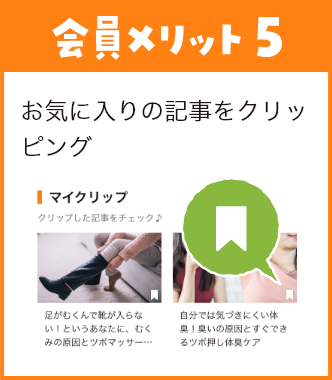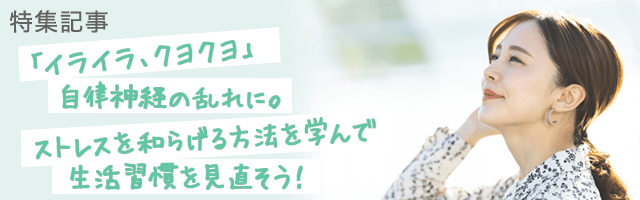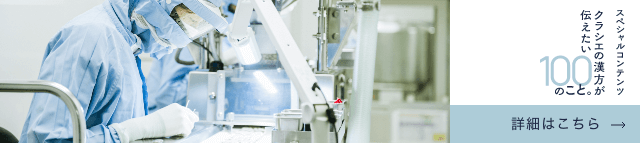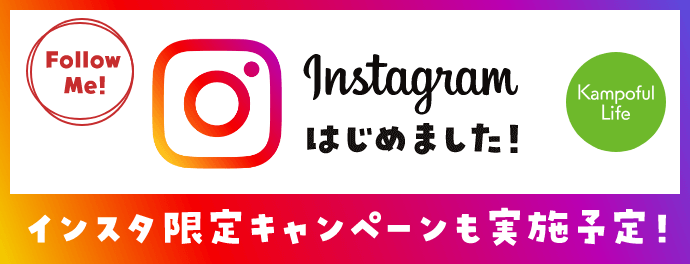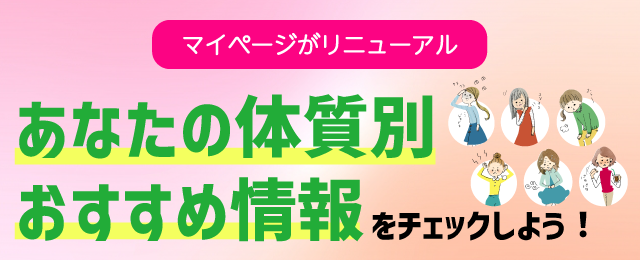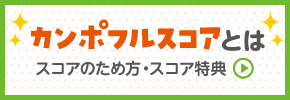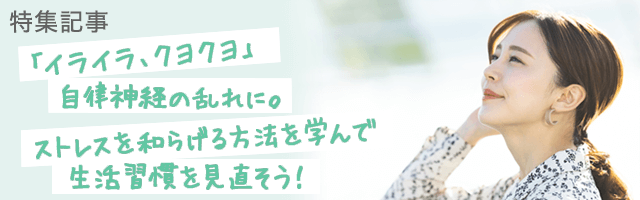目次
- 夜間尿とは何か?その定義と症状
- 夜間尿の主な原因とは
- 西洋医学・漢方で考える頻尿・夜間尿の原因
- 夜間尿が引き起こす健康への影響
- 漢方で考える、水分代謝を整えて夜間尿を改善する方法
- 頻尿・夜間尿におすすめの食材とは
- 夜間尿対処法:日常生活でできること
- 生薬による夜間尿の対処法
- 頻尿・夜間尿にはこの3つの漢方薬
頻尿や夜間尿に悩む人の中には、「水分を摂りすぎているのかも」と不安になり、外出時や寝る前の水分補給を控えている人もいるでしょう。
頻尿や夜間尿の原因は、水分の摂りすぎだけではありません。膀胱機能の衰えや、カラダの冷え・ストレスなども関係しています。頻尿・夜間尿を防ぐには、漢方で考える「腎」の衰えや不足を補うことが大切です。今回は、頻尿・夜間尿の原因や対策について紹介をします。
夜間尿とは何か?その定義と症状
頻尿・夜間尿には、トイレの回数が増えるといった共通点があります。頻尿は朝起きてから寝るまでの間の排尿回数が8回以上ある場合を指しています。ただし、排尿の回数は個人差があるため、1日の排尿回数が8回以下でも、日常生活に支障がある場合は頻尿と判断されることがあります。夜間頻尿(夜間尿)は、夜中に1回以上トイレに起きる状態を指しています。頻尿が起きる原因は、膀胱が過敏になり少量の尿で膀胱が過剰に収縮する「過活動膀胱(かかつどうぼうこう)」や膀胱炎といった感染症が多く、夜間尿の原因は加齢や生活習慣病などが挙げられます。頻尿・夜間尿が続くと、睡眠不足や集中力の低下、疲労などさまざまな症状があらわれます。糖尿病や高血圧といった生活習慣病が頻尿・夜間尿を引き起こすこともあり、放置せず適切な処置や対応が必要です。
夜間尿の主な原因とは
夜間尿の原因は、加齢・生活習慣病・薬の副作用・過剰な水分摂取などがあります。
<加齢>
年齢とともに膀胱の筋肉が衰え膀胱が収縮しやすくなるため、膀胱の容量が少なくなり夜中に何度もトイレに行きたくなります。この状態が続くと起きている時間が長くなるため、尿意も感じやすくなります。
<生活習慣病>
食事・睡眠・運動などのバランスが崩れて生活習慣病になると、夜間尿になることがあります。例えば、高血圧や糖尿病が進行すると、腎臓の機能が衰え尿を作る機能が低下し、カラダの中に余分な水分や老廃物が蓄積されてしまいます。
<薬の副作用>
夜間尿は薬を服用することにより起こる場合があります。例えば、利尿作用の強い薬を飲むと、昼だけでなく夜にも尿量が増えるため、トイレに行く回数が増えます。
<過剰な水分摂取>
寝る2~3時間前に水分を摂りすぎると夜間尿につながります。特に、コーヒーやアルコールは利尿作用があるため注意が必要です。また、味の濃いものを食べると血中の塩分濃度が高くなり、その濃度を薄めようと水分摂取が増えます。
西洋医学・漢方で考える頻尿・夜間尿の原因
西洋医学では、前立腺肥大症(ぜんりつせんひだいしょう)・過活動膀胱(かかつどうぼうこう)・骨盤底筋群(こつばんていきんぐん)の機能低下などが、頻尿・夜間尿の原因として挙げられています。
前立腺肥大は、尿の出が悪くなる、残尿感がある、頻尿・夜間尿などの症状があります。過活動膀胱は、膀胱が過敏状態になるため、尿意を感じやすくなります。骨盤底筋群は骨盤の底にある筋肉で膀胱・子宮などの臓器を支えており、この骨盤底筋群の機能が弱くなったり傷んだりすると、膀胱が圧迫され尿漏れや突然の尿意を起こすといわれています。
漢方では、五臓の「腎」の機能が低下した状態=「腎虚(じんきょ)」が頻尿・夜間尿の原因の1つと考えられています。
範囲と概念:漢方では「腎」は、生命エネルギーの管理や全身の健康維持に関わる広範な概念を含みますが、西洋医学の「腎臓」は主に尿生成と体内のバランス調整に焦点を当てています。
症状の捉え方:漢方では、腎の不調が全身のさまざまな症状に影響すると考えられますが、西洋医学では腎臓の機能低下が主に尿や血液の異常として現れます。
このように、同じ「腎」という言葉でも、漢方(中医学)と西洋医学ではその役割や概念が大きく異なります。どちらの視点も健康管理において重要ですので、バランスよく取り入れることが大切です。
漢方では、腎はカラダの成長や発達に関わる機能を担っており、腎の機能が低下すると成長の遅れや老化、水分代謝の低下といった症状が起こります。
水分代謝の低下は体内に余分な水分をためこみ、頻尿や夜間尿などの尿トラブルにつながる場合があります。
夜間尿が引き起こす健康への影響
夜間尿は睡眠の質を低下させ、日中の眠気・疲労感・集中力の低下・精神不安などにつながります。これらの症状は毎日の生活に大きな影響を及ぼす可能性があるため、夜間尿を放置せず適切に対処することが大切です。
高齢の方は夜中に何度もトイレに行くことで、転倒するリスクも高くなり怪我や骨折などにつながる可能性があります。また、基礎疾患がある方は、疲労や睡眠不足が原因で免疫力が低下し基礎疾患自体が悪化することもあります。
漢方で考える、水分代謝を整えて夜間尿を改善する方法
漢方では、慢性化した頻尿・夜間尿は、加齢による「腎の衰え」=「腎虚(じんきょ)」が関係していると考えられています。腎虚は、腎陽虚(じんようきょ)・腎陰虚(じんいんきょ)の2つに分類され、夜間尿は腎陽虚のタイプだと考えられています。腎陽虚は、夜中にトイレに行きたくなる・足腰がだるい・疲れやすくなる・足腰がむくむ・下半身が冷えるといった症状があらわれる特長があります。これらを改善するには、水分代謝を整えることがとても大切です。
<水分代謝を整える方法>
・冷えからカラダを守る
ウォーキングやストレッチなどの軽い運動をする、湯たんぽやカイロなどでカラダを温める、腹式呼吸でカラダの中の巡りをよくする、といったことを心がけましょう。カラダを温めると、血の巡りや水分代謝がよくなります。
・塩分の過剰摂取を控える
塩分を摂りすぎると喉が渇いて水分が欲しくなります。また、塩分の摂りすぎは、むくみの原因にもなります。塩分を摂りすぎた日は、強い運動よりもストレッチや散歩など軽めの運動がおすすめです。
・お風呂につかって代謝をあげる
お風呂に入ってゆっくりカラダを温めましょう。汗をかくことによりカラダの中の余分な水分を外に出すことができます。38℃~40℃位の温度のお風呂に10分ほど入りましょう。
・布団をこまめに干す
水分代謝が悪い人は、カラダの中に余分な水分が滞っている可能性があります。寝具や寝室の風通しをよくしましょう。天気のよい日は、布団を干したり、寝室の窓を開けて風通しをよくすることをおすすめします。
頻尿・夜間尿におすすめの食材とは
頻尿・夜間尿の改善には、次のような食材がおすすめです。
一般的な水分代謝を整える食材①:はとむぎ・小豆
カラダの中に余分な水分がたまりやすい体質には、はとむぎ・小豆などの食材がおすすめです。はとむぎ・小豆はご飯と一緒に炊くことができます。小豆を使った和菓子は砂糖が入っているためむくみやすくなります。調理する際はできるだけ砂糖を使わないようにしましょう。
一般的な水分代謝を整える食材②:銀杏・ハスの実
銀杏・ハスの実は、カラダから水分が出すぎるのを抑える働きがあります。銀杏はフライパンで焼いて食べるとほくほくとした食感を味わうことができます。ハスの実はご飯と一緒に炊くことができます。
漢方の腎機能を整える食材(腎虚):黒豆・黒ごま
夜間尿は、五臓の「腎」の機能低下により起こります。「腎」を補う食材には、黒豆・黒ごまがあります。煎った黒豆はそのまま食べられるおやつとしても販売されています。黒ごまは、ご飯やおかずにパラパラとふりかけて手軽に食べてみるのもおすすめです。
一般的なカラダを温める食材:鶏肉・人参
夜間尿はカラダが冷えることで起こります。鶏肉・人参など薬膳においてカラダを温める食材がおすすめです。鶏肉と人参を使ったスープはカラダを温めてくれます。
夜間尿対処法:日常生活でできること
夜間尿の改善には、生活習慣の見直しが大切です。まずはできることから始めてみましょう。
・カフェイン・アルコールを控える
カフェイン・アルコールは、利尿作用があるためできるだけ控えてみましょう。コーヒーなどのカフェイン飲料を飲みたいときは、午前中などなるべく早い時間に摂ることをおすすめします。
・寝る前にトイレに行く
寝る前にトイレに行く習慣をつけましょう。トイレに行くことにより、尿意を感じる回数や膀胱にたまる尿量を減らすことができます。
・利尿作用のある食材を避ける
スイカやきゅうり、セロリは、利尿作用がありカラダを冷やします。できるだけカラダを冷やす野菜を食べるのは控えましょう。
・温かい飲み物を摂る
冷たい飲み物や食べ物は、五臓の「腎」の機能を低下させることがあります。温かい飲み物や食べ物を摂るようにしましょう。
・排尿日誌をつける
頻尿や夜間尿に悩んでいる方は、排尿日誌をつけることをおすすめします。排尿時間や水分摂取量を記録することにより、自分の排尿パターンを知ることができます。
・栄養バランスのとれた食事を摂る
主食、主菜、副菜をバランスよく摂取し、栄養バランスのよい食事を心がけましょう。特に、タンパク質、脂質、炭水化物のバランスを意識し、体内の代謝を促す作用のあるビタミンやミネラルを豊富に含む食材を摂取しましょう。
・塩分・糖分の摂りすぎを防ぐ
塩分・糖分の摂りすぎは過除な水分摂取につながり、夜間尿を悪化させることがあります。「減塩・低糖質の調味料を使う」「塩分・糖分の代わりに酸味のある酢やレモン汁、カレー粉などの香辛料を使う」「塩分の多い麺類の汁を残す」「外食や加工食品は塩分・糖分の少ないメニューを選ぶ」など、できることから試してみましょう。
・適度な運動をする
定期的な運動は、全身の血行や代謝をよくし、水分バランスを整えます。負担の少ないウォーキングや軽いジョギングがおすすめです。また、頻尿の原因となる骨盤底筋群を鍛えることもできます。
・ストレスを減らす
カラダに負担がかかるストレスは、ホルモンバランスを崩し、水分代謝に影響を与えることがあります。ストレスを感じたら、ヨガや瞑想・深呼吸などのリラクゼーションを取り入れましょう。
生薬による夜間尿の対処法
・カラダを温める生薬
桂皮(ケイヒ)
血の巡りをよくし、お腹を温める作用があります。関節の痛みや肩こりにも利用します。
生姜(ショウキョウ)
カラダを温め、発汗させる作用があります。お腹の張りや下痢にも利用します。
・腎の機能を改善する生薬
地黄(ジオウ)
カラダに不足した血(栄養)を補う作用があります。生理不順にも利用します。
山薬(サンヤク)
胃腸の働きを整える働きあります。下痢を止め便通を整える働きがあります。
・水分代謝をよくする生薬
猪苓(チョレイ)
カラダの中の余分な水分を尿として外に出す働きがあります。むくみ・膀胱炎などに利用します。
沢瀉(タクシャ)
カラダの中の余分な水分を尿として外に出す働きがあります。むくみ・膀胱炎などに利用します。
カラダの中の水分バランスが乱れると、頻尿や夜間尿を引き起こす場合があります。腎虚による頻尿・夜間尿は、カラダの中の水分を適切に管理できないため、膀胱にたまる尿の量が増加することがあります。この症状の改善に、生薬を活用するのもおすすめです。
頻尿・夜間尿にはこの3つの漢方薬
尿トラブルを改善させるためには、腎の働きを補うことが大切です。今回紹介する漢方薬には頻尿・夜間尿を改善させるために必要な生薬が配合されています。自分の症状や体質に合わせた漢方薬を選びましょう。
■八味地黄丸(はちみじおうがん)
夜中に何度もトイレで目が覚める、頻尿でトイレが近い、などのお悩みがある方におすすめの漢方薬です。生薬はジオウ、サンシュユ、サンヤク、タクシャ、ブクリョウ、ボタンピ、ケイヒ、ブシが配合されています。
■牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)
足腰がだるい、手足が冷たい、などのお悩みがある方におすすめの漢方薬です。生薬はジオウ、サンシュユ、サンヤク、タクシャ、ブクリョウ、ボタンピ、ゴシツ、シャゼンシ、ケイヒ、ブシが配合されています。
■猪苓湯(ちょれいとう)
排尿困難・排尿時の痛み・頻尿などのお悩みがある方におすすめの漢方薬です。生薬はチョレイ・ブクリョウ・タクシャ・アキョウ・カッセキが配合されています。
<PR>
兵庫県在住。医療機関、薬局、IT企業での勤務経験を経て、2015年にライターとして独立。体の不調を感じたことをきっかけに、漢方・薬膳に興味を持つ。中医学スクール「薬膳アカデミア」に入学し「国際中医師(国際中医専門員)」を取得。現在は、ライターとして活動をしながら、漢方薬膳の知識を活かしたコンサルタント業務や、ワークショップ・初心者向け講座などを実施。特に女性の体に関する悩みに寄り添った活動を行っている。
実績:クラシエ薬品株式会社主催「KAMPO OF THE YEAR 2024」にゲストとしてトークショーに登壇
執筆書籍:「カラダのために知っておきたい漢方と薬膳の基礎知識」(淡交社)
資格:国際中医師(国際中医専門員)・医薬品登録販売者・漢方養生指導士・薬機法管理者・食品衛生責任者を取得
X:https://x.com/sora_writer
オフィスかなで:https://officekanade.com/