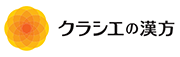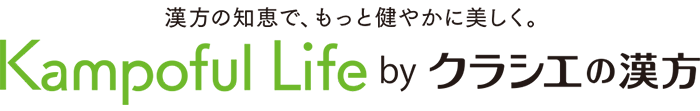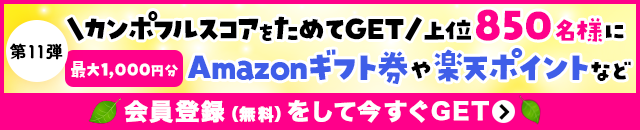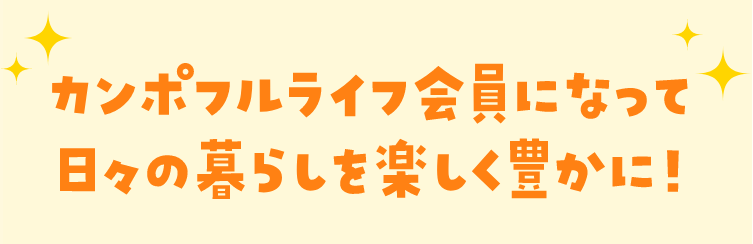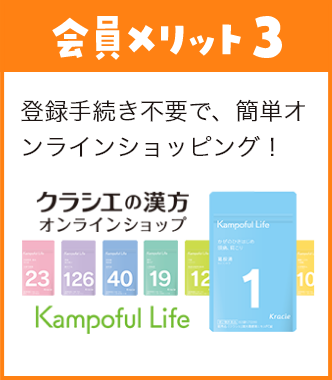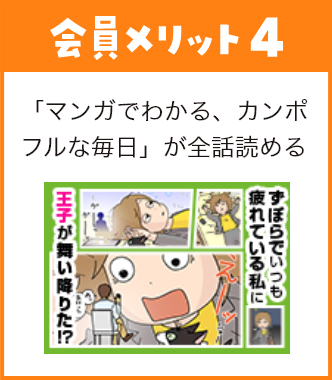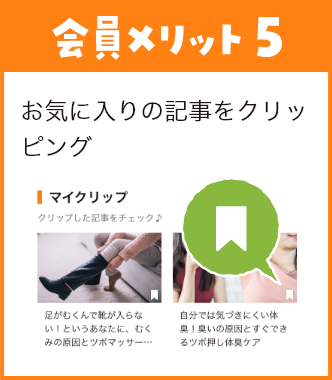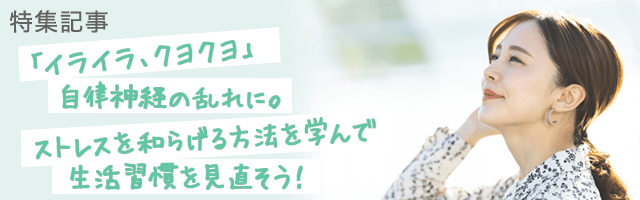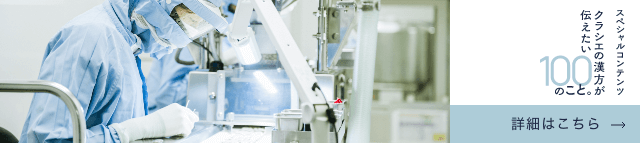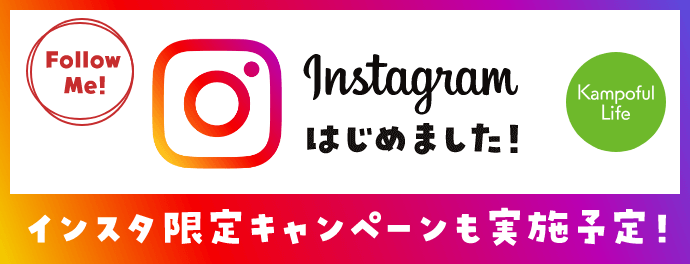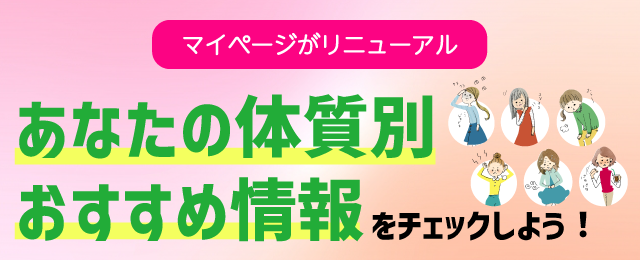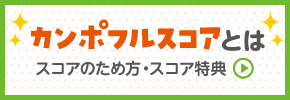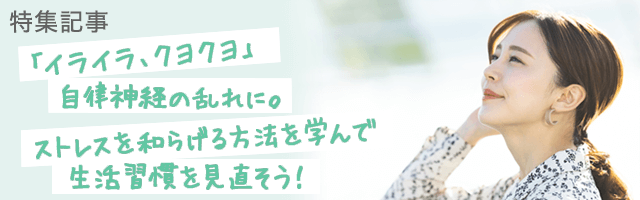目次
- 低体温と低体温症の違いは?冷え性との関係
- 低体温になる原因とは
- 低体温と関係が深い「基礎代謝」の話
- 低体温と「免疫」の関係性
- 体温を下げる3つの敵を知ろう
- 4つの対策でレッツ「温活」!
- 漢方で冷え取りと冷えないカラダづくりを
自分の平熱はご存じですか?コロナ禍の行動として体温を測るという習慣を経験した方が多いかもしれません。その際に体温が37℃を超えるとお店や施設に入れない等ということから体温が低いことでホッとしませんでしたか?理想の平熱は36.5~37.1℃です。36℃以下は「低体温」と呼ばれカラダの機能に悪い影響が及ぶことがあります。「冷えは万病のもと」と言われますが、体温が低いとどのような影響があるのでしょうか?この記事では体温と深く関わりのある基礎代謝や免疫について解説し、効果的な食事や運動法など体温を上げるための「温活」の方法についてご紹介していきます。
低体温と低体温症の違いは?冷え性との関係
「低体温」とは、平熱が正常範囲よりも下がっている状態を指します。人の体温には“皮膚温”と“深部体温”の2種類があり、腋下(脇の下)などカラダの表面から測定する温度が皮膚温、脳や内臓などカラダの内側の温度が深部体温です。平熱は人によって異なるとは言え、腋下で測る皮膚温が36.0℃以下の人は、低体温に分類され深部体温が低い可能性が高いと言われます。
一方「低体温症」とは、体の深部体温が35℃以下に低下した状態を指します。正常時の深部体温は、もっとも温度が高い肝臓で38.5℃、直腸では38℃程度とされています。基本的に直腸用の体温計を用いて深部体温を測定し、直腸の温度が35℃以下になった場合に低体温症と診断されます。深部体温は脳や心臓といった生命維持に関わる臓器の温度を反映しているため、低体温症は命に関わることがあります。低体温症は、カラダから失われる熱が、産生する熱を上回ることが原因で起こります。カラダから熱が失われるのは外的な要因が多く、登山や水難事故、災害時等の寒冷環境などで起こりやすい症状です。
「冷え性」は、平熱や深部体温は低くないのにもかかわらず手足などに部分的な冷えを感じる状態で、カラダ全体の温度が低くなる低体温とは異なります。低体温は深部体温が影響するため免疫力の低下につながり、細菌やウイルスなどの病原体に感染しやすくなります。また、内臓が冷えることから消化不良や体力の低下、食欲不振が起こります。そして、体温調節に関与する自律神経の乱れが生じるため血行不良に陥りやすく、集中力や思考力の低下にまでつながります。
低体温になる原因とは
低体温の原因は、加齢によるもの、食生活の偏り等による栄養状態の悪化、運動不足による筋肉量の減少で基礎代謝が低下し、十分な熱を作り出せなくなることが挙げられます。甲状腺や下垂体、副腎といったホルモン分泌に関わる臓器の機能低下や、脳血管障害、頭部外傷、低血糖などの症状によって低体温になることがあります。思い当たる場合は病院で検査を受けてみることも必要です。外的要因によるものでは、低温環境にカラダがさらされることで体表温度が低くなる低体温もあります。原因が病気ではありませんが、低温環境に長くいることで深部体温が35度以下の低体温症になると体の機能を保てなくなります。例えば、登山や雪山での遭難や水難事故、災害現場など、寒い場所に長時間いる、冷たい水や冷風にさらされることで低体温に陥るケースがあります。
低体温と関係が深い「基礎代謝」の話
人間の24時間あたりの総エネルギー消費量は、基礎代謝量・身体活動量・食事誘発性熱産生の3つに大きく分けられます。基礎代謝量は全体のおよそ60%を占め3つのエネルギー消費量のうち最も大きな割合です。基礎代謝とは生命を維持するために必要とされる最低限のエネルギーのことです。カラダは体温を保つ、心臓を動かす、呼吸をするといった活動をする際、常にエネルギーを使っています。これらの活動は、寝ている時や休んでいる時にも行われます。つまり基礎代謝は生きているだけで使われるエネルギーだといえるでしょう。基礎代謝量は筋肉量が増えるとそれに伴って増加するため筋肉量の少ない小柄な人や女性は基礎代謝量も少なくなります。加齢に伴い筋肉が萎縮したり減少したりするため、年齢と共に基礎代謝量は減っていきます。しかし年齢や性別は変えられなくても、筋力トレーニングによる筋肉の増量や食事内容の見直しをしたり、体温調節に関わる自律神経を整えたりすることで体温を上げる底力を養い基礎代謝を上げることができます。一方、基礎代謝を下げる原因の1つに便秘があります。便秘により腸内環境が悪化すると栄養素をエネルギーとして全身へ送り出す肝臓の働きに影響します。肝臓の働きが鈍くなると、必要な栄養素がカラダに行き渡らず基礎代謝が乱れます。基礎代謝が低下することで糖や脂肪分の分解がうまく行われず、太りやすいカラダになることも考えられます。
低体温と「免疫」の関係性
低体温によって生じるリスクの1つとして考えられるのが免疫力の低下です。 寒さにさらされてカラダの表面が冷えると、カラダはストレスを感じます。ストレスを受けると、ストレスに影響されるさまざまな機能のバランスを維持するために脳からステロイドホルモンや神経伝達物質が分泌されます。これによりリンパ球(白血球の一種)や細胞の働きを低下させるため、一時的に免疫力が下がってしまうのです。免疫力が下がれば、それだけ感染症にかかるリスクが上がります。寒い冬に風邪をひきやすくなるのは、寒さだけが原因ということではなく、それによるストレスによって免疫が下がることが引き金となります。さらに体温が下がるほどカラダの細胞の働きが鈍くなるため、消化・吸収といった内臓機能のみならず、思考力に至るまで、多くの臓器の機能が低下してしまいます。低体温の改善には基礎代謝を上げたり、体温を上げたりする対策が有効です。予防には室温調節や保温も大切なのです。
体温を下げる3つの敵を知ろう
①血行不良(血液の滞り)
血液には、体内の熱を全身に伝える働きがあります。しかし、ストレスや不規則な生活によって自律神経のバランスが乱れると、血管が収縮して血行が悪くなります。そのため血液がカラダのすみずみまで行き渡らずカラダが冷えてしまいます。血流が滞ることで冷えだけでなく肩こり、腰痛、むくみなどの症状を引き起こします。また血行不良は内臓の働きを低下させるため、消化不良や便秘の原因にもなります。
②自律神経(ストレスによる交感神経優位な状況)
自律神経は意思でコントロールすることができませんが、カラダの外からの刺激や内部からの情報によって循環・消化・代謝・体温調整といった生命を維持するために不可欠な機能を自動的に調整してくれる神経です。リラックスしているときに活発に働く副交感神経と、緊張しているときなどに活発になる交感神経の2つのバランスが取れていると、病気になりにくいとされています。一方ストレスがかかることによって、交感神経が優位になると血流が乱れカラダが冷えてしまいます。
③むくみ(カラダに溜まった余計な水分)
むくみは血管の外に溜まった余計な水分です。この溜まった水分がカラダを冷やし、さらに血管を圧迫するため血行不良になるといった悪循環が起きます。運動不足、ストレス、不規則な食習慣により血流が悪くなると溜まった水を運ぶことが出来ないためむくみを引き起こしやすくなります。
★番外編:食事の仕方
食事をする際、食べ物をカラダに取り込む時の消化熱や吸収熱で体温が上がりますが、食べ物をよく噛まないと消化器に負担がかかり、胃腸に熱が集中してしまいます。そのためカラダ全体に熱が行き渡らなくなり低体温につながる習慣となりえます。食べ過ぎも同じ理由で低体温の原因になると言われています。
4つの対策でレッツ「温活」!
体温を上げる温活方法として運動習慣やカラダを温める入浴や食事、冷やさない予防行動が大切です。
①運動習慣で体温を上げる。
<朝におすすめ>・ウォーキング
運動習慣がない方や体力に自信がない方でも気軽に始めやすいのがウォーキングです。ウォーキングは日常生活の中で無理なく簡単に始められるため取り入れやすい運動の1つです。体温の一番低い朝にウォーキングを行うと、効率良く体温上昇が期待できるため、一度上がった体温を日中もしっかりと維持できます。通勤・通学時間を有効に使う意識を持つと効率的に習慣付けができます。
<日中におすすめ>・座ったままのジャンプ運動
自宅又は職場の椅子に座ったままジャンプする運動で、手軽に体幹と股関節の大きな筋肉である腸腰筋を鍛えることができます。椅子に座った状態で両足をジャンプするように弾ませましょう。デスクワークで滞りがちな足のむくみ改善にも効果が期待できます。
<やり方> 10回程度を1日数セット
1.おへそが水平方向に向くように骨盤を立てて背筋を伸ばして座ります。(両膝を付けておくと内ももの筋肉も同時に鍛えられます)
2.手は胸の前で組んでおくと効果的ですが、ぐらつく場合は椅子の座面や近くのテーブルなどにのせておきましょう。
3.息を吐きながら両足を同時に上に持ち上げ、できるだけ音を立てないようにゆっくり着地させます。
※カラダが前後に動きすぎないように腹筋と背筋を使いましょう。
※痛みがでない程度に、足は少し浮くだけでも効果はあります。

<夜におすすめ>・ストレッチ
ストレッチは筋肉や関節を伸ばす運動になるため、血流促進効果が期待できます。夜のゆったりとしたストレッチは一日の溜まった疲れを取り払い、リラックス状態へと導く自律神経のうちの副交感神経を整えるために効果的です。呼吸を止めずに心地よいレベルでゆっくりとした動作で行いましょう。寝る前の習慣にすることで睡眠の質向上にも有効です。
②入浴法で温まる。
・体を温める基本の入浴法
38~40℃程度のぬるめのお湯に10分~30分程度浸かりましょう(無理をせず季節や体調によって調節しましょう)。ゆったり入浴することで副交感神経が優位になり、リラックス効果も深まります。冷え取りには薬用入浴剤(医薬部外品)をプラスすることで温浴効果が高まりカラダが温まります。エプソムソルトというミネラル化合物の一種でマグネシウムをたっぷり含む成分が入っているものを選ぶと効果的です。さらに温まりたい人は、入浴前に軽い筋トレをして、入浴後にストレッチを行うと良いでしょう。
※薬用入浴剤で温浴効果を得たい場合は、医薬部外品を選びましょう。
・むくみをとる理想的な入浴方法
とにかくカラダを伸び伸びとさせること。鼠径部(そけいぶ)を圧迫しない程度に適度に足をあげて血行を良くすることも大事です。入浴後は広がった血管を収縮させるためシャワーで冷水をかけると血行がよくなります。充分に温まった後の冷水がポイントです。
・ダイエットにも効果的な分割浴
熱い湯(40~42℃)を張った浴槽に3~5分おきに肩まで浸かったり、出たりを繰り返す入浴法で反復浴とも呼ばれています。心拍数を急に上昇させることなく血流量を増やすので、肩こりや冷え性の改善が期待できます。休憩と入浴を繰り返すことによって交感神経を刺激するため代謝がよくなり脂肪燃焼が促進されると考えられています。交感神経が優位になるため入眠前はおすすめではありません。
③温める食生活と取り入れる。
温活では、冷たい飲み物やカラダを冷やす食べ物は避けるようにしましょう。過度に避ける必要はありませんが、バランスよく食事や日常生活に取り入れることをおすすめします。
| 体を温めるもの | 体を冷やすもの | |
| 野菜 | 玉ねぎ、人参、等の根菜類、 冬野菜、加熱した生姜 |
レタス、トマト、ナス、 きゅうり等の水分の多い夏野菜 |
| フルーツ | りんご、桃等 寒い地方で採れるフルーツ |
バナナ、スイカ等の南国フルーツ |
| 飲み物 | 白湯、生姜湯、紅茶、ほうじ茶等 温かい飲み物 |
コーヒー、牛乳、緑茶等 冷たい飲み物 |
発酵食品で腸を温めよう!
腸が冷えると、消化機能が落ちて腸内環境が乱れ、便秘や免疫機能の低下、肌荒れなどの不調を引き起こします。腸内を温めるには発酵食品がおススメ。発酵食品に含まれる善玉菌は腸内環境を整え、カラダを温める作用があります。
低体温改善におすすめの飲み物レシピをご紹介!
★にんじんりんごジュース
<材料>にんじん 2本、りんご 1個
<作り方>
①にんじんとりんごの皮をむき、ミキサーに入れやすい大きさに切ります。
②切った材料をミキサーにかけ、器に移し替えたら完成。
※食前など空腹時に飲むと栄養素の吸収率が上がります。
★辛さ際立つ生姜紅茶
<材料>生姜 1かけ、紅茶の茶葉またはティーバッグ
<作り方>
①生姜をスライスして電子レンジで7~8分程度加熱しカラカラに乾かし刻んでおきます。
②ホットで淹れた紅茶に加熱して刻んだ生姜を加えてよく混ぜます。
※生姜を加熱すると辛味がアップしますので、量は好みに応じて調節してください。
※甘味が欲しい場合は黒糖やはちみつを加えてもOK。
※妊娠中や妊活中の方は、カフェインの取り過ぎには注意しましょう。
④ 冷やさない生活を知り、実践する。
・カラダの温めポイントを知る
冷やさないための温活行動は、効率的にカラダの温めポイントを知ることが大事です。首、手首、足首という「首」と名の付く3点を冷やさないことが重要です。さらに、臓器が集まるお腹や筋肉が多く集まっている腰から太もも周辺を温めることで、効率よく体を温めることができます。マフラー、アームウォーマー、レッグウォーマー、腹巻、膝掛けなどを活用し、日常生活の中でカラダから熱を逃がさないようにしましょう。できることから始めて、寒さ由来の冷えから脱出しましょう。
・温めのツボを知る
【三陰交(さんいんこう)】
東洋医学では冷えの原因を消化器の不調、水分代謝の低下、生理機能の低下と考えます。三陰交はその3つの経路(けいらく)を同時に刺激するため冷え性に効果的と言われています。
<場所>足首の内側で内くるぶしの骨から指の幅4本分上に位置
<やり方>回数:両脚各3回程度
①ツボの場所に手の親指をあて、ゆっくりと息を吐きながら痛気持ち良い力加減で指圧します。
②息を吸いながら力を緩めて、次の吐く息で同じ場所を指圧します。
③反対の脚も同様に行います。

※三陰交は陣痛を促進するツボとしても働くため妊娠中の方は避けましょう。
漢方で冷え取りと冷えないカラダづくりを
体温の産生・維持を支えているのが、全身の筋肉や消化器官の働きです。筋肉は人体最大の発熱器官として、脂肪とともに体温維持に貢献しており、消化器官も飲食物の消化・吸収を通じて体温の産生を担います。漢方では筋は肝(肝臓)が養う、肉は脾(消化器官)が養うと考えられています。低体温や基礎代謝を改善するには、カラダを温めることに加えて、人体最大の代謝器官である肝臓や消化器官を整えるために、血行促進(栄養を巡らす)、水分代謝、自律神経を整える効果のある漢方を取り入れることもオススメです。
■当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)
全身に大切な栄養素を与え、血行を良くするのと同時に、水分代謝を整えることで余分な水分をカラダから取り除き、足腰の冷え症や生理不順を改善する漢方薬です。
■大柴胡湯(だいさいことう)
ストレスによる自律神経系の乱れを整え、蓄積した脂肪の分解・燃焼を促すことで肥満や肥満に伴う便秘を改善する漢方薬です。
■十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)
虚弱体質、疲労や産後・病後などで体力を消耗している時、消化器や循環器の機能低下による貧血、手足の冷えの改善などに効果を発揮する漢方薬です。

那須久美子
広告会社、大手化粧品会社宣伝部にてCM、雑誌等の広告制作に携わる。
その後フリーランスとしてバレエ講師、ピラティスマスターストレーナー、ヨガセラピスト、介護予防運動指導員として老若男女への伝える仕事に従事。
企業や官公庁での健康アドバイザーや研修講師も務める。
国家資格キャリアコンサルタントとしては企業内障害者ジョブコーチを経て自治体事業の就労支援プログラム講師とカウンセラーを兼任。
現在は就労支援事業の現場統括責任者を務める傍らキャリアコンサルタントのスクールにおいてオウンドメディアの監修も担当。
・ヘルスケアデザイナー
・バレエティーチャー
・ピラティストレーナー、ヨガセラピスト
・アスリートキャリアコーディネーター
・国家資格キャリアコンサルタント
・漢方アドバイザー
・介護予防運動指導員
HP:https://www.kandworks.com/about