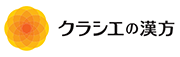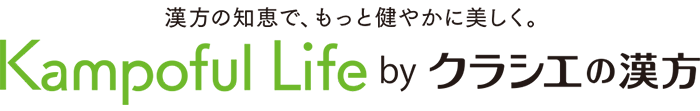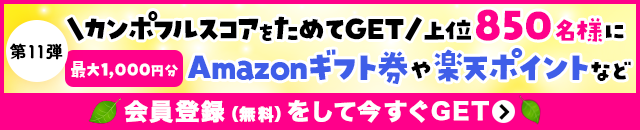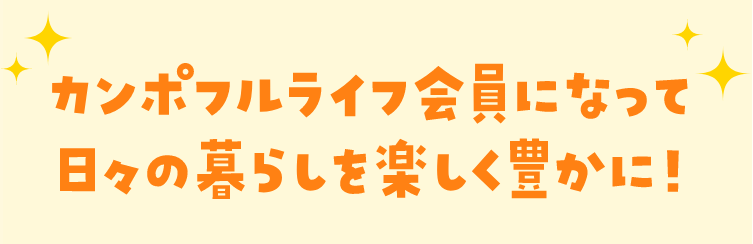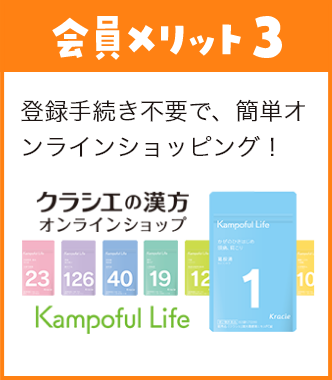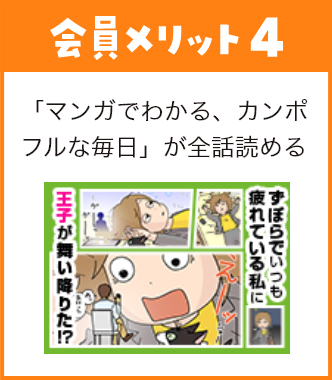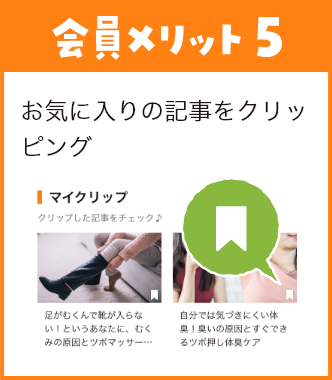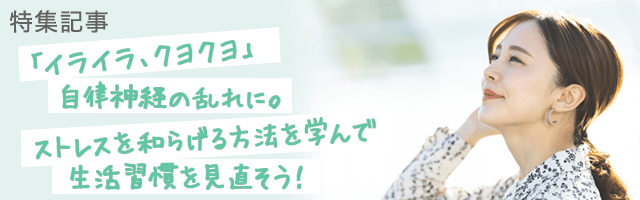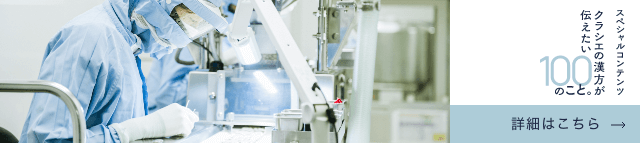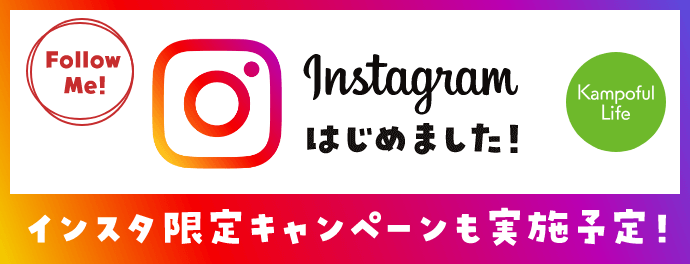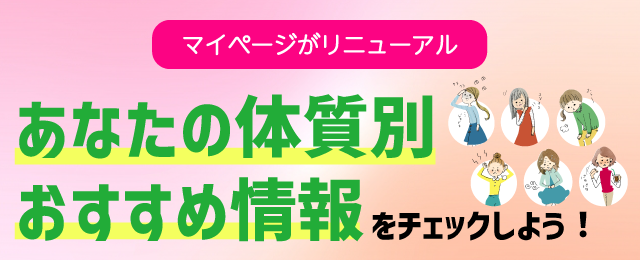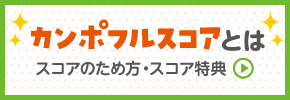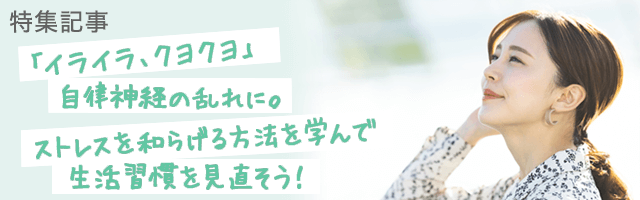目次
- 足のつり(こむら返り)に即効性がある漢方「芍薬甘草湯」
- 漢方で考える、足がつる原因
- 足がつりやすい状態とは?対策も併せて紹介
- 足がつる人に必要な栄養素とは?摂取方法と注意点
- 足のつり(こむら返り)の正しい対処法と痛みを和らげる方法
- 【簡単予防4選】「今日は足がつりそう」だと感じたら・・・
- 足のつりが病気のサイン?可能性とリスクをチェック
「イタタタ・・・!」と夜中に突然足がつると、驚いて目が覚めますよね。焦ってもどうすることもできず、"不安"と"つったふくらはぎ"を抱えながら、こむら返りの症状が治まるのをひたすらじっと待つ。「痛いし、寒いし・・・」真冬の明け方に、こんな風に目が覚めるのは、できれば避けたいものです。
足のつり(こむら返り)に即効性がある漢方薬「芍薬甘草湯」
漢方薬には即効性がないというイメージをお持ちの方も多いかと思いますが、「芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)」は「急激に起こる足のつり(こむら返り)」に即効性がある漢方薬です。
・寝ていて突然ふくらはぎがつる
・久々の運動中、いきなり足がつる
・筋肉がけいれんして、急にふくらはぎに痛みが出た
「芍薬甘草湯」は、こんな時に服用されることが多い漢方薬です。
「芍薬甘草湯」に配合される生薬の 芍薬と甘草の組み合わせが筋肉のけいれんを抑制してくれます。できれば、足がつった時にすぐ服用できるのがベストですが、難しい時はつってしまった後に服用しても効果が期待できます。また、「前兆」があることが多い症状ですので、「前兆」を感じたら早めに服用してください。
漢方解説 – 芍薬甘草湯|漢方セラピー
急な足のつり、こむらがえりにおすすめの漢方薬「芍薬甘草湯」がどのように効くのか解説します。
漢方で考える、足がつる原因
足がつる時ってどんな時でしょう?「寒い冬の朝に足がつりやすい」という方も多いのではないでしょうか?この季節につりやすい原因は「冷え」が大きく関係しています。漢方では「冷えは万病の元」と捉えていますが、「冷え」は、 足のつりも引き起こしやすくします。
”第二の心臓”とも呼ばれるふくらはぎの血行不良
ふくらはぎは全身の血行を巡らせる大切な役割を持っています。冷えて、このふくらはぎの筋肉が凝り固まってしまうと、血流が滞り血行不良を引き起こしやすくなります。血行不良は足がつる要因の一つでもあります。
真冬の朝方は気温がとっても低いので、自分でも気づかないうちに猫のようにぎゅっと縮こまって寝ていることもありますよね。すると筋肉は緊張状態となり筋肉の収縮に必要な栄養素が十分に届きにくくなります。急に足を伸ばすと「!」となってしまうのです。
水分代謝とミネラルのアンバランス
漢方では、人のカラダは「気(き)」「血(けつ)」「水(すい)」の3つで構成されていると考えています。そのうち、「水(=血液以外の水分や体液を指すもので、飲食物中の水分を消化吸収によってカラダに必要な形にし、カラダをうるおしているもの)」に含まれるミネラルは筋肉が働くための重要な役割をしています。ミネラルバランスが乱れると足の筋肉が硬直しやすくなると考えられています。また、「水」が不足していると「血」を巡らせることもできません。この「水」と「血」のバランスが乱れた状態が、足をつりやすくさせます。 冷えると水分代謝が悪くなりむくみやすい、というのはイメージしやすいですよね。実は「水」が少なくても足がつりやすくなってしまうのです。
足がつりやすい状態とは?対策も併せて紹介
足がつるという症状は、こむら返りとも呼ばれ、筋肉が急激に収縮して痛みを感じる状態です。では、どのようなときに足がつるのでしょうか。
水分不足:体内の水分やミネラルのバランスが崩れると、筋肉の収縮や弛緩がうまくいかなくなります。漢方でいう「水」と「血」のバランスが乱れた状態です。暑い季節や運動中に汗をかく場合は、熱中症対策も意識して水分補給を怠らないようにしていきましょう。 具体的には、一日に2リットル以上の水分を摂るように心がけます。スポーツドリンクなどでミネラルの補給を意識することも大切です。
冷え:体が冷えると、血流が悪くなり、筋肉に十分な栄養や酸素が届かなくなります。漢方で言えば、「血」の巡りが悪い状態です。 特に、寝ている時に足先が冷える状態では、足がつるリスクが高くなります。このような場合は、 寝る前に足湯をしてみたり、湯たんぽや電気毛布などで足先を温めてあげましょう。また、急激な寒暖差に注意して冷房や扇風機の風に当たらないようにしましょう。
筋肉疲労:長時間の立ち仕事をしている人や過度な運動が原因で、筋肉に負担がかかると、乳酸などの老廃物がたまりやすくなります。乳酸などの老廃物が筋肉の収縮を妨げて、足のつりを引き起こすことがあります。立ち仕事の合間や、運動前後、就寝前に軽くストレッチを行い、ふくらはぎや太ももの筋肉を伸ばすと、足のつりを予防する効果があります。
栄養不足:カルシウムやマグネシウムなどのミネラルは、筋肉の働きに欠かせない栄養素です。これらが不足すると、神経から筋肉の伸縮を命令する信号が乱れて制御がうまくできなくなります。 そのため足の筋肉は硬直しやすくなり、痙攣して足のつりを起こしやすくなります。栄養素については、次の章で解説していきます。
足がつる人に必要な栄養素とは?摂取方法と注意点
足のつりを予防するために必要な栄養素はミネラルです。 ただし、栄養素はバランスよく摂取することが大切です。詳細に解説していきましょう。
足(ふくらはぎ)がつる原因は、筋肉の収縮が正常に行われないことです。筋肉の収縮に必要な栄養素は、ミネラルです。なぜでしょうか。ミネラルは、血液中に溶けて電解質として働きます。電解質とは、神経から筋肉への信号伝達や筋肉の収縮力を調節する役割を持ちます。しかし、疲労などで血液中の電解質のバランスが崩れると、筋肉が過敏に反応して血行不良が生じて、こむら返りが起こりやすくなります。
では、どんなミネラルを摂取すれば良いのでしょうか?足がつりやすい人は、カルシウムやマグネシウムを十分に摂取しましょう。カルシウムは、乳製品や小魚、海藻類などに多く含まれています。マグネシウムは、ナッツ類や大豆製品、ほうれん草などの緑黄色野菜などに多く含まれています。つまり、意識的にこれらの食品をバランスよく食事に取り入れると、血液中の電解質のバランスが整えられていきます。
ただし、他の栄養素も足がつる原因に関係します。例えば、ビタミンDはカルシウムの吸収を助ける働きがある栄養素です。ビタミンDは、皮膚が日光に当たることで生成されますし、魚介類や卵黄などに含まれるので食事での摂取も可能です。また、ビタミンB群は神経系の機能をサポートする働きがあります。ビタミンB群は、肉類や穀物類などに含まれています。
このように、不足しているミネラルを摂取することで、足がつる症状(こむら返り)を予防することができます。ですが、摂りすぎには注意しましょう。過剰な摂取が、逆に電解質のバランスを乱したり、腎臓に負担をかけたりする可能性があります。また、食事だけではなく、水分補給や適度な運動も忘れずに行いましょう。
また、漢方では、鶏肉・牛肉・魚・大豆製品・酢など、漢方では赤い食材は血を増やし、血流を良くして体を温めるとされています。また、クコの実・なつめ・赤身のお肉なども積極的に摂るようにすることもおすすめします。
足のつり(こむら返り)の正しい対処法と痛みを和らげる方法
足がつったときは、慌てず、落ち着いて正しい対処法を取りましょう。一気に無理に動かそうとすると、筋肉を傷めたり、肉離れやアキレス腱断裂などの重篤な状態になる可能性があります。
足がつった場合の対処法を部位別に紹介していきます。
ふくらはぎがつる:足の指を自分の方に引っ張って、ふくらはぎの筋肉を伸ばしましょう。また、壁に足をつけて体重をかける方法も効果的です。
太ももの裏がつる:座った状態で足を伸ばして、手で足首を持ち上げます。また、立った状態で患部の足を後ろに引いて、手で足首を持つのも効果的です。
その他の部位がつる:基本的に、つった部位の筋肉を反対方向に伸ばすことで痛みを和らげることができます。ただし、無理に力を入れないように注意してください。
これら、応急処置を行った後は、患部を温めて血行を良くします。マッサージやストレッチも効果的です。さらに、水分やミネラルの補給も忘れずに行いましょう。
<PR>

- 急な足のつり、こむらがえりにお悩みのあなたへ
芍薬甘草湯-漢方セラピー
- 詳しく見る
【簡単予防4選】「今日は足がつりそう」だと感じたら・・・
激しく運動した日や、特にカラダが冷えた日などは足のつりの症状(こむら返り)が起きやすい日と言えます。そんな「今日は足がつりそう」な予感がする日、カンタンにできる予防策を紹介します。
【今日は足がつりそうな日1】
寒い時に運動でカラダを温めるのはとても良いことなのですが、たくさん汗をかいたり、筋肉を使った日は注意が必要な日です。汗と共に筋肉の動きを調整するミネラルが排出され、筋肉疲労が起こりやすくなります。すると老廃物が溜まり、筋肉への血流も不足しがちです。そのままの状態で夜、寝てしまうと筋肉がゆるまず夜中に足がつりやすくなってしまいます。ですが、「運動した日は足がつるんじゃないか」と不安になって運動不足になってしまっては本末転倒。運動をしないと筋肉が衰え、血流が滞り、余計に足がつりやすくなってしまいます。
【今日は足がつりそうな日2】
特にカラダが冷えた日も要注意です。真冬は特に底冷えし、足元から冷えが襲ってきます。しっかり防寒していても一日中外に居てはカラダの芯から冷え切ってしまいます。筋肉がカチカチに硬直してしまっているので、必ずお風呂に入ってカラダを温め筋肉を緩めてから休みましょう。
予防策1:足湯
足裏にはたくさんのツボがあります。ツボは温めることでも刺激になるので、足元だけの足湯でもカラダ全体がポカポカしてくることでしょう。
予防策2:ストレッチ
足首を向う側へ倒したり手前に曲げたりと数回ゆっくり繰り返します。寝ながらできるので寝る前におすすめです。
予防策3:締め付けないレッグウォーマー
冷え対策として靴下を履く方もいますが、締め付けの強いものだとかえって血行を悪くしてしまうことも。ふんわりと包み込んでくれるレッグウォーマーで足首を冷えから守ります。
予防策4:就寝前の一杯の常温のスポーツドリンク
人は睡眠中も発汗します。お休み前にスポーツドリンクなどを飲んで水分と栄養分を補給しましょう。ただし、この時期の水分補給の仕方にも気をつけてください。水分は必要ですが、飲みすぎると逆にカラダを冷やしむくみや足のつりにつながります。できるだけ常温か温かいものを一口ずつゆっくり飲むようにしましょう。
とにかく温めて、水分と栄養分を補給することが大事なのです。
足のつりが病気のサイン?可能性とリスクをチェック
足のつりが、重大な病気のサインであることもあります。例えば、以下のような病気が考えられます。
糖尿病:高い血糖値が、神経や血管に障害を与え、感覚や血行を悪化させます。これにより、足底筋膜(そくていきんまく)に問題が起こりやすくなります。また、尿中に多くの水分やミネラルが排出されることで、電解質のバランスが崩れる影響で、足の裏がつりやすくなります。糖尿病は、放置すると合併症を引き起こして、失明や腎不全などの重篤な状態になる可能性があります。尚、糖尿病では喉の渇きや頻尿、体重減少や倦怠感などの兆候が現れることもあります。
末梢動脈硬化症:動脈硬化は、血管の内壁にコレステロールやカルシウムなどが付着し、血管が細くなったり詰まったりすることです。末梢動脈硬化症は、特に足の血管に起こりやすい動脈硬化です。足の血管が詰まると、筋肉に十分な酸素や栄養が届かなくなる結果、足がつりやすくなります。歩くと足がしびれたり冷たくなったりする間欠跛行(かんけつはこう)や、靴下を履いても消えない赤い斑点(紫斑)などの兆候が現れることもあります。末梢動脈硬化症は、放置すると壊死や感染を引き起こして、切断が必要になる場合もあります。
下肢静脈瘤(かしじょうみゃくりゅう):下肢静脈瘤とは、足の静脈に血液が溜まって拡張したり曲がったりすることで、重力や立ち仕事などで足にかかる圧力が原因で起こりやすくなります。下肢静脈瘤は、見た目だけでなく、足のむくみや重だるさ、足のつりなどの不快な症状を引き起こします。足に青いぶつぶつやねじれた筋が見えたり、足が熱くなったりするなどの兆候が現れることがあります。放置すると血栓や潰瘍を引き起こして、深部静脈血栓症や肺塞栓症などの命に関わるケースもあります。
もし、これらの症状も感じる場合は、早めに医師に相談しましょう。早期の診断や治療で、病気の進行や合併症を防ぐことができる可能性が高まります。
また漢方や東洋医学の知恵を活用することも効果的です。
カンポフルライフでは、カラダを冷やさないための生活アドバイスをたくさんご紹介しています。カラダを温める食べ物・飲み物から、すぐ実践できる末端の冷えに効く「ツボ」やお手軽なカイロ活用法など。カンポフルライフの記事一覧から気になる記事を探してみませんか?
<PR>

- 急な足のつり、こむらがえりにお悩みのあなたへ
芍薬甘草湯-漢方セラピー
- 詳しく見る
監修
樫出 恒代