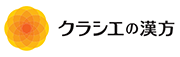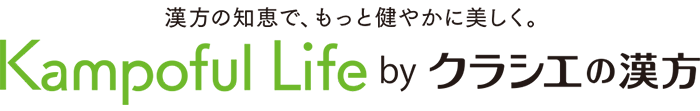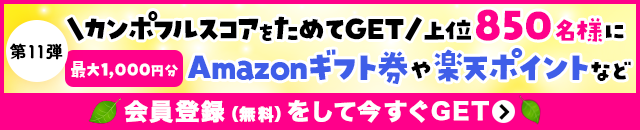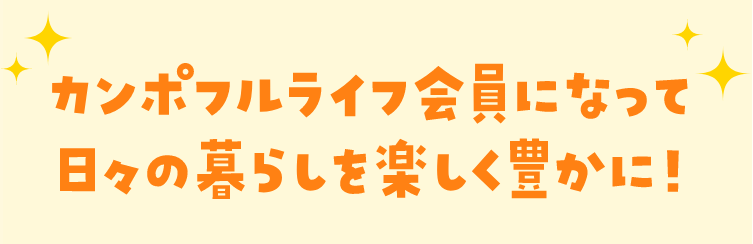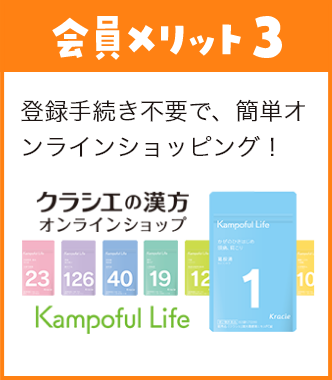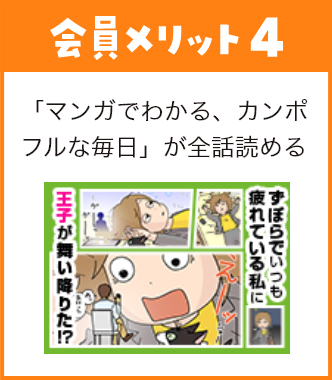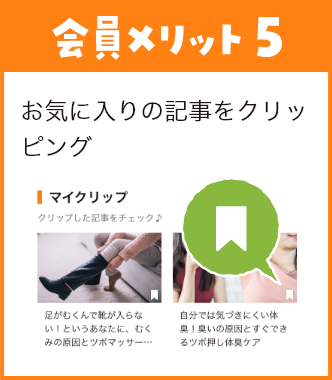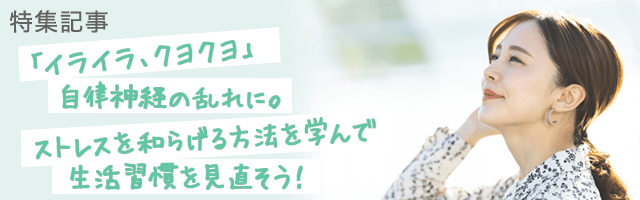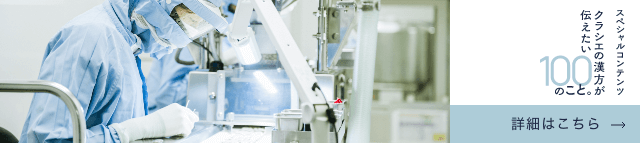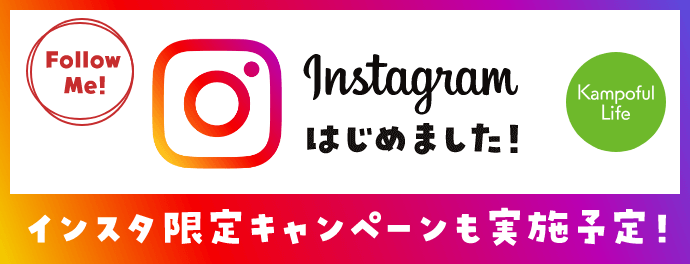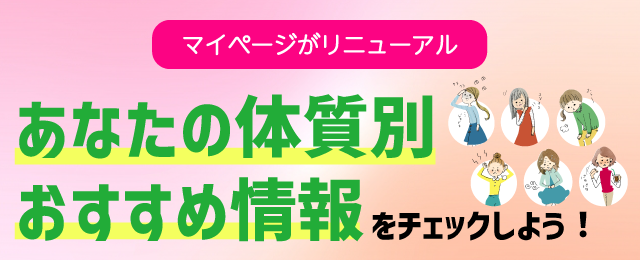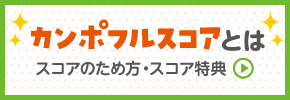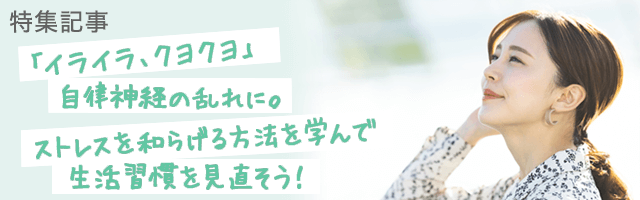目次
- まずは、漢方診断で体質チェック
- 「陰虚」体質のあなたはどんな状態?
- 陰虚体質の症状とは?
- 陰虚タイプにおすすめの漢方
- おすすめ3つの生活習慣
- カラダを潤わせる食材は?
- 陰虚を補うには「水(津液)」がポイント」
- ストレスで感じる喉の違和感を治す方法は?
- 陰虚が原因でほてりや熱感が生じる理由は?
- 陰虚を引き起こす原因とは?
- 老廃物の排出を改善するには?
漢方の考えでは、カラダは「気(き)」・「血(けつ)」・「水(すい)」の3つの構成要素で支えられていると考えます。この3つの構成要素のバランスが悪いと私たちのカラダには、さまざまなトラブルが出やすくなると考えられています。漢方ではこの3つの構成要素のバランスを元に、体質を気虚(ききょ)・気滞(きたい)・血虚(けっきょ)・瘀血(おけつ)・陰虚(いんきょ)・水滞(すいたい)の6つのタイプに分けて、体質ごとにトラブルの原因をさぐります。
今回はその中の『陰虚』体質について解説します。 症状の紹介と、おすすめの漢方薬、生活習慣に関するアドバイスとおすすめの食べ物なども紹介していきます。体質を改善して、元気なあなたを目指していきましょう。
まずは、漢方診断で体質チェック
まずは、あなたの体質が60秒で分かる体質診断コンテンツ「クラシエの漢方診断」からスタートしましょう。
診断は漢方理論に則り、体質を6つに分類します。あなたの体質は何でしたか?
<PR>
診断結果が『陰虚』だった方は、このまま読み進めてください。
その他の体質の方は、以下のリンクから該当体質の解説をご覧ください。
「陰虚」体質のあなたはどんな状態?
陰虚(津虚)体質はカラダの潤いである「水(すい)」が少なくなり不足している状態です。漢方では「水」とは体液だけでなく、汗や唾液、胃液、腸液、尿のような分泌液や排泄液など、血液以外の カラダのすべての水分の総称です。水はカラダを潤す役割を担っています。臓腑や筋肉、皮膚、髪の毛、粘膜などを潤し正常に保ったり、関節を潤し円滑に動かす手助けをしたり、ときには尿や汗、鼻水となってカラダに溜まった老廃物を体外へ排出するなど幅広く活躍しています。水が不足し陰虚の状態になると、カラダが乾燥し、あらゆるところで乾燥によるトラブルが起こりやすくなります。
陰虚体質の症状とは?
カラダがむくむ
水滞になり余分な水がカラダに停滞すると、全身がむくみやすくなると漢方では考えます。特に、ふくらはぎや足首など下半身はむくみやすい部位で、ひどいときにはだるさや痛みを伴うこともあります。関節も余分な水がたまってむくみやすい部位で、指が曲げにくい、こぶしが握りにくい、腕が上がりにくい、動かしにくいなどのトラブルが出やすいと言われています。
のどが渇いて水分を欲する
陰虚になり水分が不足すると、それを補おうとカラダが水分を欲します。そのため、のどがとても渇きやすくなると漢方では考えています。しかし一時的に水分をとってもすぐに体質が改善するわけではないため、再びのどが渇くなど、なかなか渇きが治まらないのも陰虚の特徴です。
口の粘膜や、鼻の粘膜が乾燥する
陰虚体質になると、口の粘膜も乾燥しやすくなります。そのため、口が乾燥する(ドライマウス)、口がネバネバする、口が臭うなどのトラブルが起こりやすくなると漢方では考えます。また唇も乾燥しやすく、唇がカサカサする、唇が割れやすくなるなどの症状も出やすくなると言われます。口の粘膜と同様に、鼻の粘膜も乾燥しやすくなります。鼻の中が乾燥して荒れやすくなり、ひどいときには出血しやすくなると言われます。
のどがイガイガする、咳がでやすくなる
陰虚体質になると、のどや気管支の粘膜も乾燥し、潤いを失っていきます。漢方では“粘膜は潤いを好み、乾燥を嫌う”と言われ、乾燥するとのどがイガイガする、かゆくなる、せきが出る、呼吸がしにくくなるなどのトラブルが出やすくなると考えます。せきは空咳のように乾燥した咳で、痰は無いか出ても少なく、ときに粘性があって出しにくいのが特徴です。
皮膚が乾燥してカサカサになる
皮膚も粘膜同様に潤いを好み、乾燥を嫌うと漢方では考えます。そのため陰虚になると乾燥により皮膚のコンディションが悪くなり、カサカサする、艶がなくなる、キメが荒くなる、粉がふく、かゆみが出る、皮膚が弱くなるなどのトラブルが起こりやすくなると漢方では考えます。
便が硬くなる、尿が少なくなる
陰虚になると大腸粘膜の潤いも不足し乾燥しやすくなると漢方では考えます。そのため、便が乾燥して硬くなり、排便困難、排便痛、さらにはコロコロした兎糞便や便秘にも繋がりやすくなると言われています。 便だけでなく、尿にも影響が出ます。陰虚になると体内の水分が少ないため、尿として排出され水分が減少し、尿量も少なくなると漢方では考えます。
陰虚タイプにおすすめの漢方
知柏地黄丸(ちばくじおうがん)
知柏地黄丸は「腎(じん)」のはたらきが低下した状態を改善する補腎薬(ほじんやく)を配合した処方です。特に、陰虚体質(ほてり、のぼせ、口渇)の方におすすめです。排尿困難、頻尿にも効果がある生薬製剤です。
<PR>
麦門冬湯(ばくもんどうとう)
麦門冬湯は、粘膜や気道を潤し、からだに栄養を届ける機能を高める働きがあり、からせきや、痰が切れにくく、のどにからんだりするときの咳や気管支炎に効果的な漢方薬です。
<PR>
おすすめ3つの生活習慣
汗のかきすぎに注意して、こまめな水分補給を
こまめに水分を補給して、カラダに潤いをプラスしてあげましょう。また、汗をかき過ぎるとカラダの水分が少なくなり、陰虚を助長します。運動の際は特に、こまめな水分補給を忘れずに。カラダの乾燥にも注意しましょう。
カラダの乾燥を助長するに注意しましょう
漢方では、辛いたべものは発汗を促し、カラダを乾燥させやすくすると考えます。生姜、胡椒、山椒、唐辛子などの香辛料の摂りすぎには注意するようにしましょう。
酸味×甘味でカラダの潤いをサポート
漢方では“酸味“と“甘味”の組み合わせはカラダの潤いを補うと考えます。酢の物や甘酢あんのように、日々の食事で酸味×甘味の組み合わせを意識してみましょう。
舌の苔をチェックしてカラダの水分量を把握しましょう
漢方では舌の苔の量はカラダの水分状態を反映すると考えています。舌の色が透けて見える程度の薄い苔がかかっている状態が健康だと言われていて、カラダに余分な水分がたまり始めると苔が徐々に分厚くなると考えます。毎日朝起きたら舌の苔をチェックして、常にカラダの水分状態を把握する習慣をつけましょう。
カラダを潤わせる食材は?
ネバネバ食材
漢方では、山芋やオクラのようなネバネバした食べものはカラダの潤いを補うと考えます。山芋はできるだけ加熱せず、生に近い状態で食べるのがおすすめです。なぜなら、山芋は加熱してホクホクした状態になると、カラダの潤いを補う作用から、気を補う働きを助ける作用にと変化してしまうと言われているからです。陰虚では、みずみずしい状態でいただくというのがポイントです。
白色の食材
白色の食材は「肺系(鼻・のど・気管支などの呼吸器系、皮膚、粘膜、大腸など)」の働きを助けると漢方では考えます。その中でも、山芋や蓮根、白きくらげ、ゆり根、梨などは、カラダに潤いを補う働きを助けると言われていて、特におすすめです。
ナッツ類
漢方では、アーモンド、松の実、落花生などのナッツ類はカラダを潤し、陰虚の乾燥によるトラブルをサポートすると考えています。特に、腸の乾燥による便秘におすすめで、油が潤滑油のような役割をして排便がスムーズになると言われます。
≪水を補う働きを助ける食べもの≫
・潤肺
やまいも はちみつ アーモンド 銀杏 さんざし 甜杏仁 松の実 落花生、クレソン くわい 白きくらげ ゆり根 蓮根、杏 いちじく オレンジ 柿 かぼす すだち たちばな バナナ パパイヤ びわ 干し柿 みかん りんご、白魚
・生津
豆乳 豆腐 オリーブ なつめ、アスパラガス オクラ キュウリ 黒くわい 白きくらげ ズッキーニ 冬瓜、トマト はやとうり 蓮根、杏 いちじく 梅 カリン ココナッツ シークワーサー スターフルーツ、すもも 梨 びわ マンゴー みかん メロン 桃 ヤマモモ ライチ りんご レモン、合鴨 牛乳 ヨーグルト
・補陰・滋陰
やまいも 黒豆 エリンギ オクラ かぶら きくらげ じゅんさい 人参 ほれんそう、桑の実 梨
陰虚を補うには「水(津液)」がポイント」
陰虚体質では、水(津液)を補うことを意識した生活が大切です。東洋医学で考える「水」は体液だけでなく、汗や唾液、胃液、腸液、尿、リンパ液のような分泌液や排泄液など、血液以外のカラダのすべての水分を指します。この水は、カラダ全体に水分を充実させ、肌・関節・臓腑などに潤いを与えます。また、水はカラダの中の余分な熱を抑え、汗や尿として排出する働きもあります。
水が不足すると、カラダが乾燥します。すると、喉が乾いたり、肌荒れが起きたり、便秘になったりすることがあります。水の不足は、食生活の乱れ、食事の不足、働きすぎや運動しすぎなどが原因になることがあります。逆にカラダの中の水の流れが滞る(水滞)とむくんだり、下痢を起こしたり、鼻水が出たりすることもあります。水が滞る原因は、水分や冷たいものの摂りすぎです。甘いものや脂っこいものの摂りすぎが原因になることもあります。
「水」を補うためには、前章の「カラダを潤わせる食材は?」を参考に、バランスの取れた食生活を意識してください。陰虚は、体内の水分が不足しやすい状態です。体内の水分を補うために、豆乳や白色の食材、例えばレンコンや米を中心としたものを食事に取り入れるようにしましょう。豆乳や野菜などには、体に必要なエネルギーを与える食材が含まれます。日中にこまめに水分を補給し、陰虚体質を補うための食材を積極的に食べることで、心とカラダの健やかな健康を維持していきましょう。
ストレスで感じる喉の違和感を治す方法は?
ストレスによる喉の違和感を治すには、まずは陰虚の状態を改善することが大切です。また、緊張やストレスが喉の違和感に関係している場合もあります。
咳や喉の違和感が続く場合、漢方薬を使った治療が効果的です。例えば、ストレスによる緊張を和らげたり、心を落ち着けたりして喉の違和感を改善する漢方薬があります。また、体内の水の巡りを改善し、粘膜や気道、体全体を潤して喉の違和感を改善する漢方薬もおすすめです。
喉の違和感を改善するためには、声の出し方や呼吸法にも注意し、心身のリラックスを心がけることが重要です。あなたに合ったリラックス方法が見つかると、心の負担も減って、快適な毎日を過ごせるようになるでしょう。
陰虚が原因でほてりや熱感が生じる理由は?
陰虚体質で、ほてりや熱感が生じるのは体内の水(津液)が不足することが原因です。陰虚体質では、カラダの中の水分が不足しやすいため、特に喉や肌の乾燥が見られます。この乾燥状態が続くと、内熱が生じ、ほてりや熱感などの症状が現れてきます。また、便秘や便の乾燥、足の乾きなどの症状も伴いやすいようです。
漢方では、陰虚タイプの治療には水(津液)を補い、水分を補給することが重視されています。漢方薬を用いて体内のバランスを整えることで、カラダの乾燥を改善します。漢方薬の作用により、喉の乾きやカラダの乾燥を改善し、ほてりや熱感を抑える効果が期待されます。
日常的な水分補給を心がけ、便秘や肌の乾燥といった状態を防ぐことが陰虚では大切です。
陰虚を引き起こす原因とは?
陰虚には多くの原因が考えられますが、体内の水分と潤いが不足することが主原因です。他にも、長期間のストレス、不適切な生活習慣や食生活の乱れ、体質や遺伝、病気なども陰虚の原因として挙げることができます。糖尿病のような慢性病では、陰虚を引き起こしやすいようです。
陰虚体質では、水分補給で潤いを保つことが重要なのは当然ですが、質の良い生活を心がけることも大切な要素です。あなたに合ったリラックス方法や活動を取り入れることが効果的なことがあります。
漢方に視点を移すと、陰虚を改善するためには体質に合った薬を用いていきます。さまざまな種類の漢方薬の中から適切な方針で選んだ漢方薬によって陰虚体質を改善、不足している潤いを取り戻すことを試みていきます。
老廃物の排出を改善するには?
陰虚の方は、体質を改善することで、老廃物を効果的に体外に排出できるようになります。まず、体内の水分を補給し、バランスの取れた生活習慣を心がけることが基本となります。日々の生活の中、運動を取り入れ、汗をかくことは効果的な生活習慣です。
また、適切な食事や水分補給を通じて腸の調子を整えることも大切です。特に、食物繊維が豊富な食材を選び、腸内環境のケアを意識しましょう。さらに、心とカラダのバランスを保つため、リラックス習慣を持つようにしましょう。水分補給と共に、体内の潤いを保つための漢方薬を服用してみることも有効です。老廃物の効果的な排出を促し、体調を整えることができるようになります。
まずは、日々の生活習慣の見直しから、陰虚体質をケアしていきましょう。
<PR>