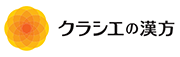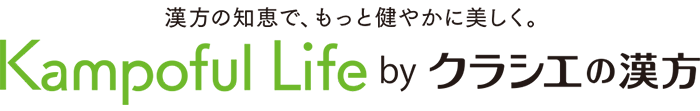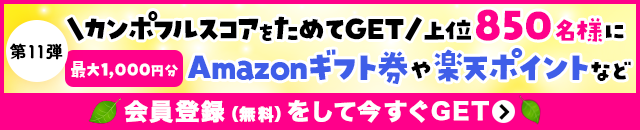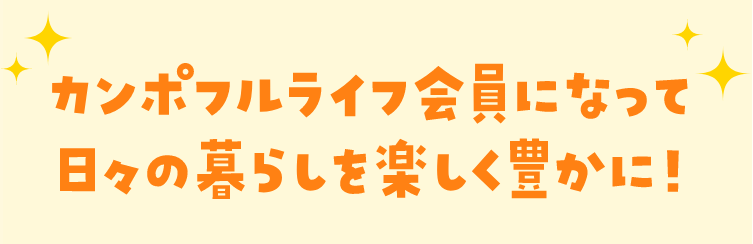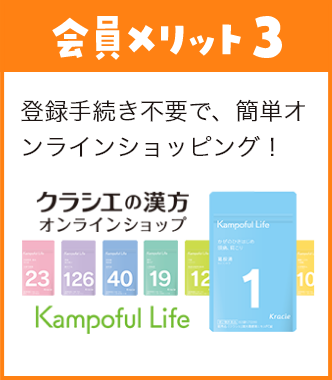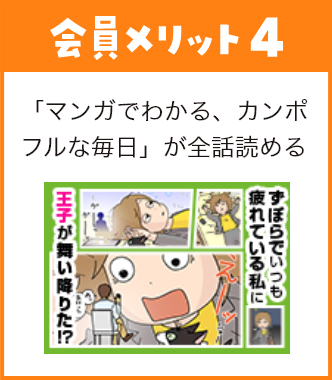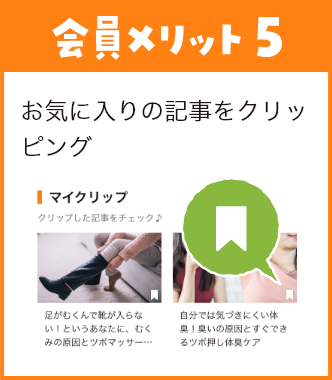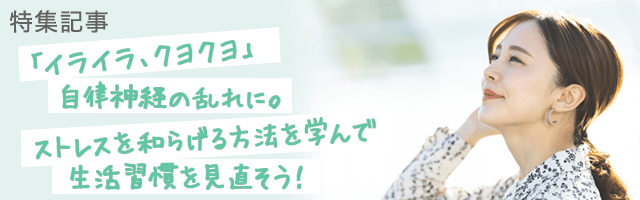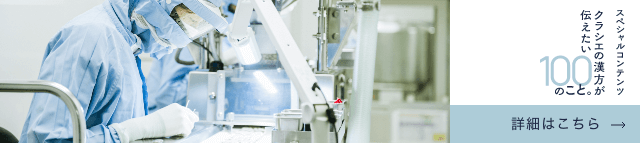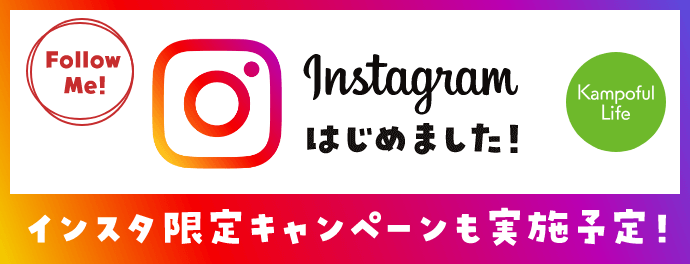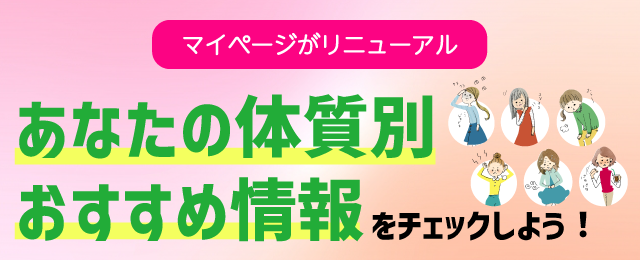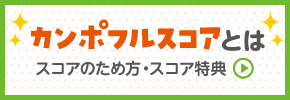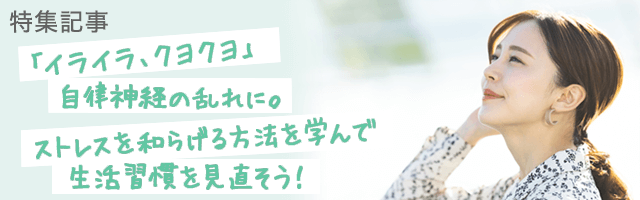目次
- まずは、漢方診断で体質チェック
- 「水滞」体質のあなたはどんな状態?
- 水滞体質の症状とは?
- 水滞体質におすすめの漢方薬
- おすすめ4つの生活習慣
- 水の巡りを良くする食材は?
- 水分が足りてない状態のサインは?
- 水はこまめに飲むか、一気に飲むか?
- 水分を1日に摂りすぎるとどうなる?
- 1日に1.2リットルの水を飲むとどんな効果がある?
- 【豆知識】水を飲んでからトイレに行きたくなるまでの時間は?
漢方の考えでは、カラダは「気(き)」・「血(けつ)」・「水(すい)」の3つの構成要素で支えられていると考えます。この3つの構成要素のバランスが悪いと私たちのカラダには、さまざまなトラブルが出やすくなると考えられています。漢方ではこの3つの構成要素のバランスを元に、体質を気虚(ききょ)・気滞(きたい)・血虚(けっきょ)・瘀血(おけつ)・陰虚(いんきょ)・水滞(すいたい)の6つのタイプに分けて、体質ごとにトラブルの原因をさぐります。
今回は『水滞』体質について解説します。体質改善法として、漢方薬による改善、生活習慣に関するアドバイスとおすすめの食べ物なども紹介していきます。体質を改善することで、元気なカラダを目指していきましょう。
まずは、漢方診断で体質チェック
まずは、あなたの体質が60秒で分かる体質診断コンテンツ「クラシエの漢方診断 」からスタートしましょう。
診断は漢方理論に則り、体質を6つに分類します。あなたの体質は何でしたか?
<PR>
診断結果が『水滞』だった方は、このまま読み進めてください。
その他の体質の方は、以下のリンクから該当体質の解説をご覧ください。
「水滞」体質のあなたはどんな状態?
水滞(水毒)体質はカラダの水の巡りが悪くなり、滞っている状態です。漢方では、「水(すい)」はカラダのすべての水分の総称で、体液だけでなく、汗や唾液、胃液、腸液、尿のような分泌液や排泄液なども入ります。水はカラダを潤す役割とともに、カラダにたまった不要な老廃物を尿や汗、鼻水などと共に体外へ排出する役割も担っています。水滞体質になるとカラダの水の巡りが悪くなるだけでなく、余分な水や老廃物がカラダのあらゆるところに溜まりやすくなるため、さまざまなトラブルが起こりやすくなります。
水滞体質の症状とは?
カラダがむくむ
水滞になり余分な水がカラダに停滞すると、全身がむくみやすくなると漢方では考えます。特に、ふくらはぎや足首など下半身はむくみやすい部位で、ひどいときにはだるさや痛みを伴うこともあります。関節も余分な水がたまってむくみやすい部位で、指が曲げにくい、こぶしが握りにくい、腕が上がりにくい、動かしにくいなどのトラブルが出やすいと言われています。
カラダが重だるい・頭帽感や頭重感
水滞体質では、カラダに余分な水がたまりやすくなるため、カラダが重く、重だるい、動きにくいなどと感じやすくなると漢方では考えます。また、水滞では頭痛も起こりやすく、その特徴は“頭の上に重い石を乗せたような痛み”の頭重感や、“きつい帽子をかぶって締め付けられるような痛み”の頭帽感として表現されます。雨や台風など天気が悪くなると頭痛が悪化しやすいのも水滞の頭痛の特徴です。
めまいがする
水滞では、耳にも余分な水がたまりやすく、それが原因でめまいを起こしやすくなると漢方では考えます。水滞によるめまいは“ふわふわする(浮動感)のようなめまいや、グルグル回るような回転性のめまい”が特徴で、これは西洋医学のメニエール病(内リンパ水腫・内耳のむくみ)に相当すると考えられています。
胃腸の不調
漢方では、水滞になると胃腸の不調が起こりやすいと考えます。漢方では、食べ物の消化吸収を担っている“脾(胃腸などの消化器系)は湿を嫌い、燥を好む”と言われていますが、水滞体質は脾に余分な水が溜まりやすく、不調を起こしやすくなると考えられているのです。そのため、水滞になると悪心や嘔吐、腹部の膨満感、下痢などのさまざまな胃腸トラブルが起こりやすいと言われます。
天気が悪くなると体調が悪くなる
水滞体質は水分の侵入にとても敏感です。天気が悪くなるとカラダが重だるくなる、台風が近づくと頭痛やめまいがする、お風呂など湿気の多い場所に入ると気分が悪くなる、水を多く飲むと体調が悪くなるなど、カラダに余分な湿気や水が入ってくるような環境になると症状が出たり、悪化するといった傾向が見られます。
水滞体質におすすめの漢方薬
五苓散(ごれいさん)
五苓散は、カラダのはたらきを高め、余分な水をカラダの外へ出す処方です。余分な水だけを出すので、一時的に不要な水がカラダにたまっているときに効果的な漢方薬です。口渇や尿量の減少があるような方に適しています。他にさまざまな浮腫(むくみ)、急性胃腸炎、下痢、暑気あたり、吐き気にも用いられています。
<PR>
- 水分の摂り過ぎや口が渇いて尿量が少ない方ににおすすめの漢方薬
五苓散(ごれいさん)
- 詳しく見る
当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)
当帰芍薬散は、全身に大切な栄養素を与え、血行を良くするのと同時に水分代謝を整えることで余分な水分をカラダからとり除いて、足腰の冷え症や生理不順を改善します。
<PR>
おすすめ4つの生活習慣
水の飲みすぎには注意しましょう
水滞体質は、すでに余分な水がカラダに溜まってしまっている状態です。そして、水の巡りが悪い水滞体質では、取り込んだ水分を上手に循環させて排泄するということができない状態です。そのため、水の飲みすぎは余分な水の量を増やす結果になってしまうのです。水分補給は適度かつ、少量を小まめに飲むようにしましょう。
甘いもの、油分の多いもの、ナッツ類に注意しましょう
漢方では、甘いものや油分の多いものはカラダを潤す働きがあると考えます。つまり、余分な水がカラダに溜まってしまっている水滞体質には不向きなため、摂りすぎに注意しましょう。またナッツ類も油分が多く、水滞体質の方は気を付けたい食べ物です。食べ過ぎで、湿疹などの原因になることもあります。湿気の多い梅雨や夏のナッツ類の食べ過ぎには特に注意しましょう。
胃腸の調子を整えましょう
胃腸は腎臓や膀胱と共にカラダの水分循環を支える大切な臓腑です。漢方では胃腸が弱ると、全身の水の巡りも悪くなりやすくなり、結果、水滞にもなりやすくなると考えます。さらに水滞になると胃腸が不調を起こすという悪循環に入ります。胃腸をしっかり整えることは、水滞には欠かせないケアです。
舌の苔をチェックしてカラダの水分量を把握しましょう
漢方では舌の苔の量はカラダの水分状態を反映すると考えています。舌の色が透けて見える程度の薄い苔がかかっている状態が健康だと言われていて、カラダに余分な水分がたまり始めると苔が徐々に分厚くなると考えます。毎日朝起きたら舌の苔をチェックして、常にカラダの水分状態を把握する習慣をつけましょう。
水の巡りを良くする食材は?
豆類
漢方は、豆類は水の巡りをサポートする食べものと考えます。ただし豆類の摂り方には注意が必要です。豆類の水溶性成分には有効成分が含まれると考えられています。豆を茹でる際に茹で汁を捨ててしまいがちですが、その茹で汁にこそ、水滞体質の方に大切な有効成分が多く含まれているのです。そこでおすすめしたいのが“お茶”です。小豆や黒豆など、茹で汁はお茶として、そしてゆで上がった豆はご飯のおかずに、といった形で豆のチカラを余すところなく頂きましょう。またトウモロコシやトウモロコシのひげを煎じたお茶も水の巡りをサポートする働きがあると漢方では言われています。豆類のお茶やウーロン茶、プーアール茶などとブレンドするのもおすすめです。
瓜類
漢方では、瓜類も水の巡りをサポートする働きがあると考えています。ただし、きゅうり・しろうり・にがうり・まくわうりは寒性、冬瓜・はやとうりは涼性など瓜類にはカラダを冷やす性質があるため、冷え症の方や寒い冬に食べるときには注意が必要です。加熱する、生姜・唐辛子・胡椒のようなカラダを温める温性・熱性の食材と組み合わせるなど、調理方法を工夫するなどしてカラダを冷やす性質を緩和することをおすすめします。
海藻類
海藻類も水の巡りをサポートする食材だと漢方では考えます。あおさや、昆布、海苔、わかめなど海藻類を日々の食卓に取り込みましょう。豆類同様、昆布・海苔は寒性、わかめは涼性と少しカラダを冷やす性質があります。暑い夏は問題ありませんが、TPOに合わせて調理方法を工夫してバランスを取るようにしましょう。
≪水の巡りを助ける食べもの≫
(利水効果がある)
大麦 玄米 米ぬか はとむぎ 春雨 小豆 黒豆 緑豆 カカオ 南瓜の種 落花生 アスパラガス エンドウ きゅうり 金針菜 グリンピース クレソン 香菜 コールラビ じゅんさい しろうり すべりひゆ セリ ぜんまい 高菜 チシャ 冬瓜 トウモロコシ トウモロコシのひげ 茄子 なずな白菜 はやとうり まくわうり まこもだけ ゆうがお わさび あけび スイカ スターフルーツ すもも ぶどう マンゴー メロン あおさ あさり 鮎 イカの卵 黒鯛 鯉 昆布 しため 白魚 すずき 鯛 なまず 海苔 はも はまぐり フカヒレ ふな 巻貝 わかめ 牛タン 鴨肉 豚のレバー ウーロン茶 紅茶 ココア 珈琲 ハイビスカス プーアール茶
※国立北京中医薬大学日本校監修 現代の食卓に生かす「食物性味表」より
水分が足りてない状態のサインは?
水滞体質で水の飲みすぎに注意をした結果、水分不足になることは避けてください。水滞体質でも、当然に適度な水分補給が必要です。では、水分が足りていない状態の人のカラダに現れるサインにはどのようなものがあるのしょうか?例えば、頭痛や体温上昇、尿量の減少、食欲の減退など、さまざまな不調がサインとして現れます。また、熱がカラダにこもりやすくなり、体温調節がうまくいかない場合があります。頭が重く感じたり、血の巡りが悪くなることで足の冷えを感じることもあります。
水分が足りないことによるカラダの不調を予防するには、日常的に水分補給を意識し、適切な食事を摂ることが大切です。水分補給の不足はカラダの水分不足による血液の循環悪化を招き、腎臓の活動を低下させることによってカラダに深刻な影響を与える可能性があります。
日中に定期的に水分を摂ることで、体調を上向きに保つことができます。特に、運動など活動の前後には、意識的に水分を補給するようにしましょう。
水はこまめに飲むか、一気に飲むか?
水滞体質の水分補給では適度かつ、少量を小まめに飲むようにしましょう。
一般論として考えても、小まめな水分補給の方をおすすめします。一気に大量に飲んだ水分は、カラダに吸収されずに尿として排出されてしまいます。体内の水分バランスを保ち、体温の調節や血液の循環を助けるためには、適切な方法での水分補給が大切です。正しい飲み方を心がけて、健やかな日々を過ごしていきましょう。
水分を1日に摂りすぎるとどうなる?
水分を1日に過剰に摂りすぎると、さまざまな影響がカラダに出ることがあります。
- ・体内の水分バランスが崩れ、むくみが発生。
- ・血流に負担がかかり、血管に圧力が加わることで、血圧上昇の原因になる。
- ・腎臓の処理能力を超過。尿として排出することが難しくなり、体内に蓄積される。
- ・手足が冷たく感じたり、重く感じたりする。
- ・血液が希釈され、体内の電解質バランスが崩れて低ナトリウム血症を引き起こす可能性がある。
これらは、重大な健康リスクを伴うため、水分摂取は適切な量を守ることが重要です。
1日1.2リットルの水を飲むとどんな効果がある?
ここまでは水分不足も、水の過剰摂取も避けるべきという話でしたが、では1日の水の摂取量はどの程度が適切なのでしょうか?実は、水の摂取量に関する基準値は特には設定されていません。
公益財団法人長寿科学振興財団が運営する健康長寿ネット「 水は1日どれくらい飲めば良いか 」によると、水に関する摂取量の基準値はないものの、人の体に必要な水の総量のうち、飲料水から得る水の量は1日約1.2リットルとされています。
では1日に水を1.2リットル飲むと得られる効果はどのようなものと考えられるのでしょうか?
- ・体温が適切に調節され、体内の代謝が活発になる。
- ・代謝が活発になると、エネルギー消費が増え、ダイエット効果が期待できる。
- ・血液の流れがスムーズになり、老廃物が効率よく排出されるようになる。
- ・血液循環が良くなることで、酸素や栄養素が全身に行き渡りやすくなり、カラダの働きが向上。
- ・肌が潤い、健康的な見た目を保つことができる。
- ・体内の水分バランスが整うと、体温調節機能も改善、熱中症や脱水症状の予防になる。
適切な水分補給は、健康維持や美容に大きな役割を果たしてくれます。
【豆知識】水を飲んでからトイレに行きたくなるまでの時間は?
摂取した水分が体内で吸収され、尿として排出されるまでのプロセスは約3時間以内です。
ただし、水分が尿として排出されるまでの時間には、体内の水分バランスや代謝の働き、食事の内容や量、治療中の病気の有無などが影響します。特に夕方に水分を多く摂ると、夜間のトイレ回数が増えることがあります。病気や治療中の方は、医師の指示に従い適切な水分摂取を心がけることが重要です。また、尿の量が多くなると感じる方は、食事や水分摂取の方法を見直すことで改善できる場合があります。体内の水分バランスを保ち、健康な生活を維持するためには、適切な水分補給と生活習慣の調整が大切です。
<PR>