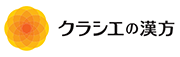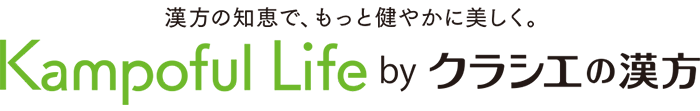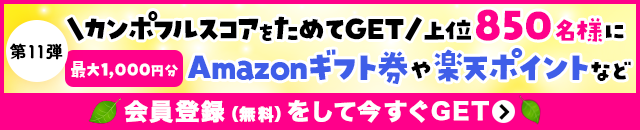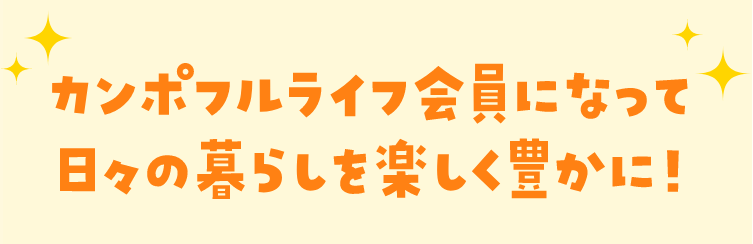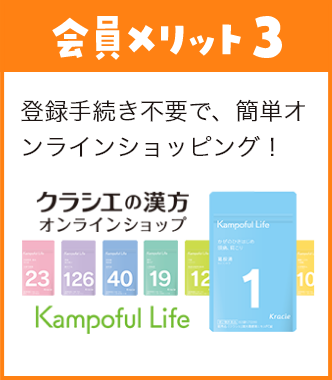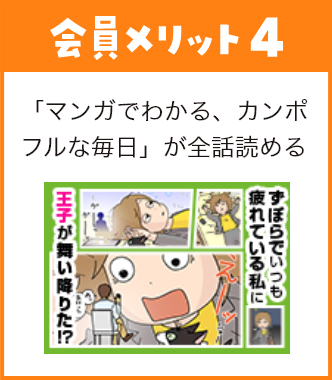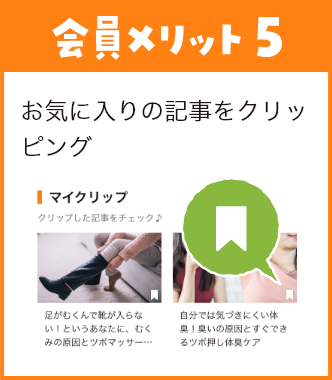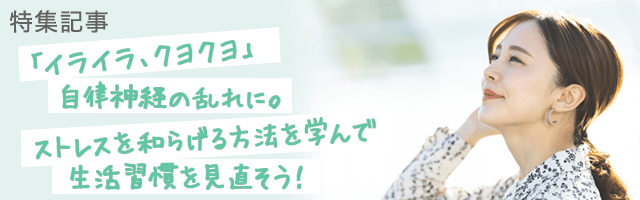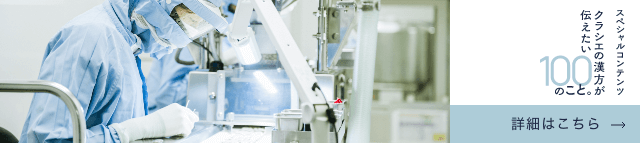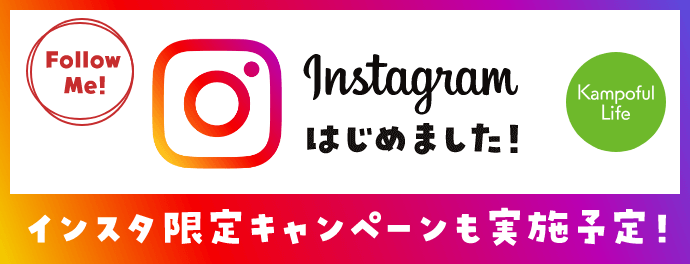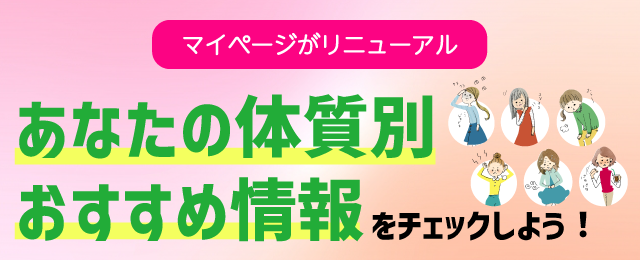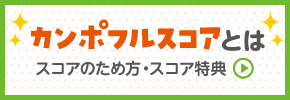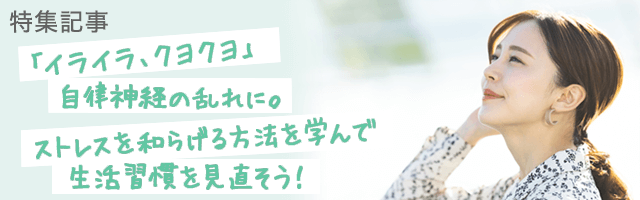目次
- お腹が空くのに食べたいと思わない原因は?
- お腹が空いているのに食欲が湧かない理由は?
- 【漢方で考える】食欲不振の原因とは
- あなたの食欲不振はどのタイプ?
- お腹は空くのに食欲が湧かない時の対処法
- 食欲不振におすすめの発酵食品と漢方薬
- 食欲不振に発酵食品がおすすめの理由
- 医療機関を受診するタイミングはいつ?
- 食欲不振の場合、受診するのは何科?
- ニセの空腹とは?
- ストレスで食欲がなくなった時の対処法
「お腹は空くのに食べたいと思わない」「お腹は空くのに食べられない」と感じたことはありませんか?もしかしたら、胃腸が弱っているのかもしれません。食欲不振の原因は、カラダの機能が弱っている、ストレス、カラダの中に余分な水分が滞っているなど、その人の体質や状況によって異なります。このような食欲不振で悩んでいる方のために、漢方の視点で考える食欲不振が起こる原因や食欲不振のときにおすすめの発酵食品などを紹介します。
お腹が空くのに食べたいと思わない原因は?
「お腹が空くのに食べたいと思わない」その原因にはいくつか考えられものがあります。
主な原因は、ストレス、薬の副作用、消化器の機能低下などです。例えば、ストレスが原因で消化器系の機能が低下すると食欲不振が起こる場合があります。特定の病気が原因となっている場合もあり、がんなどの重篤な病気が食欲不振を引き起こすこともあります。このように食欲不振が引き起こされる原因はさまざまなため、早期の原因特定と対応が必要です。
食欲不振の症状が続いている場合には、病気の可能性も考えて早めに医師の診断を受けることをおすすめします。専門家の適切な治療を受けることで、食欲不振の原因を特定し、対策を講じることができるようになります。また、消化器系の機能を改善する薬の服用が有効なこともあります。
お腹が空いているのに食欲が湧かない理由は?
ストレスや胃腸の弱り、体内で余分な水分が滞っている状態など、お腹が空いているのに食欲がわかない理由は、その人の体質や状況によって異なることから、さまざまなものが考えられます。
例えば以下のようなものです。
- ・ストレスが体内のホルモンバランスを乱すことで、食欲が抑えられる。
- ・胃腸機能の弱りでカラダは食べ物を受け入れる準備が整わず、食欲が湧かない。
- ・胃の中に余分な水分が溜まっていると胃腸の働きが鈍り、食欲が低下する。
- ・薬の副作用や質が良くない食生活も食欲不振の理由となります。
【漢方で考える】食欲不振の原因とは
「お腹は空くのに食べたいと思わない」といった食欲不振が起きる原因には、ストレス・冷えなどもありますが、次に、食事がとれなくなると倦怠感や体重減少が起こったり、やる気が出なかったり、吐き気をもよおすなど、カラダに大きな影響を与えます。
漢方ではストレスが起こる原因は肝(かん/自律神経や情緒などをコントロールする臓腑のこと)、消化器の不調は脾(ひ/脾は、食事を消化吸収し、気血水を作り出す臓腑のこと)が関係していると考えます。具体的にどのようなタイプがあるのかを確認し、自分の症状を当てはめてみましょう。
<PR>
あなたの食欲不振はどのタイプ?
食欲不振のタイプは、いくつかあります。自分のタイプを確かめてみましょう。
1.カラダを温める力が弱っているタイプ
胃腸の機能が弱っているため栄養がとれなくなり、カラダを温める力が弱っています。お腹や手足が冷えたり、むくみやすくなったりします。
2.ストレスがたまっているタイプ
精神状態を安定させる肝の気の流れが悪くなっています。カラダの中の気の流れが悪くなることから、脾(胃腸)に影響を与える食欲不振になります。
3.脾(胃腸)の機能が弱っているタイプ
口から入った食べ物を受け入れる脾(胃腸)と消化の機能が低下しています。お腹がすくのに食べられなかったり、お腹が張ったりします。
4.カラダの中に余分な水分が滞っているタイプ
脾(胃腸)の機能が低下しているため、胃の中の余分な水分が滞り、胃がつかえたり、お腹を押すとチャポチャポと音がします。
5.食べ過ぎ飲み過ぎで脾(胃腸)に負担がかかっているタイプ
暴飲暴食などが原因で消化の機能が悪くなり、胃腸に負担がかかっています。お腹が張ったり、胸焼けを起こしたりします。
お腹は空くのに食欲が湧かない時の対処法
「お腹は空くのに食べたいと思わない」時のセルフケア・セルフメディケーションの方法を紹介します。
食事を工夫する。
消化に良い食べ物を選び、少量ずつ小まめに食べるように工夫してみましょう。お粥やスープ、ヨーグルトなど食べやすいものが良いでしょう。
水分補給に気をつける。
十分な水分を摂ることが大切です。温かいお茶やスープなど、胃に優しいものを優先しましょう。
ストレスを管理する。
ストレスが原因で食欲不振になることがあります。リラックスする時間を大切にし、心地よいくらいの適度な運動や楽しめる趣味を持つことが効果的です。
OTC(Over The Counter)薬を利用する。
市販の胃腸薬や漢方薬で効果が得られる場合もあります。ただし、薬剤師や登録販売者に相談して、使用方法や用量を守って服用することが大切です。次の章でおすすめの食品と漢方薬を紹介します。参考にしてみてください。
食欲不振におすすめの発酵食品と漢方薬
食欲があるのに食べられない、食事がとれないので疲れがとれないなどの方におすすめの発酵食品を紹介します。食べやすいもの、カラダの調子を整える働きのあるものがあります。
<おすすめの発酵食品4選>
・ヨーグルト
口当たりがさっぱりして食べやすい食材です。カラダの熱を冷まし、潤いを与えます。ただし、カラダが冷えている人は控えるようにしましょう。
・納豆
カラダの中の血のめぐりをよくする食材です。カラダの冷えによる食欲不振や気を補う作用もあるため、元気がでない、やる気が起こらないという方にもおすすめです。
・味噌
カラダに熱がこもっている方におすすめの食材です。カラダの中の余分な水分を排出する働きがあります。
・お酢
むくみを解消し、カラダを温める食材です。お酢はさっぱりした味が食欲を増します。ただし、胃腸の弱い人は、控えめにしてください。
<食欲不振タイプ別に選ぶ漢方薬>
生活習慣を変えてみたり、食べるものを変えてみたりしても食欲不振が改善されない方には、漢方薬をおすすめします。食欲不振状態では、カラダに必要な栄養が摂取できなくなるため、体力の不足、免疫力の低下につながります。自分の体質にあった漢方薬を見つけて早めに対処していきましょう。今回は3つのタイプにしぼって漢方薬を紹介します。
・ストレスがたまっているタイプには
■半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)
みぞおちがつかえ、吐き気が起こり、お腹がゴロゴロ鳴るなどの症状に使われる漢方薬です。神経性胃炎・胃潰瘍・口内炎などにも使われます。カラダの中の気の流れをよくするため、脾(胃腸)の負担となっている気の流れの滞りがよくなります。
・胃腸の機能が弱っているタイプには
■六君子湯(りっくんしとう)
胃腸が弱く、みぞおちがつかえ、疲れやすいなどの症状に使われる漢方薬です。胃痛・胃炎・胃下垂などにも使われます。カラダの中の気の流れが滞っていることが原因で起こる胃の不調に使われます。気を補いカラダの中の気のめぐりをよくすることによって胃の不調を改善させます。
・カラダの冷えが原因で起こるタイプには
■胃苓湯(いれいとう)
下痢、吐き気があり、口の乾き、尿量の減少などの症状に使われる漢方薬です。暑気あたり、急性胃腸炎などにも使われます。カラダが冷えることによりお腹にたまった余分な水分を排出する働きがあります。
<PR>
食欲不振に発酵食品がおすすめの理由
食欲がないときに、なぜ発酵食品がおすすめなのでしょうか。
発酵食品とは、乳酸菌・麹菌など微生物の働きによってできる食品を指します。この発酵食品には、次のようなカラダに嬉しい特徴があるからです。
・カラダに吸収されやすい
発酵食品は、微生物がタンパク質やでんぷんなどの栄養素を発酵の過程でこまかく分解するため、カラダに吸収しやすく、お腹に優しいのが特徴です。植物性食品では栄養価の高いタンパク質で納豆など消化吸収率が高いものがあります。
・風味や味わいが増す
発酵食品は、食材を発酵させることによりタンパク質を分解し、グルタミン酸の成分ができることによって、元の食材にはなかった風味や味わいなどを作り出すことができます。風味や味わいを感じる代表的な日本の食材には、醤油や味噌、納豆などがあります。
・栄養素を増やす
発酵食品は、元の食材に比べビタミンB1やビタミンKなどの栄養成分が増えます。例えば、ビタミンB1は味噌に、ビタミンKは納豆に多く含まれています。発酵食品では、元の食材に含まれるものが増えたり、元の食材になかった新しい成分が作り出されることもあるのです。
・免疫力が向上する
発酵食品には、カラダによいといわれる乳酸菌・麹菌・ビフィズス菌などが含まれています。これらの菌に代表される善玉菌は、腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)のバランスを整え、免疫力を上げる効果があります。カラダに必要な善玉菌を増やすためには、ヨーグルト・納豆・漬物などをおすすめします。免疫力の向上には、毎日とり続けることが大切です。
医療機関を受診するタイミングはいつ?
「お腹は空くのに食べたいと思わない」状態でセルフケアやセルフメディケーションを試してもなかなか改善が見られない場合、以下のような状況では医療機関の受診をおすすめします。
・症状が2週間以上続く
長期間にわたる食欲不振は、何らかの基礎疾患が原因の可能性があります。
・体重の減少が見られる
意図しない体重減少が見られる場合は、早めの受診が必要です。
・他の症状を併発している
発熱、腹痛、吐き気、嘔吐などの症状がある場合は、すぐに医師の診察を受けるべき状態です。
・精神的な問題を抱えている
ストレスやうつ症状が原因の場合は、心療内科の受診を検討してみてください。
食欲不振の場合、受診するのは何科?
お腹が空いているのに食べたくない食欲不振が続く場合、まずは内科や消化器内科の受診が推奨されます。食欲不振の原因が、胃や腸の機能低下、ストレス以外にも、がんなどの重篤な病気であることも考えられます。症状が続いている場合、病院で適切な検査を受け、消化器の状態を確認することが重要です。
心の問題が関係している場合には、心療内科の受診を検討してみてください。心療内科では、ストレスや心の病が原因となる食欲不振に対処してくれます。早期にクリニックや病院で専門医の診断を受けることにより、食欲不振の主な原因を特定し、適切な治療を受けることが可能です。
病の予防や改善には、定期的な検査と診察を受けることが大切です。
ニセの空腹とは?
「ニセの空腹」という言葉を聞いたことはありますか?ニセの空腹とは、実際にはカラダがエネルギーを必要としていないのに空腹を感じてしまう状態のことです。
ニセの空腹は、脳が食欲を刺激する物質を分泌することで、空腹と錯覚する状態です。目に見える食べ物がおいしそうという誘惑からニセの空腹が起こることがあります。その他にはストレスや水分不足も原因となります。脳がこれらの状態を空腹と誤認して、食べ物を欲しがるのです。
ニセの空腹は体内のエネルギーが不足しているわけではないため、本当の空腹状態ではありません。ニセの空腹を防ぐには、バランスの取れた食事と十分な水分の摂取が大切です。
もし、ニセの空腹だと感じた場合は、まず水を飲んでみることや、何か別の活動をして気を紛らわせるのが効果的です。
本当は、エネルギー補給の必要がないにもかかわらずニセの空腹に騙されて食べてしまうことは、体重増加や健康に悪影響を及ぼす可能性があるので注意が必要です。
ストレスで食欲がなくなった時の対処法
ストレスで食欲がなくなった場合に試してほしいことがあります。
まずは規則正しい生活を心がけながら、ストレスを減らしていくことが大切です。
- ・リラックスできる時間を作り、適度な運動をしてみましょう。
- ・心の健康のために、趣味や好きなことに時間を費やしてみてください。
- ・消化の良い食べ物を、少量ずつ、ゆっくりと食べるようにしましょう。
- ・味の変化を感じ、楽しむため、食事の方法や食べ方を工夫することもおすすめします。
状態によって、心療内科や内科のクリニックを受診し専門的なアドバイスを受けることが必要な場合もあります。体質や状態に応じた薬の服用で状態を改善していくこともあるでしょう。適切な方法でストレスを管理し、食欲不振を改善することは、健康の維持につながります。
<PR>
監修
多田有紀(https://x.com/sora_writer)
漢方薬膳コンサルタント