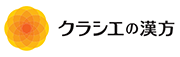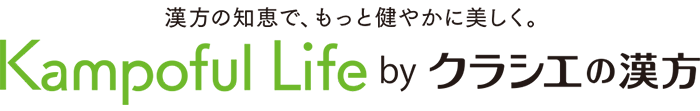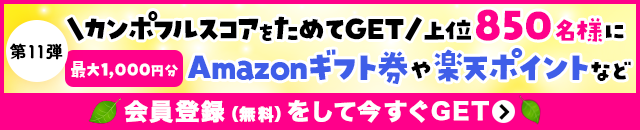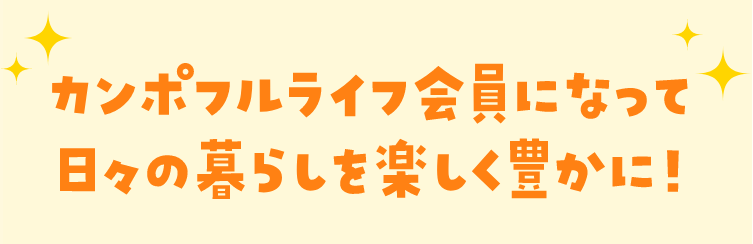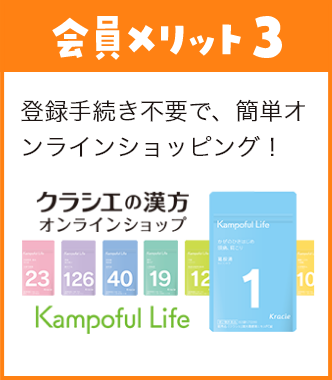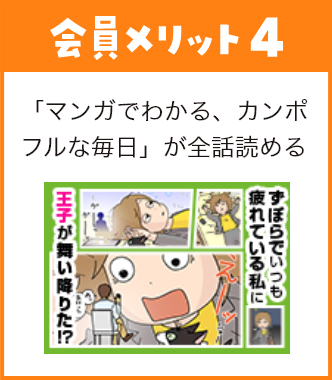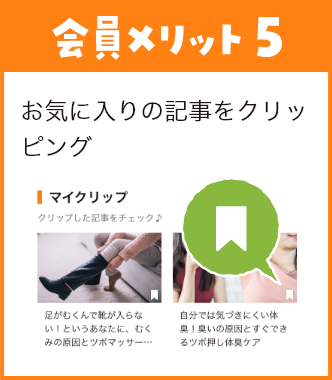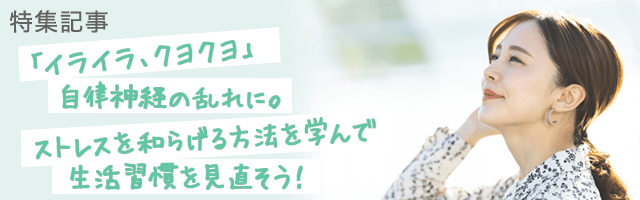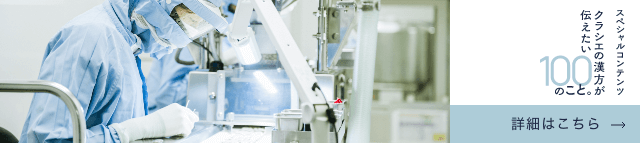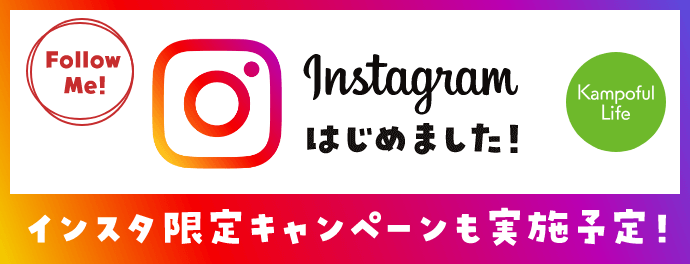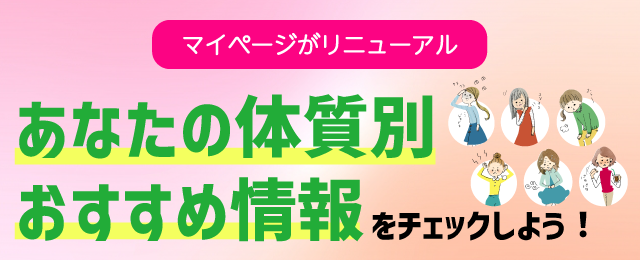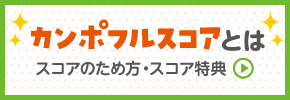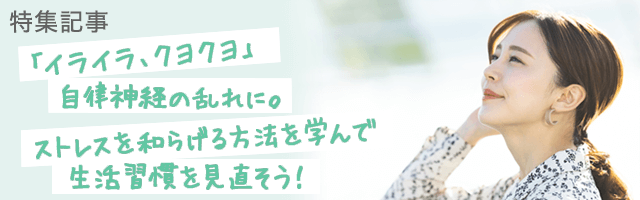目次
「スパイス」といえば、日本人におなじみの「カレー」を思い浮かべる人が多いかもしれません。カレーには健康に良い多くのスパイスが含まれており「美味しい漢方薬(薬膳)」とも言われています。スパイスは、料理をするうえでアクセントをつけたり、風味を調えたりするのに欠かせない香辛料ですが、同じように香り豊かな植物に「ハーブ」があります。ハーブはお茶として楽しむだけでなく、スパイスとして利用されることも多くあります。この記事では健康と美容に効果的なスパイスの日常的な活用法とそのメリットを活かすレシピをご紹介します。
植物のパワー「スパイス」「ハーブ」の違い
日本においては、スパイスとハーブについての厳密に区別する定義はありません。スパイスもハーブも、食べ物や飲み物に香りや色、風味をプラスするという点では同じです。植物学的には、茎と葉と花を利用するものをハーブ、樹皮や種子、実、根などを使うものをスパイスと区分する説もありますが、実際に分類しきれてはいません。その理由は、国によって定義付けが違ったり、葉や種子ではそれぞれ扱いが異なったりする場合があるためです。例えば、タンポポ茶はタンポポ(ダンデライオン)の『根』を煎じたものですが、スパイスではなくハーブティーに分類されています。また、カレーに使われるクローブは丁子(チョウジ)の『花』のつぼみを用いていますがスパイスとされています。世界中で使われているスパイス、ハーブの種類は350~500種、日本だけでも100種類が使われていると言われています。
スパイスは「薬」になる?
スパイスは、料理の品質や風味を調えるだけでなく消化を促進したり胃腸を整えたりするなど生薬としての効能があり、漢方薬の原料としても活用されているものがあります。インド・スリランカの伝統医学アーユルヴェーダの考え方に基づいたインド圏の家庭料理では多くのスパイスが使われますが、これらは個々のスパイスにおける整腸作用や消化促進作用等はもちろん、使われるスパイスの種類と組み合わせによって健康への有用性が期待されているのです。「医食同源」という言葉は、食事と薬は同じ源から成り立っており、健康を保つためには日々の食事が非常に重要であるという考え方を表しています。この概念は日本や中国の漢方思想の基礎であり、薬膳のルーツでもあります。体質や季節に合わせ、食事を通して未病に対応していくという健康維持のために、意識してスパイスを活用していきたいものですね。
スパイスの健康効果を知ろう!
「生薬」とは、漢方薬の原料にもなる薬効のある植物や食材のことです。広い意味ではスパイスだけでなく旬の野菜も生薬。旬の食材、薬効のあるスパイスを体質や体調に合わせて食べるものが薬膳と言えます。スパイスの健康効果を知り「ミントティーで頭をしゃっきりさせたい」など自分に必要な効果実感をセレクトし、日常生活に取り入れてみましょう。
【スパイスの特徴・健康効果】
・ペッパー(胡椒・こしょう)
辛味成分が気(き)を巡らし消化不良を改善、カラダの内側を温めるため冷えによる胃腸の不調を整え血行を促進すると言われています。辛味や香り消しといった下ごしらえだけでなく抗菌・防腐効果があり料理に活用しやすいスパイスです。
・クローブ(丁子・ちょうじ)
熱帯多雨原産の常緑樹フトモモ科の花のつぼみを乾燥させたものでバニラに似た甘い香りと刺激的な香味があります。抗酸化力や殺菌力が強いため肉料理によく使用されます。胃腸の働きを高める作用や抗炎症作用もあると言われています。
・シナモン(桂皮・けいひ、ニッキ)
世界最古のスパイスの1つといわれ、40度前後で香りが高くなります。樹皮からとれる精油には殺菌効果・活性作用があり、化粧品にも使用されます。抗酸化作用が高いポリフェノールを含み、香りの素には血流促進と血管を保護する成分が含まれていると言われています。
・ナツメグ(肉荳蔲・にくずく)
独特の甘い香りがあり、挽き肉料理や魚料理の臭みを消すために用いられます。ナツメグに多く含まれている銅は貧血予防に有効です。また消化促進や食欲増進、美肌にも効果があると言われています。
・フェンネル(茴香・ういきょう)
若い葉および種子(フェンネルシード)は、甘い香りと苦味が特徴的で中国の五香粉の原料のひとつとされています。消化促進、消臭、解毒作用があり、咳止めの効果があると言われています。冷えによる痛みの改善や独特の香りで気を巡らせる効果も期待できます。
・ターメリック(姜黄・うこん)
黄色い成分はクルクミンと呼ばれるポリフェノールを含み、抗酸化作用や抗炎症効果があると言われています。消化促進や新陳代謝をよくする働きがあるとも言われ、体質改善や皮膚病にも用いられます。
・カルダモン(小豆蔲・しょうずく)
スパイスの女王とも呼ばれるほどに名高いスパイス。疲労回復や整腸作用があると言われていますが、冷性で身体を冷やす働きも期待できます。爽やかな香りが食後の口直しにも適しているため、デザートや飲み物にも使われます。
・コリアンダー(胡荽子・こずいし、パクチー)
葉は独特の強い香りがあり、カロチンやビタミンを豊富に含みます。胃腸のはたらきを促し、新陳代謝を活性させる作用があると言われています。種子(コリアンダーシード)は葉とは異なり、爽やかな香りで消化促進とデトックス効果が期待されアレルギーにも有効です。
・ミント(薄荷・はっか)
ストレス対策にスッーとした香りでリフレッシュ効果を発揮します。他にも消化促進効果、頭痛、ホットフラッシュ、眠気防止に効果的です。料理やお菓子だけでなく歯磨き粉や化粧品などにも多く利用されています。
・ジンジャー(生姜・しょうが)
香辛料としてだけではなく食材としても食べられています。生薬としても有名で、発散、健胃、保温、解熱、消炎、鎮吐など多くの効果が期待でき、免疫力を高めるために風邪予防にもよく用いられます。
※スパイスは基本的には光や熱、湿気に弱いため密閉容器に入れ冷暗所にて保管することがおすすめです。冷蔵庫保管は出し入れの温度差から結露による湿気を帯びやすいため注意が必要です。
※スパイスは料理を引き立てる目的での使用量にとどめましょう。スパイスの過剰摂取は、健康への悪影響をもたらす可能性があります。
日常生活に取り入れるスパイスの簡単レシピ
スパイスを使った簡単なレシピをご紹介します。インドやバングラデシュなどで食べられている炊き込みご飯「ビリヤニ」を炊飯器で簡単調理。細長い形が特徴のインディカ米「バスマティ米」を使うと本格的になりますが、スパイスによって風味豊かになるので普通のお米でも手軽に仕上がります。ピラフやパエリア感覚で『お家でスパイスご飯』をぜひ試してみてください。クミンや生姜の消化促進効果やターメリックの肝機能の強化などのカラダにうれしい効果実感が期待できます。
★炊飯器で作るお手軽ビリヤニ風
【材料】2人分
・米1合
・オリーブオイル(大さじ1)
・玉ねぎ(1/2個)
・ニンニク(1かけ)
・生姜(1かけ)
・クミン(小さじ1弱)
・ガラムマサラ(小さじ1弱)
・コショウ少々
・パクチー又は乾燥パセリ(適宜好みでトッピング)
・A:鶏肉(200g/一口大にカットされたもの)、ヨーグルト(大さじ1)、麺つゆ(大さじ1)、塩・コショウ少々
・B:トマト1個(又はカットトマト缶150g)、カレー粉大さじ1程度(又はターメリック、チリパウダー、カルダモン、コリアンダー、シナモン等をミックス)、塩少々、水120ml
【作り方】
- ① 米1合を洗っておく。
- ② Aの材料を混ぜ合わせておく。
-
③ フライパンにオリーブオイルを熱し、粗くみじん切りにした玉ねぎ、ニンニク、生姜を炒め、火が通ったらクミンとガラムマサラ、コショウを加えて②の鶏肉を投入し焼き色がつくまで焼く。

- ④ Bの材料と②のつけ汁の残りを入れひと煮立ちしたら火を止める。
-
⑤ 炊飯器に米と④を汁ごと入れて普通に炊飯する。

-
⑥ 器に盛り好みでパクチー又は乾燥パセリをちらして完成。

もっと簡単!飲み物に入れるだけのスパイスアイデア
料理が苦手な人や忙しい人には、飲み物にスパイスを加えるだけの簡単アレンジがおすすめです。好きな飲み物に効果を意識して手軽にアレンジを取り入れてみましょう。
★疲れた午後に:コーヒーアレンジ
<カルダモン・コーヒー>
「香りの王様」「スパイスの女王」とも呼ばれるスパイス、カルダモンの粉末をコーヒー豆とともに抽出してみましょう。少し甘い独特な香りが、疲れた脳を休めてリラックスした気分に誘います。口臭予防にも効果的なため食後の一杯におすすめ。
★カラダが冷えている方に:紅茶アレンジ
<シナモン&クローブ・チャイ>
紅茶の茶葉にシナモンとクローブの粉末を入れて淹れるだけで、スパイシーなチャイが簡単にできあがります。紅茶はティーバッグでもOK。お好みで温めたミルクやハチミツを加えると気持ちまでほっこり温まります。
★スッキリ起きたい朝に:緑茶アレンジ
<ミント・グリーンティー>
モロッコでよく飲まれているというミントを使用した緑茶。爽快で冷涼感があるためスッキリと目覚められます。ミントのメントールが緑茶と相性抜群。砂糖やハチミツを入れて甘く仕上げてもOK。
☆番外編:味噌汁アレンジ
<美味しく腸活・カレー味噌汁>
粉末の市販カレー粉にはターメリック、コリアンダー、ジンジャー、シナモンなどが配合されています。発酵食品の味噌汁にさっと加えるだけで味の変化が楽しめるだけでなく気軽にスパイスを摂り入れて美味しく腸活できます。
<PR>
-
- 気になる症状に漢方薬という選択肢
クラシエの漢方オンラインショップ
- 詳しく見る
<PR>
-
- 漢方療法推進会
漢方のプロフェッショナルに相談してみませんか?
- 詳しく見る

那須久美子
広告会社、大手化粧品会社宣伝部にてCM、雑誌等の広告制作に携わる。
その後フリーランスとしてバレエ講師、ピラティスマスターストレーナー、ヨガセラピスト、介護予防運動指導員として老若男女への伝える仕事に従事。
企業や官公庁での健康アドバイザーや研修講師も務める。
国家資格キャリアコンサルタントとしては企業内障害者ジョブコーチを経て自治体事業の就労支援プログラム講師とカウンセラーを兼任。
現在は就労支援事業の現場統括責任者を務める傍らキャリアコンサルタントのスクールにおいてオウンドメディアの監修も担当。
・ヘルスケアデザイナー
・バレエティーチャー
・ピラティストレーナー、ヨガセラピスト
・アスリートキャリアコーディネーター
・国家資格キャリアコンサルタント
・漢方アドバイザー
・介護予防運動指導員
HP:https://www.kandworks.com/about