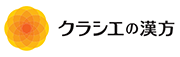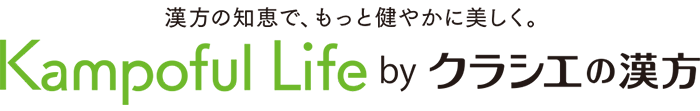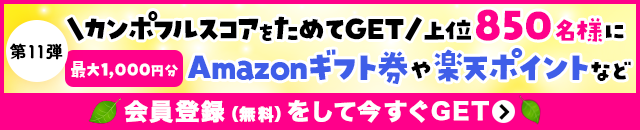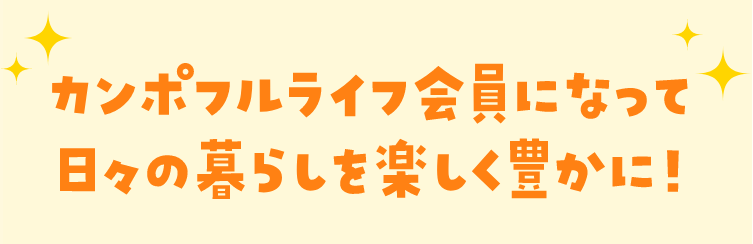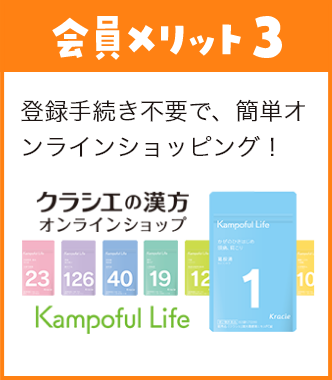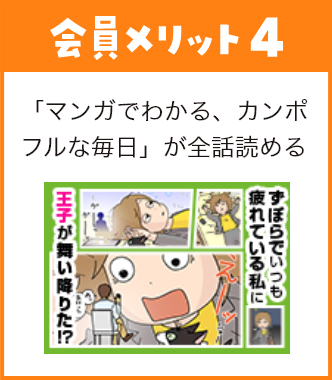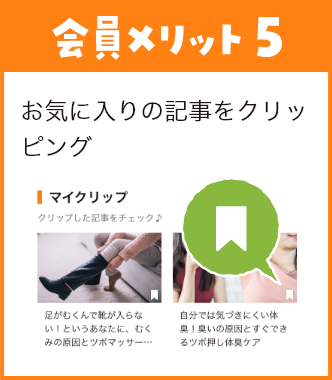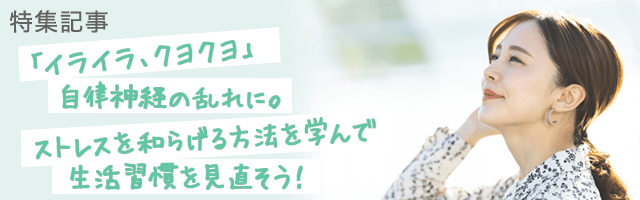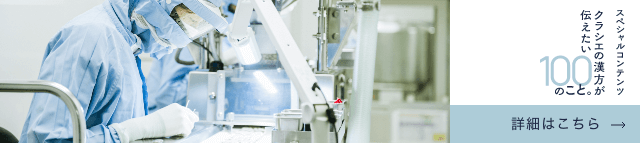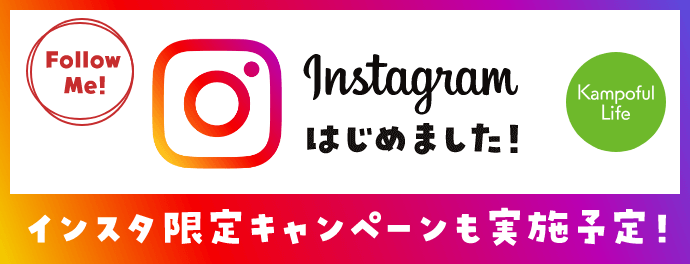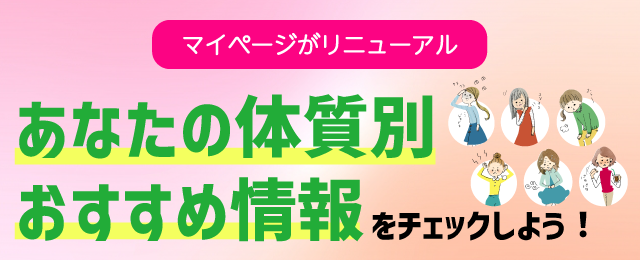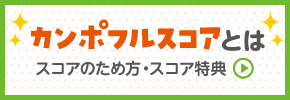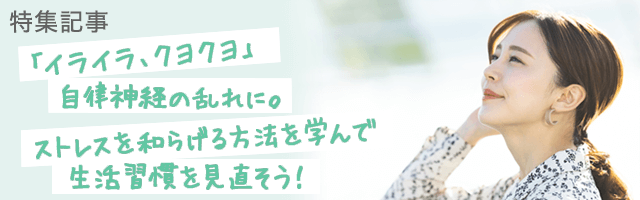目次
なぜ、周りとうまくコミュニケーションをとれないのだろう…。なぜ、みんなができることを自分はうまくできないのかな…。みんなと違うことに悩み、苦しんでいませんか?感情をコントロールできなかったり、悪意はないのに相手を怒らせてしまったり、なぜか周囲とうまく付き合えない。このような悩みの背景には、発達障害(神経発達症)という特徴が隠れている場合があります。今回は、発達障害が起こる原因や特徴、向き合い方などについてご紹介をします。
発達障害が起こる原因
発達障害の原因は解明されていませんが、脳の働きの違いにより、行動や情緒に様々な特徴が現われると考えられています。お子さんが発達障害と診断された親御さんの中には、育て方に問題があったのかもしれない…。と悩んでいる方がいるかもしれません。発達障害の原因については、遺伝子要因や環境要因が研究されていますが、育て方や本人の努力不足ではありません。
発達障害のあるお子さんを育てている親御さんは、日々の生活で精神的なストレスや将来への不安を感じていることも少なくないでしょう。頑張らないといけない。その気持ちがストレスとなり、親御さんが病気になっては悪循環となります。一人で、家族で抱えこまず、周りの家族・友人、または発達障害の専門家に相談してみてください。
発達障害の特徴と基本知識
発達障害にはいくつか種類があり、同じ種類でもその特徴の現われ方は多様で、他の発達障害や精神疾患を併せ持つこともあります。子どもの頃から特徴が現れることが多いですが、大人になってから気づくこともあります。なぜ、大人になってから発達障害に気づくケースがあるのでしょう。理由の一つとして、子どもの頃は個性としてとらえられていた発達障害の特徴が、社会に出てから仕事のつまずきや周りとのずれを感じ、自身で初めて発達障害ではと疑うようになるからです。
次に発達障害の種類と特徴を紹介します。
※正確な診断には、医療機関を受診し精神科や心療内科など、発達障害を専門とする医師にご相談ください。
<発達障害の種類と特徴>
発達障害は大きく「自閉スペクトラム症(ASD)/広汎性発達障害」「注意欠陥多動性障害(ADHD)」「学習障害(LD)」「その他の発達障害」に分けられます。この中でも大人の発達障害として多いのは、自閉スペクトラム症と注意欠陥多動性障害といわれています。
自閉スペクトラム症(Autism Spectrum Disorder: ASD)/ 広汎性発達障害
以前は「自閉性」「アスペルガー症候群」「特定不能の広汎性発達障害」などを含む「広汎性発達障害(こうはんせいはったつしょうがい)」とも呼ばれていた発達障害(神経発達症)です。2013年にアメリカ精神医学会の診断基準DSMの改定で、自閉スペクトラム症という名前に統一されています。興味関心の偏り、特定のものごとへのこだわり、対人関係が苦手といった特徴があります。症状が軽い場合は大人になってから初めて診断されることもあります。自閉スペクトラム症は、遺伝と環境が関係していると考えられています。
<特徴>
・言葉の発達が遅い
言葉の意味を理解しにくい、話す際に使う単語が限られている、または殆ど話さない。
・コミュニケーション障害
無反応、冗談・皮肉・例え話が通じにくい、話し相手の気持ちがわからない、空気を読むのが難しい、一方的に話す、目と目があわない。
・こだわりが強い
特定の手順・習慣にこだわり、いつもと同じでないと落ち着かない。変化を嫌う。(作業順や通う道順、ものの配置)
同じ行動を繰り返す(手を叩く、手足をバタバタさせる)
注意欠陥多動性障害(Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder: ADHD)
本人の努力とは無関係に、一つのことに集中するのが難しかったり、衝動的な言動をしたりすることがある発達障害(神経発達症)で、日常生活に支障をきたすことがあります。これらの症状は、幼い子どもにもみられる特徴でもあり、年齢によっては注意欠陥多動性障害と診断することは難しいといわれています。また、見た目だけではその特徴がわかりにくく、個人の努力不足と誤解されてしまうこともあります。
<特徴>
・不注意が目立つ
集中できない、気が散りやすい、他人の話を聞けない、なくしもの・忘れものが多い、計画通りに行動できない、遅刻をする、約束を忘れる。
・多動性
じっとできない、待てない、カラダを動かす、常に何かを触る。
・衝動性
欲求をコントロールできにない、イライラする、他人の気持ちや順番を考えず思ったことを口にしてしまう。
学習障害(Learning Disorder:LD)
知的発達に遅れはないにもかかわらず、主に読む・書く・計算など特定の領域で学習に困難がみられる発達障害(神経発達症)の一つです。就学前に気づくことは難しく、小学校に入学し学習を始めたタイミングで先生や保護者が気づく場合も少なくありません。学習障害をもつ子どもは、自信を失ってしまうケースがあります。本人の苦手領域を理解して、勉強や仕事の仕方を工夫することでその影響を和らげることもできるといわれています。
<特徴>
・読字障害
文字・音・数字が結びつかず覚えられない、単語が理解できない、読んでいる文章の内容をまとめられない、どこまで読んだかわからなくなる。
・書字障害
文字をバランスよく書けない、書き順を間違う、考えたことを文章にして書けない。
・算数障害
数の概念がわからない、数字が読めない、計算できない。
その他の発達障害
トゥレット症・吃音症も発達障害に含まれることがあります。トゥレット症は本人の意思と関係なく突然カラダを動かしてしまったり、声を出してしまったりする状態で、吃音症はどもったり、何度も同じ言葉を繰り返したりする状態です。トゥレット症・吃音症はどちらも日常生活に支障が現れる場合があります。
尚、上記に挙げられた特徴に該当した場合でも、必ずしも神経発達症であるというわけではありません。ご自身やご家族が日常生活でお悩みを抱えているようであれば、一度医師などの専門家に相談してみてください。
発達障害との向き合い方。生活上のコツ
発達障害がある人や周りの家族は、日常生活で様々な困難や悩みを抱えています。発達障害は症状や特徴を理解して対処することで、日常生活で感じる生きにくさを減らすこともできる障害です。発達障害において、主に日常で困ることと、その対処法は以下です。
・なくしもの・忘れものが多い
大切なものは目立つ場所に置く、なくしやすいものは決まった場所に保管する習慣を身につける。
・片づけができない
ものの分類、置く場所を決めておく。ものを増やさない。
・自分で時間の調整ができない
予定があるときはアラームを利用する。ノートにスケジュールを書き、ノートを見る習慣をつける。
・人の名前を覚えられない
名前をメモに記録する。相手に自分の特徴(名前を覚えられない)を伝えておく。
・においに敏感で気持ち悪くなる
マスクをつける。好きなにおい袋や香水を持ち歩く。
・一度に複数のことができない・優先順位がつけられない
やるべきことを紙に書き出す。締め切りが近いものから始める。重要なものには、番号をつける。
・周りの音が気になり集中できない
ヘッドホン・イヤーマフを利用する。音の少ない場所で作業をする。イライラするときは、一旦その場所から離れる。
・トラブルが起こるとパニックになる
静かな場所に移動する。本人が冷静になるまで待つ。危険なものは目につかない場所に置く。想定されるトラブルと対処法を書き出し、トラブルが起きたときに見るようにする。
・抽象的な表現が理解できない
具体的に確認をする。
・学習障害
PCやスマホを利用する。読むのが苦手(読字障害)ならスマホの読み上げ機能、書くのが苦手(書字障害)ならスマホの音声入力を活用する。
発達障害と毎日の食事
発達障害を抱える方には、特定の味や食感のものを食べない「こだわり特徴=偏食」が強く現われる場合もあります。無理に苦手なものを食べさせると、食事そのものが苦痛になることもあります。わがままで食べないのではなく、特徴で食べられないということを理解することが大切です。偏食の原因は様々ですが、以下主な原因と対策についてご紹介します。
<偏食の原因と対策>
発達障害の人は、嗅覚・視覚・味覚などが敏感な場合があります。食べものにも好き嫌いがあり、ルーティンでの食事を好みます。
・触覚過敏
揚げものの衣がチクチクして痛い、じゃがいものホクホク感が苦手など、食感で食材を苦手と感じる場合があります。また2つ以上の食感が混ざると食べられないこともあります。調理法を変えてみる(揚げる、細かく刻む、ミキサーを使うなど)、食感別に分けて食べられるようにすることをおすすめします。(揚げものは衣と中身を分ける。カレーライスはカレーとライスに分ける。魚料理は皮・身・骨などを分ける。)
・視覚過敏
食材の見た目が苦手で食べられない、食材によっては食べられるものと認識できない場合があります。
見た目(色)が変わると食べられない場合は、調理法で食べられる食材の色にする、食べられる色の食材に細かく刻んで混ぜる、食べられる色のお皿に料理を盛り付けるなど工夫してみるとよいでしょう。見た目が苦手で食べられない場合は、見た目を変えてみる。(苺ならジュースにするなど)食べられるものと認識できない場合は、絵やイラストを使って「食べられるもの」だと説明することから始めましょう。
・嗅覚過敏
特定のにおいがするものや、においが強いものは食べられない場合があります。においの強いハーブやスパイスは使わない、料理のにおいを感じにくくする工夫をするとよいでしょう。温かい料理よりもにおいを軽減させる冷たい料理に変更する、魚のにおいが苦手な場合は、煮ものにして生臭さをとるといった方法があります。
・味覚過敏
苦味や酸味など特定の味が苦手な場合があります。好きな食材と組み合わせたり、味付けを変えてみましょう。酸っぱい味が苦手なときは、はちみつをかけることにより味が和らぎます。
・こだわり
特定の食感や味のものしか食べない、同じ食品でも決まったメーカーのものしか食べないなど、いつもと同じものしか食べない場合があります。いつもの食事に少しずつ違う食材を入れる、味付けを変えるなどで少しずつ変化を取り入れる方法があります。
偏食の対策についていくつかご紹介しましたが、無理にやりすぎると今まで食べられていた料理にも拒否反応を示すこともあります。無理強いしないことも大切です。一番重要なことは、食事を楽しく食べることです。折角作った料理を食べてくれないとイライラしがちですが、和やかな雰囲気で食事ができるように心がけてください。
発達障害の方に起こりやすい症状を改善させる漢方薬
漢方薬は、一人ひとりの体質や症状に合わせて服用する場合があります。病院に通っている方は、主治医に相談しましょう。
■柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)
ストレスでイライラする、眠れない、などの悩みがある方におすすめの漢方薬です。カラダの中の気を巡らせ、こもった熱を抑え、神経症の症状を改善します。疲れやストレスにより気が滞っている人に向いています。
■抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ)
ストレスでイライラする、気分が落ち着かない、などのお悩みのある方におすすめの漢方薬です。気の巡りをよくすることにより、気分を安定させ、神経症の症状を改善します。ストレスにより気が滞っている人に向いています。
■半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)
気分がふさぐ、のどに違和感がある、などの悩みがある方におすすめの漢方薬です。のどがつまったような感じがする方に向いています。気の巡りをよくして「気滞」を改善し、ストレスや不安による不安神経症の症状を改善することができます。
「漢方ナビ」では、漢方の相談ができる医師を見つけることができます。自分で漢方薬を選択できない方は、漢方や発達障害にくわしい先生に相談するのも一つの方法です。
※漢方ナビで検索頂いた後、お近くの病院へお問い合わせください。
<PR>
-

- 漢方ナビ:漢方を処方する病院検索
自分に合った漢方薬がわからないときは専門家に相談を
- 詳しく見る
兵庫県在住。医療機関、薬局、IT企業での勤務経験を経て、2015年にライターとして独立。体の不調を感じたことをきっかけに、漢方・薬膳に興味を持つ。中医学スクール「薬膳アカデミア」に入学し「国際中医師(国際中医専門員)」を取得。現在は、ライターとして活動をしながら、漢方薬膳の知識を活かしたコンサルタント業務や、ワークショップ・初心者向け講座などを実施。特に女性の体に関する悩みに寄り添った活動を行っている。
実績:クラシエ薬品株式会社主催「KAMPO OF THE YEAR 2024」にゲストとしてトークショーに登壇
執筆書籍:「カラダのために知っておきたい漢方と薬膳の基礎知識」(淡交社)
資格:国際中医師(国際中医専門員)・医薬品登録販売者・漢方養生指導士・薬機法管理者・食品衛生責任者を取得
X:https://x.com/sora_writer
オフィスかなで:https://officekanade.com/