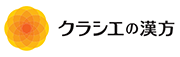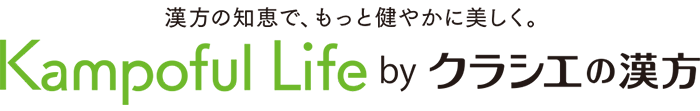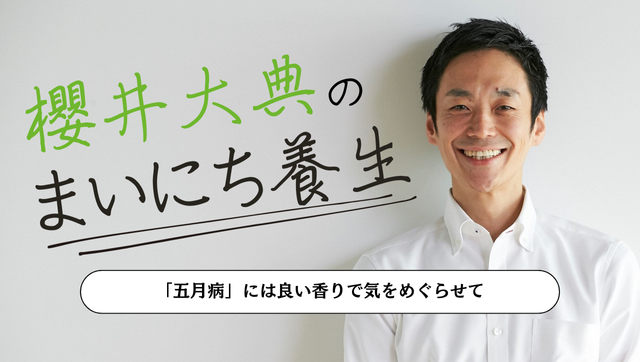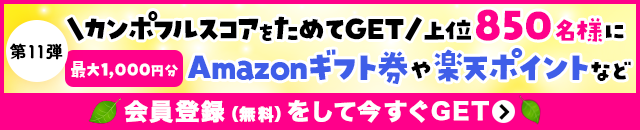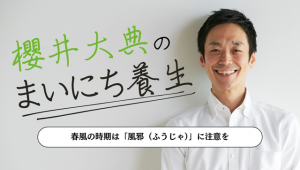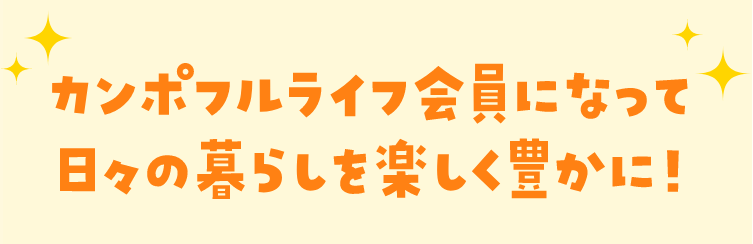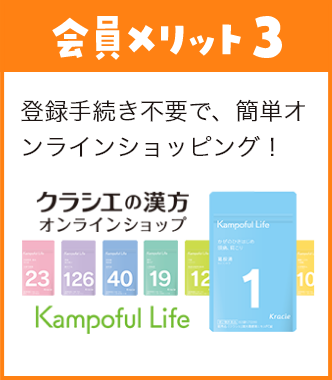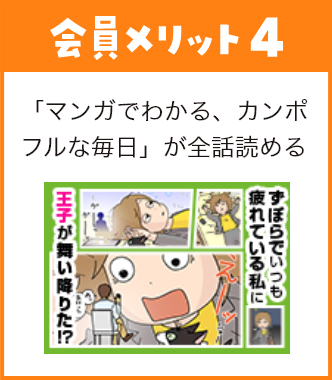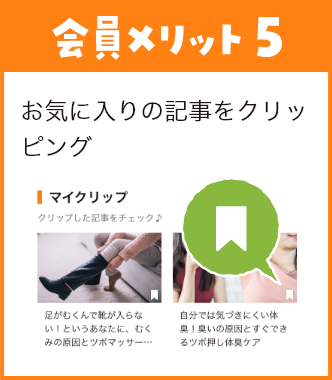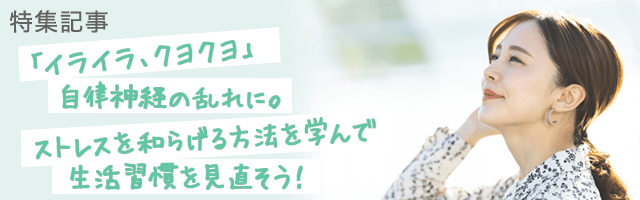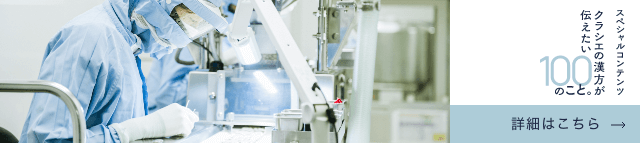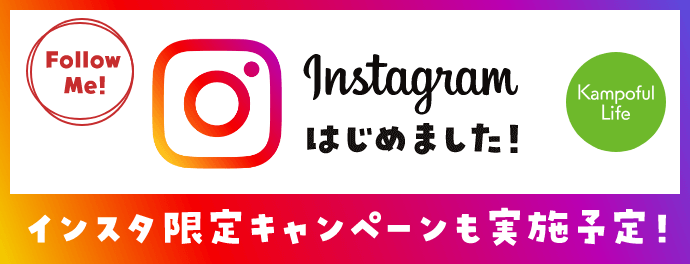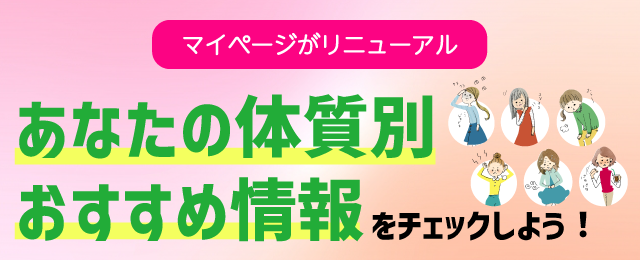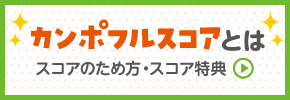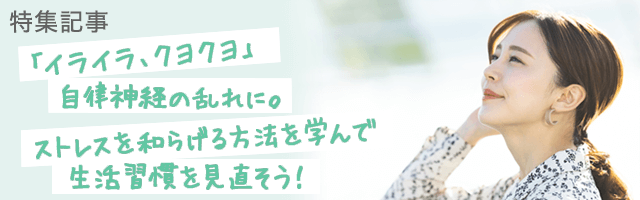目次
人気の漢方家・櫻井大典さんの連載、今回は5月頃からの初夏に気をつけたい体の整え方をご紹介します。活動的に過ごしてほしい時期ですが、心がつらくなったら、こんな養生を心がけてみてください。
心が不調なときは「気」が滞っている
初夏のこの時期は、暑すぎず、寒すぎず、1年で最も過ごしやすい時期といえるでしょう。春のような寒暖差も少なくなり、体が安定します。
本来なら不調の出にくい時期ですが、気になるのが「五月病」です。環境の変化や、新生活のストレスで、ウツウツとしてしまうというものですね。
ただ、こうした身の回りの変化がない方でも、五月病のようになる場合もあります。
この時期は、五臓の「肝」の働きが重要になります。肝は「気」のめぐりに作用するので、肝が弱っていると気が滞ってしまい、やる気がない、気分が落ち込むといった状態になるのです。こうした状態を漢方で「気滞(きたい)」と言います。
他にも、胸や脇が張るような不快感、食欲の低下、胃もたれ、ガスがたまりやすい、下痢と便秘をくり返す、といった不調も、気の滞りと関係があります。
「理気」に働く香りを取り入れる
気滞のときに効果的なのが、良い香りです。
香りには、気をめぐらせる「理気(りき)」という作用があります。これにより、肝が元気を取り戻して情緒が安定したり、胃腸の働きが整って食欲がもどったりします。
香りの良いもので、まずおすすめなのが柑橘類。爽やかで、気分が明るくなり、食欲もわきますよね。
漢方薬の生薬である「陳皮(ちんぴ)」は、みかんの皮を乾燥させたものです。この陳皮をお茶がわりに飲むと、とても効果的です。
でも、漢方薬でなくてかまいません。オレンジやグレープフルーツを食べたり、レモンや柚子の香りをかいだり。柑橘系は精油の種類も多いので、アロマをたくなどして 自由に取り入れ てください。
最近の研究でも、1日に1個、柑橘類を食べる人は、うつが少ないということがわかっているそうです。漢方で昔から言われている効果が、西洋医学的にも証明されてきたということですね。
ハーブ系の香りでいえば、ミントは頭をすっきりさせるし、ラベンダーは気持ちを落ち着かせ、ローズマリーは集中力を高めるといった作用があるとされます。
香味野菜もいいですね。しそは「利湿(りしつ)」といって、湿気を散らす力もあるので、湿度の高い梅雨時にぴったりです。食事で摂ってもいいし、乾燥した葉をお茶にしても。
三つ葉、春菊、パクチー、セロリ、バジルなども料理に使っていきましょう。
スパイスの香りは、胃腸の働きをよくしてくれるので、シナモン、しょうが、八角などを食事やお茶に活用しても。
さらに、食べ物だけでなく、花など自然の香りも有効です。
ポイントは「自分が好きな香り」であること。あなたがいいなと思うなら、どんな香りでもいいのです。
考える時間を1分1秒でも止めるのが大事
もっといえば気を流すためには香りでなくてもいいんです。五感を刺激して、気分が変わることが大事なのです。
気持ちが停滞しているときって、よけいなことを考えてしまうものです。でも、考えれば考えるほど、悪い方向に行ってしまう。
漢方の古典に「思いは気を結ぶ」という言葉があるんですが、これは、考えるほど気が滞るという意味です。
人はどんなに賢くても、2つのことを同時にできない 。だから、別の要素を入れて、1分1秒でも、悪循環になっている考えを止めるんです。
たとえば道を歩いているとき、パン屋さんの店先で、パンが焼ける香りがしたら「あっ、いい匂い!」と気を取られるでしょう。その時、一瞬でも考えていたことを忘れるはずです。
気持ちが何かにとらわれているとき、離れるには、感じることが有効なんです。
五感を刺激するのに手っ取り早いのが、食べる「食感」です。だから、みなさんストレスを感じたとき、食べ物に走りがちですよね。
でも、食べ物は、それ自体がまた別の滞りを生むことになる。食べすぎて胃がもたれたり、体がだるくなったり。また、ストレスで食べがちな“甘い物”は、それ自体がお腹の中で滞りのもとになってしまいます。
その点、香りには弊害がない。さらに、香りは五感の中でも、ストレートに脳につながる刺激とされています。手軽で即効性も期待できるのです。
私はロールオンタイプのアロマグッズを持ち歩いて、気分転換に使っています。これなら周りの人に気兼ねすることなく、自分だけの好きな香りを、どこでも楽しめます。
空気を変えて気の流れをよくする
気滞の対策としては、換気も行ってください。さらに深呼吸して、体の中も換気しましょう。
気分がモヤモヤしてきたら、離れた窓を2カ所開けて、部屋の気を通して、深呼吸。それだけで、堂々巡りしていた考えに風穴が空いたり、新しいアイデアが出てきたりします。
ストレッチなどで体を少し動かすのも、気を通すよい方法です。
ウツウツとしてやる気の起きないときは、大きな変化をさせようと思わなくていいんです。小さなことでできる「理気」を取り入れていくうちに、気持ちがゆるゆると変わっていきますよ。
この時期はどんどん活動するのが養生
ところで、漢方では5~7月が夏とされています。この季節は、春に芽吹いた物を伸ばし、広げて成長させていく時期です。
どんどん活動して、いろんな人に会って、たくさん話をして、新しいことを始めて進めていきたいとき。それが、この時期の“養生”です。
養生というと、体を休めることと思われがちですが、人の体には季節に応じた流れがあって、この時期は活動的に過ごすことが、次の時期につながる養生なんです。
ただし、五月病で気分がすぐれない人は、無理することはありません。気の流れをよくして、元気を取り戻したら、動き出せばいい。
いまの自分に合った養生を取り入れて、心地よい体を作っていきましょう。

漢方コンサルタント、国際中医相談員、日本中医薬研究会会員。
アメリカ・カリフォルニア州立大学で心理学や代替医療を学び、帰国後、イスクラ中医薬研修塾で中医学を修める。漢方セミナーを開催し、年5000件以上の相談を受けて漢方での健康づくりの普及に務めている。プライベートでは、好きな和菓子や夜更かしの楽しみと養生を両立。趣味のバイク一人旅は、愛娘のイクメン作業優先で自粛中。著書に『まいにち漢方―体と心をいたわる365のコツ 』『病気にならない食う寝る養生』『二十四節気の暦使い暮らし』など多数。
HP:
https://yurukampo.jp/
X:
https://x.com/pandakanpo
Instagram:
https://www.instagram.com/pandakanpo/
撮影(トップ画像)/長谷川梓