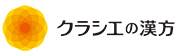咳が出る理由は?
止まらない咳の対処法と
咳の種類を解説
最終更新日 2025年04月28日
目次
咳は身近な症状のひとつなので、そのうち治るだろうとはじめはあまり気にしないかもしれません。しかし、咳だけがずっと残っている、痰がからむしつこい咳が続いている、咳で寝られないなど、咳が原因で日常生活に支障が出ることも。
少しでも早く咳から解放されるには、咳の原因を知り、適切な対処をすることが大切です。ここでは咳の種類や原因、つらい時の対処方法について詳しく解説します。
どうして咳が出るの?
咳は、ほこりやウイルス、細菌などの異物が、体に入ってこないように働く防御機能です。気道内に侵入した異物は、気道にある咳受容体を刺激し、その信号が脳にある咳中枢に伝えられ、咳が出ます。異物のほかにも、気道に炎症が生じたり、気道に溜まった痰を出す為にも咳がでます。咳中枢は、大脳皮質によってコントロールされているため、心因性ストレスによって咳が発生することもあります。
咳が出るメカニズム

あなたの咳はどんな咳?咳の種類と症状
咳に対処する際、持続期間や咳の仕方、痰の有無などで「咳の種類」を見極めるのがポイントです。
〈 症状持続期間と感染症による咳嗽比率 〉

咳の持続期間から分類する
咳は「どのぐらい続いているか」という持続期間で、急性、遷延性(せんえんせい)、慢性の3つに分類されます。
咳の持続期間によって原因が大体推測できるといわれており、咳の持続期間が長くなればなるほど、原因に感染症が占める割合は少なくなってきます。
3週間未満の
「急性咳嗽(きゅうせいがいそう)」
3週間未満の咳を「急性咳嗽」といいます。
その原因はウイルスや細菌によるかぜなど、急性上気道炎による咳がほとんどです。ウイルス感染による咳の場合、発熱、くしゃみ・鼻水、のどの痛み、頭痛、倦怠感などをともなうことで判断できます。
ただし、3週間以内であってもひどい咳が続いている、咳をして吐く、痰に血が混じる、高熱が続いている、膿性の痰が出るなどの症状がある場合にはインフルエンザや肺炎など重篤な感染症や他の病気が疑われます。
胸のレントゲン写真を撮ったり喀痰検査(かくたんけんさ)などをおこない、原因を突き止めて適切な治療をする必要があるので、医療機関を受診しましょう。
3週間以上8週間未満の
「遷延性咳嗽(せんえんせいがいそう)」
3週間以上8週間未満の咳を「遷延性咳嗽」といいます。
咳が3週間以上長引くときは、咳喘息やアトピー咳嗽、副鼻腔炎による後鼻漏など感染以外が原因である場合があります。
咳以外の発熱や胸痛、頬の圧迫感などの症状、咳が出やすい時間帯や状況、咳の仕方や痰の性状に気を付け、医療機関を受診するようにしましょう。
8週間以上続く
「慢性咳嗽(まんせいがいそう)」
8週間以上の咳を「慢性咳嗽」といいます。
慢性咳嗽は、感染が原因であることはほとんどありません。原因として多い病気は咳喘息、アトピー咳嗽、胃食道逆流症、感染後咳嗽です。
喀痰のない慢性咳嗽ではX線検査などで感染症の疑いを除外した後、治療的診断をおこないます。たとえば、吸入ステロイド(必要に応じて気管支拡張剤を追加)により治療を開始し、2週間程度で効果があれば咳喘息が確定されます。
一方、喀痰があり、X線検査で感染症の疑いが除外できない場合、喀痰検査や血液検査で慢性咳嗽の原因を探ります。副鼻腔炎や気管支拡張所見、好中球性気道炎症などの異常所見があれば、副鼻腔気管支症候群の可能性もあります。抗菌薬を8週間投与し、症状が改善すれば副鼻腔気管支症候群が確定されます。
咳の仕方や音から分類する
咳は、咳の仕方や音などから2つに分類されます。痰の有無によって、咳の仕方や音が異なるためです。
痰をともなう咳は、分泌物の量が多いため気道が狭くなり痰を気道外に出すためにゴホゴホという音がする「湿った咳」になります。一方、痰がないか少ない咳は、コンコンやケンケンという音がする「乾いた咳」になります。
痰をともなう湿った
「湿性咳嗽(しっせいがいそう)」
痰をともなう咳を「湿性咳嗽」といい、「ゴホゴホ」といった湿った咳が出ます。痰や鼻汁といった気道からの分泌物を体外に出そうとする反応です。
痰をともなう咳が3週間以上続く場合には、副鼻腔炎や気管支拡張所見をともなう副鼻腔気管支症候群の可能性もあり、抗生剤の投与等が必要になるため、専門医を受診する必要があります。
コンコンと乾いた
「乾性咳嗽(かんせいがいそう)」
痰が出ない・少ない「コンコン」と乾いた咳を「乾性咳嗽」といいます。湿性咳嗽と同様に、気道に炎症が起こっている状態ですが、咳喘息、アトピー咳嗽、胃食道逆流症、感染後咳嗽など、感染症以外が咳の原因であることが多いです。
その咳、かぜではないかも?長引く咳のチェックポイント
咳はかぜが原因とは限りません。特に、咳が3週間以上続く場合、かぜ以外の病気が原因である可能性が高いです。
通常、かぜによる咳はかぜ自体が治ると自然に収まりますが、咳だけが続く場合は注意が必要です。
以下のような咳の症状は、かぜ以外の原因を疑う必要があります。
- 咳だけが長期間長引く
- 咳や痰の症状が3週間以上続いている
- 血が混じる痰や色の濃い痰が出る
- 咳の頻度が増えてきた
- 呼吸がしづらく感じる
- 階段の上り下りなど軽い運動で
動悸や息切れが起こる - 胸に痛みをともなう
これらの症状が見られる場合は、かぜ以外の病気が原因となっている可能性があるため、専門の医師に相談することをおすすめします。
熱がないのに咳が出るのはなぜ?
咳が症状としてあるのに熱がない主な原因は、感染症以外の気道の炎症やアレルギー反応です。
気管支喘息や咳喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの慢性的な呼吸器疾患では、気道に炎症が起きて咳が発生しますが、通常は発熱しません。同様に、アトピー咳嗽などのアレルギー反応による咳も、一般的に熱をともないません。
また、胃食道逆流症(GERD)による咳も、胃酸や食道内容物の逆流による刺激が原因であり、発熱はともないません。
咳は体が異物を排出しようとする防御反応であり、特に気道の慢性炎症やアレルギーが原因の場合は熱が出ないことが多いです。咳が長引く場合は、これらの可能性を考え、医師に相談することをおすすめします。
長引く咳、止まらない咳の原因と症状
咳が長引く場合、単なるかぜ以外にもさまざまな疾患が考えられます。ここではかぜ以外で疑われる主な疾患について解説します。
咳喘息
咳喘息は、8週間以上咳が持続する慢性咳嗽の最も多い原因です。痰をともなわない乾性咳嗽のことが多いです。咳喘息は、一般的な気管支喘息とは異なり、「ゼーゼー」や「ヒューヒュー」といった喘鳴(ぜんめい)や呼吸困難がなく、主に長く続く咳だけが症状として現れる病気です。
就寝時や深夜、早朝に咳が出ることが多く、季節ごとに発症する方や1年中症状のある方もいるようです。かぜ、冷気、喫煙、雨天やじめじめした天候、花粉や黄砂の飛散などで、悪化することがあります。
主な治療法・注意点
- ステロイド薬や気管支拡張薬の吸入剤や飲み薬で治療
- 喘息に移行することもあるので、医師の指導のもと治療する
アトピー咳嗽(アレルギー)
アトピー咳嗽は、8週間以上持続する慢性咳嗽の原因のひとつで、のどにイガイガ感やかゆみなど違和感をともなうのが特徴です。中枢気道にアレルギー性炎症が起こり、長期間続く乾いた咳が出ます。
症状は咳喘息と同様、「ゼーゼー」などの喘鳴や呼吸困難はなく、痰をともなわない乾性咳嗽のことが多いです。
就寝時や深夜、早朝に咳が出ることが多く、エアコン、喫煙、電話での会話、運動、精神的緊張などで悪化することがあります。喘息以外のアレルギー疾患がある方も多いです。
主な治療法・注意点
- 第1選択薬は抗ヒスタミン薬
- 吸入ステロイドも効果的
- 気管支拡張薬は無効(咳喘息との違い)
副鼻腔気管支症候群(ふくびくうきかんししょうこうぐん)
副鼻腔気管支症候群は、上気道の副鼻腔炎に下気道の気管支炎などが合併した状態で、8週間以上持続する慢性咳嗽のひとつです。
呼吸困難はなく、痰をともなう湿性咳嗽です。
副鼻腔炎の症状として、鼻水やのどの後ろに鼻水が流れる後鼻漏(こうびろう)、咳払い、鼻やのどの奥にひっかかる粘りの強い分泌液などがあります。
主な治療法・注意点
- 少量の抗菌薬の長期間服用
- 去痰薬(きょたんやく)を併用
胃食道逆流症(いしょくどうぎゃくりゅうしょう)
胃食道逆流症は、胃酸や胃の内容物が食道に逆流して、胸焼けやげっぷ、咳払い、のどの痛み、声がれなどの症状が起きる病気です。乾いた咳が8週間以上持続する慢性咳嗽の原因のひとつです。
乾いた咳に、胃食道逆流症の症状をともないます。夜間の咳はないか、あっても少ないことが多い傾向にあります。また、横になったときに悪化することがあります。
主な治療法・注意点
- 胃食道逆流症の治療
- 胃酸分泌を抑える薬や消化管運動機能改善薬の服用
- 減量などの生活習慣改善
- アルコール、高脂肪食など食生活の見直しなど
感染後咳嗽
感染後咳嗽は、かぜなどの呼吸器感染症に引き続いて起こる遷延性・慢性咳嗽のひとつです。かぜの後に咳だけ残っている状態で、遷延性・慢性咳嗽の原因と考えられる病気が他になく、症状が自然と良くなる傾向であることが特徴です。
感染後咳嗽の原因は一般的なウイルス感染が最も多いですが、百日咳、マイコプラズマ感染症などに続いて起こることもあります。
感染後咳嗽の原因は完全には解明されていませんが、気道粘膜の炎症や損傷、咳反応の過敏化などが考えられています。
主な治療法・注意点
- 自然に回復することが多い
- 咳止め薬、抗ヒスタミン薬などの服用
その他
通常のかぜや感染後に残る咳は、時間が経つと自然に回復することが一般的です。しかし、咳が長引く場合には、さまざまな肺疾患が原因である可能性があります。
例えば、間質性肺炎、結核、肺がん、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、非結核性抗酸菌症である肺MAC症などが挙げられます。これらの疾患は、自然回復が期待できないため、医師による診断と治療が必要となります。
肺疾患は、放置すると症状が進行するため、早期診断と治療が非常に重要です。咳が長期間続く場合や他の症状が現れる場合は、医療機関を受診し、専門的な診察を受けることが推奨されます。
つらい咳を和らげるために自分で
できる対処法
咳は体力を消耗するため、長引くと睡眠不足になったり、日常生活に支障が出ることがあります。つらい咳を和らげて少しでも楽に過ごすために、先述した治療法以外で、自分でできる対処法を紹介します。
漢方薬を活用する
漢方医学では、咳や痰の症状だけに着目するのではなく全身状態を改善することで、咳や痰を和らげることを目指します。
せきで用いられる漢方薬の選び方は、体質や咳の種類や原因に応じて異なります。
体質では体力の有無など、個々の体質差を考慮して選びます。
またせきの症状の観察では咳の種類(乾いた咳、湿った咳)、痰の有無、痰の色(透明、黄色)咳の頻度や強さを観察します。
ここでは、咳や痰に効果が期待できる漢方薬を紹介します。
麦門冬湯(ばくもんどうとう)
麦門冬湯は、麦門冬 (ばくもんどう)、粳米 (こうべい)、大棗 (たいそう)、半夏 (はんげ)、人参 (にんじん)、甘草 (かんぞう)の6種類の生薬が配合された漢方薬です。
痰が少なく、のどが乾燥して強くせき込む乾いた咳に体の中から潤いを与えることで、呼吸器やのどの乾燥を改善し咳を和らげることが期待できます。
詳しくみる
竹葉石膏湯(ちくようせっこうとう)
竹葉石膏湯は、竹葉(ちくよう)、甘草(かんぞう) 、石膏(せっこう) 、半夏(はんげ)、麦門冬(ばくもんどう)、人参(にんじん)、粳米(こうべい)が配合された漢方薬です。
かぜを引いた後に咳や微熱が続いている場合や、痰が切れにくいと感じるときにおすすめです。のどの粘膜を潤し、からぜきや気管支炎を改善する効果が期待できます。
詳しくみる
五虎湯(ごことう)
五虎湯は、麻黄 (まおう)、杏仁(きょうにん)、桑白皮(そうはくひ)、石膏(せっこう)、甘草(かんぞう)の5種類の生薬が配合された漢方薬です。
黄色い粘り気の強い痰が出て強くせき込む激しい咳に、気管や気管支、のどの炎症を抑えて咳を鎮めることが期待できます。
詳しくみる
寝るときの体勢は横向き
寝るときには、気道が確保できる横向きがおすすめです。
うつ伏せや仰向けより、夜間の咳を和らげることができます。また、クッションなどを重ねて上半身を斜めに立てるようにすると呼吸が楽になり、鼻水や痰がのどに流れにくくなります。
のどや胸を温める
のどが冷えていると、気管支の粘膜が刺激に敏感になって咳が出やすくなります。首にタオルやネックウォーマーを巻いて寝たり温かい飲み物を飲んだりして、のどを温めてみてください。
濡れマスクで加湿する
濡れマスクには、のどや鼻を潤して乾燥を防いだり、冷気の刺激から気道を守ったりする効果があります。不織布のマスクに濡らしたガーゼをはさんでもよいでしょう。
水分やはちみつでのどを潤す
のどの乾燥が刺激となって咳を引き起こすことがあるため、少しずつ水を口に含みのどを潤しましょう。
また、水分を摂ると痰が薄まって吐き出しやすくなるメリットもあります。水分は、冷たいものは避けて、室温や温かい飲み物にしましょう。はちみつには保湿の効果があるため、スプーン1杯程度のハチミツをお湯に溶いて飲むのもおすすめです。
ただし、1歳未満の乳児がはちみつを食べることによって乳児ボツリヌス症にかかることがありますので、1歳未満の乳児には与えないでください。
アルコールを控える
アルコールは体の防御機能を弱めることがあり、喉を刺激して咳を悪化させる可能性があります。また、アルコールによって体が脱水状態になると、痰の粘りやすさや咳の治まりにくさが増すこともあるので、注意が必要です。
禁煙する
咳が止まらないときは、禁煙することが非常に重要です。タバコの煙は喉や気管支を直接刺激し、炎症を悪化させ、咳がさらにひどくなる原因となります。
また、喫煙することで肺の防御機能が低下し、咳を悪化させる要因ともなります。タバコをやめることで喉や気道の負担が軽減され、咳が治まりやすくなるでしょう。
運動やストレッチで肺機能を高める
運動やストレッチを取り入れることで、肺を強化し、咳の改善につながることがあります。運動をすることで、呼吸に関わる筋肉を鍛え、咳をしにくくなることが期待できるのです。
ただし効果的におこなうには、どのくらいの頻度でどのように運動するかを注意深く決める必要があります。医師や専門家に相談し、自分の体に合った安全で効果的な運動プランを立ててから始めましょう。
病院を受診する目安は?こんな時は医師に相談しよう
咳が3週間以上続く、血が混じった痰が出る、または色の濃い痰が気になる場合、それは単なるかぜではないかもしれません。
最初に述べたチェックリストに一つでも当てはまるような咳がある場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。これらの疾患の進行を防ぐためにも、早期発見と適切な治療開始が非常に重要となります。
まとめ
咳が出るのは、口や鼻から吸い込んだウイルス、ゴミなどの異物を排除するための生体防御反応です。咳の治療は、原因となる病気に対して適切な治療をする必要があるため、咳が長引くときには医療機関を受診することをおすすめします。
適切な治療に加えて、咳を少しでも楽にする方法もあります。漢方薬は長引く咳や痰が絡む激しい咳などに、体の水分を整え炎症を鎮めることで咳や痰を和らげることが期待できます。普段の体力と咳の状態に合わせた漢方薬を選ぶようにしましょう。
出典:
診療ガイドラインup to date/Ⅱ呼吸器疾患 1咳嗽・喀痰
健康長寿ネット/肺炎のケア
小谷敦子
薬剤師免許取得後、病院薬剤師として就職。ライフステージの変化にともない、調剤薬局の薬剤師とメディカルライターとしての実績を積んできた。東洋医学専門診療科のある大学病院の門前薬局では、漢方薬の処方に対する数多くの服薬指導を経験。
下田篤男
京都大学薬学部卒業。 卒業後は薬剤師として調剤薬局グループで勤務。現在も薬剤師として現場で働く傍ら、その知識や経験を活かして、医療記事や美容記事の執筆、編集や薬局経営コンサルタントなど幅広い業務に携わる。